筆者三辻孝明さんは、一昨年の2019年8月に癌の告知を受けました。以後、自然療法や抗癌剤治療を経て癌の摘出手術を受けるなど、その約10ヶ月間、「静かに死を見つめながら、久しぶりに文章を残すことができました」と話しています。また「レポートに毛の生えたようなものですが、過去の自分自身の経験を形にできたことは、少し肩の荷が降りたような気持ちです。よろしければ、ご一読ください」と語っていました。
そして、2020年7月16日に当「硫黄島ダイアリー」の連鎖がスタートすることになりましたが、翌月の8月10日、残念ながら三辻孝明さんは帰らぬ人となってしまいました。
闘病生活中に死を見つめながら書き上げられた当連載「硫黄島ダイアリー」ですが、生前の故人の遺志を受け継ぎ、パースエクスプレスでは連載を継続掲載致します。読者やユーザーの皆様には、引き続き「硫黄島ダイアリー」をご愛読頂けると幸いです。
<第四章『CHEMISTRY』5話はこちらから>
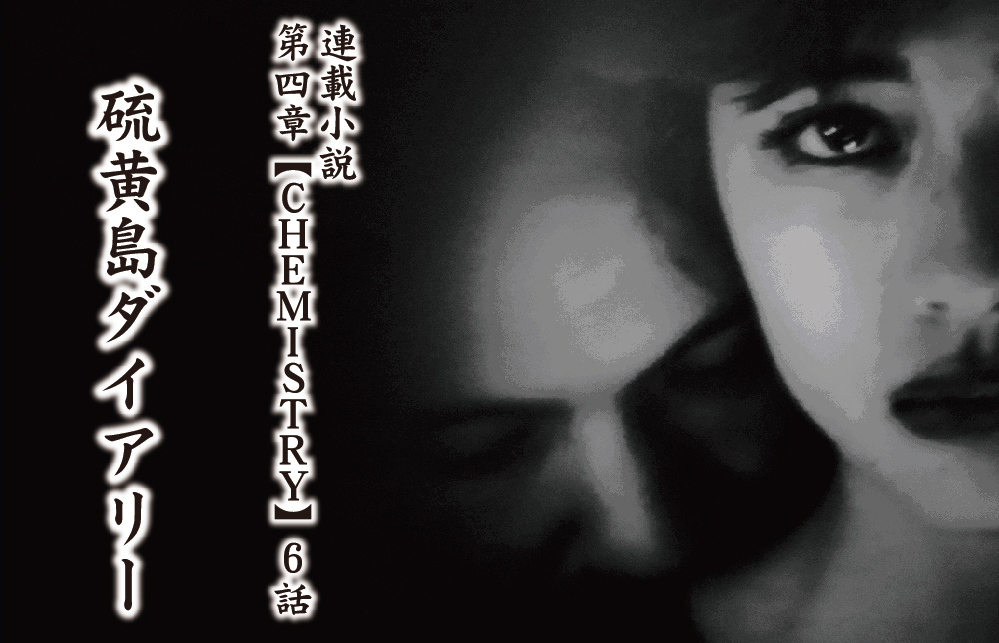
【連載小説】
硫黄島ダイアリー
三辻孝明
第四章『CHEMISTRY』6話
シャロンが帰ってから10日が経っていた。キヨシ少年からはあれ以来、何の連絡もない。人は過去を振り返る時、神の目で物事を見ることができるという。何かの本にそう書いてあった言葉を思い出す。
どうしてああなってしまったのだろう?キヨシ少年の話していた、腕に這い上がってくるさそりを殺してはいけないという話は、あの日のシャロンの事を指していたのだろうか?
でもひとつだけはっきりしているのは、今自分の心の大半を占めているのは、分かれた妻のことではなく、淡い憧れを抱いていたローズマリーのことでもなく、あのウニのようにとげのあるシャロン・ワイズブロットだった。彼女のことは一線を越えるまで、女性として意識したことはなかった。
でもあの日以来、それまで知らなかった彼女の体温や、息遣い、ペニスに残る子宮の感覚が、ひとり横になったとたんに生々しく蘇ってきてしまう。あの夜、確かに自分の腕の中にいた裸のシャロン、無意識のうちに自分を探す彼女の指の感覚を、僕は忘れることができない。
それは愛しているとか、自分の女にしたいとか、そういう気持ちとは違った感覚だった。ただただ切ないのだ。あの人は、どうしてあんなに一途なのだろう。言葉が見つからない。こんな安アパートのベッドで、一心に抱かれていたあの人が、だから切ないのだ。肉体は正直だ。だからあれ以来、知らないうちに彼女を探してしまう。僕の肉体の知っている彼女は、素直で、寂しがり屋で、ぜんぜん理屈っぽくなくて、切ないくらいに可愛いひとりの女の子だった。彼女とは気持ちが通じてから結ばれたわけではなかったから、なおさらそのメッセージは強烈だったのかもしれない。
でも、これは神の目で見ていることとは違う。なぜなら、シャロンが僕の体や心に残した足跡は過去のことではなく、今、現在も生きているからだ。こう書き記しているその間にも、彼女の残した感覚は少しずつ形を変え、刻々と輪郭を見せ始めている。だから僕は過去を振り返っているのではなくて、あの日以来時間が止まったまま、彼女との明るい未来を感じることもできずに、ずっとそれを見つめているだけなのだった。
その日の午後、玄関のドアをノックされ、急いで出てみるとドアの外に立っていたのはシャロンではなく、友人のローズマリーの方だった。彼女は桔梗の花を持っていた。桔梗だなんて、神の演出にしてはでき過ぎている。
「スグカエル。」
僕はたぶん遠慮のない目で彼女を見ていた。
「どうしてここが分かったのですか?」
そうたずねる自分の声が震えている。
「シャロンガオシエテクレタ。」
「シャロン?」
「カノジョハマリオノコトデ、ココニキタコトガアッタ。カノジョハ、ミチヲオボエテイタ。イマ、サカノシタデワカレタ。」
「そこの坂の下ですか?」
「ソウ、デンワノアルトコロデス。」
********
やっと止まったタクシーのドアが開き乗り込んだ時、後ろに人の気配を感じた。そしてその刹那、強い力で腕をつかまれた。立っていたのはタカだった。あいつは言葉を口にできないほどに息が上がっていた。ずっと走ってきたに違いない様子だった。
「お客さん、どうするの?」
運転手の不機嫌な声がする。
「少し待ってください。」
あいつの顔から汗が噴出している。
「だいじょうぶ?」
私が聞くとあいつは白い歯を見せて笑った。
「君の方は?」
「ええ、ちゃんと生きてるわ。」
あいつが車から離れるのを待ってドアは閉まりタクシーは走り出した。振り返るとあいつはそのまま、車道に立って私に手をあげている。そして坂を登りきった瞬間、タクシーの視界からあいつの姿は完全に消えていった。全くの茶番だわ。私は後ろの景色を振り切るように前を向いた。自分の意思に反して涙が溢れていた。
だってこんな体じゃ、もうどうしようもないじゃない。こんなに暑いのにウィッグまで被って、それでまだ恋愛ごっこ続けるつもりなの?自分が死にたいくらいに惨めだった。声を上げて泣きたかった。そして今はただ、一刻も早くひとりになりたかった。
********
シャロンが骨髄の癌に侵されていると知ったのは、それから何日かしてドアの下に挟まっていたローズマリーからの置き手紙によってだった。
「友達だからどうしても伝えたかったのです。」
気がつくと辞書を引きながら横文字の便箋を追う手が震えていた。
強い薬の副作用で、苦しんでいることも初めて知った。最初に癌が見つかったのも、その肺の癌を摘出したのも、彼女が大学生の時。そして東京に来てから骨髄に転移しているのが見つかってしまったらしい。でも、彼女は負けてはいない。病気と一緒に生きている。無茶もしているけど、彼女はきっと自分が健康な体に戻ると信じている。だから、これからも普通にしていて欲しい。
手紙の最後に、ずいぶん悩んだけれども、あなたにだけは知らせておいた方がいいような気がして書きました。と、結ばれていた。
日を追うごとに真夏の暑さは、容赦がなくなっている。シャロンは命を懸けてあの日僕の腕の中に飛び込んできたのだろうか?いや、そうではなくて、シャロンはあらゆることに今、命をかけて臨んでいるに違いない。そうだとしたら、僕は、彼女の伝えたかったことを、果たして受け止めきれたのだろうか。
僕はまた、ここでも何か大切なメッセージを見落としてしまっていたのではないのか?どうすれば、キヨシ少年やシャロンのように、“今の連続”に、もっともっと深く入っていく姿勢を身につけることができるのだろう、、、
どうして生きていくこと、人と人との間に生まれてしまうこのCHEMISTRYというやつは、こんなにも繊細で、後戻りや巻き戻しがきかない一発勝負の世界なのだろう、、、
考えなければいけないことはわかっていたけれども、矛盾するようだけれども、その場に立った時には、考えるという時間がいつも全くないのだった。本能で瞬時に対応を繰り返せるように、自分を磨いていくということも、きっとこれからは意識していかなければいけないのかもしれなかった。
それにしてもローズマリーはなぜ、ほとんど口を聞いたこともない僕の、この部屋を訪ねて来たのだろう。自分にはわからなかった。そういえばあの日彼女は来た途端、すぐに帰りますとも言っていた。何か聞きたい事があって訪ねてきたのは、間違いないようであった。
彼女が置き手紙をわざわざ置いていった日、僕は終日仕事で留守にしていた。きっとその時も、何か聞くことがあって尋ねて来ていたに違いない。ここ数日の間に何度も訪ねてくるなんて、何か急を要する用事があったのだろうか。あるいは、何か問題を抱えて困っているのだろうか。
あれ以来、シャロンのことばかり考えていた僕は、ふと強い胸騒ぎを覚えた。
置き手紙にも彼女の住所は書かれていなかったし、その時の自分にとってローズマリーに連絡を取る方法は、麻布署の刑事に聞く以外、もう残されていないことだけは分かっているつもりだったけれども。
| 三辻 孝明(みつじたかあき) 「CUBE IT AUSTRALIA」のCEO(最高経営責任者)。早稲田大学人間科学部環境科学科卒業。1989年より豪州在住。2020年8月10日永眠。 |
【関連記事】
関連記事:【新型コロナウイルス関連】日豪物流業界のパイオニア。死と向き合い、激動のパンデミックの中を生きる。
関連記事:ドロップアウトの達人
関連記事:Madison






