筆者三辻孝明さんは、一昨年の2019年8月に癌の告知を受けました。以後、自然療法や抗癌剤治療を経て癌の摘出手術を受けるなど、その約10ヶ月間、「静かに死を見つめながら、久しぶりに文章を残すことができました」と話しています。また「レポートに毛の生えたようなものですが、過去の自分自身の経験を形にできたことは、少し肩の荷が降りたような気持ちです。よろしければ、ご一読ください」と語っていました。
そして、2020年7月16日に当「硫黄島ダイアリー」の連鎖がスタートすることになりましたが、翌月の8月10日、残念ながら三辻孝明さんは帰らぬ人となってしまいました。
闘病生活中に死を見つめながら書き上げられた当連載「硫黄島ダイアリー」ですが、生前の故人の遺志を受け継ぎ、パースエクスプレスでは連載を継続掲載致します。読者やユーザーの皆様には、引き続き「硫黄島ダイアリー」をご愛読頂けると幸いです。
<第四章『CHEMISTRY』4話はこちらから>
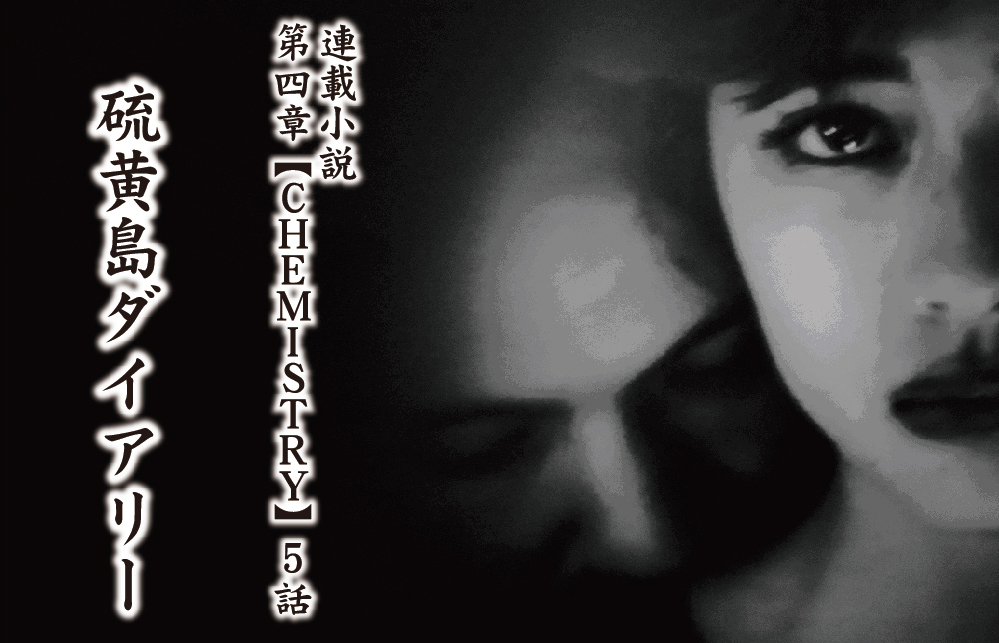
【連載小説】
硫黄島ダイアリー
三辻孝明
第四章『CHEMISTRY』5話
シャロンからは連絡が来ない日が続いていた。結城の事があったから三田のアパートメントに行くわけにはいかなかったし、留守番電話にメッセージを残しても彼女からの連絡はないままだった。もしかしてまた体調が悪くなってしまったのだろうか?
Fateのあった七夕の頃から2週間が過ぎようとしている。ローズマリーはあのあと2回、古川先生の入院している新宿の病院を訪ねた。2回とも先生が眠っている間にうかがい、起こさないように病室の花を取り替えて帰ってきただけだった。先週活けてきた花はひまわりだった。ひまわりは太陽を連想させる。観ているだけで元気が沸いてくる気がして、ひまわりを選んでみたのだけれど、先生の様態が良くなっているようには見えなかった。
昼間、広尾の図書館で硫黄島の資料を集めてみた。資料の日本語を読むことは不自由だけれども、その分夏休みで時間はあるから苦にはならない。あの偽刑事さんは硫黄島で仕事をしていた。滑走路の拡張工事が進められているその島に、一般の住人は入れない。その工事は、厚木基地の夜間発着訓練による騒音公害の代替えのためのようだった。硫黄島が厚木基地の代わりに夜間発着訓練をする場所として選ばれたということらしい。彼が島に渡ったのも、滑走路の拡張工事のための労働力を補充するためのものだった。
古川先生の生徒さんが渡った島。
そのことが死を迎えようとしている先生の唯一の心残りになっている。どうしてシャロンは連絡をしてくれないのだろう?シャロンは偽刑事の住んでいる場所を知っている。シャロンはマリオの部屋に行ったことがあるのだから、その場所は覚えているはずだった。どんな些細なことでもいい、先生の生きているうちに彼と会って島のことを少しでも聞いておきたい。
ローズマリーはシャロンに手紙を書いた。短い手紙には、有栖川公園のいつもの場所に夕方には必ずいるとだけ書いておくことにした。
********
いくら強いことを言ってみても、私はまだ子どもだった。
シドニーでキースと過ごしてから以降、最近の私はあまりにもそのときの気分に流されている気がしてならなかった。いくら病気の影におびえているとはいえ、こんなことを繰返して、幸せが待っているわけがなかった。私には、でもその理由が分かっていた。立ち止まって考えるのが怖かったのだ。
勢いをつけたまま動き続けていれば、見なくてすむ事がたくさんあることを私は知っている。だから、ほとんどの人は忙しそうに毎日、自分の予定を埋めて暮らしている。そうすれば、立ち止まって考える暇がなくなるから。自分のいいかげんさ、弱さを目の当たりにしなくてすんでしまうから。まるで電車の窓から見える景色と一緒だった。電車が早く走れば走るほど、見える景色は現実を離れて、まるで写真や絵画を見ているような、自分とは関係のない距離のあるものになっていく。でも電車がブレーキをかけ、止まりはじめると、今まで見えなかった景色が細部にわたるまで見えてきてしまう。若い頃に見える眺めや心の中にある夢って、きっとスピードを上げて走る電車から見える景色のような気がする。全てが美しく見えることが、若さの証左なのかもしれない。
ローズが扉を閉めたまま息を潜めて暮らしている理由について考えてみる。彼女は、男の欲望を受け入れることにあわせて生きてしまうと、荒れて落ちていくイメージだけが残ってしまうと、繰り返し話してくれた。振り返って私とキースとの関係はきっとそうだったんだと思う。シドニーにまで出かけて、あんなにがんばった自分が惨めだけれど、正直に告白するとふたりの間にあったのは、悲しいくらいの惰性だった。
ローズが言っていた「やさしい気持ちがほしい」という言葉が、今は身にしみてよく分かる。その優しい気持ちの向こうに深い関係があるのだとしたら、私は、いや、女性は自由に自分を解放できる気がする。いや、女同士だっていいと思う。心から信じられる人となら、思い切り自分を解放できると言うことが言いたかっただけだから。
タカはそういうことのできる男なのかもしれなかった。あいつはあの夜、私を求めてはいなかった。むしろ積極的に求めていたのは、私の方だった。うまく日本語では伝えられないけれど、私は彼とのことがうっとうしかったのかもしれない。
いつまでも誰かのことで気持ちが落ち着かないような状態を、早く終わらせたかったのかもしれない。乱暴な考えだけれども、結局やってしまえば、なんだスポーツみたい、みんななんだかんだ言っていても同じじゃないって思えると信じていたのかもしれない。でも、そうすることで、私は自分の心の中の大切な何かを壊してしまった気がする。認めたくないけれども、私の中で静かに咲いていた大切な花を踏んづけてしまった気がする。タカとああなってしまった時、私に残ったのはすっきりした気持ちなんかじゃなかった。空高くまでロケットを打ち上げた後の気持ちなんかじゃなかった。ただ、無神経な靴で踏みにじられた花畑が見えていた。そして、その靴はタカのものではなくて私自身の靴だったのだ。
郵便受けにローズからの手紙が届いていた。有栖川公園で待っているという。いつまでもこうして連絡しないのは、良いことではないに違いなかった。でも、今ローズに会ったら自分がどうにかなってしまいそうでそれも怖かった。
ローズは理不尽な関係にさらされながらも、決して自分を見失うことはしななかった。傷ついて血を流しても、けして体の誘惑に妥協することもしなかった。今の私は安易に答えを求め、道をはずしてしまったのかもしれない。だから今、ローズに会うことが、私の心の中を全て見透かされてしまいそうで、本当に怖かった。
「Iwo-Jima?」
「Yes, Iwo-Jima.」
ああ、そうだったと思い出した。公園であったローズは真っ先にタカの働いていた硫黄島の名前を挙げたのだ。この2週間ずっと図書館で調べていたとも話してくれた。
「シャロン、もしよかったらこれから彼の部屋に連れて行ってくれない?」
なんですって?私は言葉を失ってしまった。いくらなんでも、どうして、よりによってこれからタカの部屋なのよ?
「ほんの少し時間をもらえれば、済むことだと思うの。硫黄島のことを、どんな所だったかだけでも実際に行ってきた彼に直接聞いてみたいだけなの。」
「もしかして先生の容態、そんなに悪いの?」
「ええ、少しでも早いほうがいいように思う。」
「あれからもお見舞いには行っているの?」
「2回行ったわ。2回とも先生は眠っていらしたけど。」
ああ、もうこれは西品川に行くしかなさそうだった。
「わかった。部屋の近くまで案内するから、あとはひとりで行ってくれる?」
「それで十分、感謝する。」
私たちはベンチから立ち上がると、広尾駅に向かって坂を下りていった。そしてタクシーを拾った。今回もタクシーは歩行者天国のために、戸越銀座通りには入れなかった。私たちは、第二京浜国道で車を降り、歩行者天国の人込みの中を歩き始めた。
途中の花屋でローズが立ち止まった。そして桔梗を買った。どうして、よりによって桔梗を選んでしまうの?私はあの日、タカとふたりで眺めた隣の家の桔梗の鉢植えを思い出していた。ローズの抱える桔梗の青がなぜが今日はお葬式を連想させる。静かな部屋で感じたタカの鼓動と肌のにおい。右に曲がって坂道を登り始める。公衆電話が見えてくる。
私にはここまでがもう本当に限界だった。
「Are you Ok?」
気がつくと、私の様子にローズが心配そうな眼差しを向けている。彼女は何も知らないんだわ。私がマリオの部屋で結城に暴力を振るわれたことを思い出してしまったと考えているんだろうな、そのトラウマでもう一度傷ついてしまったと考えているんだろうな。私の知っているローズマリーとはそういうやさしい人だった。
ローズの方が私の100倍くらいひどい目にあってしまったのに、彼女からのやさしさが今は我慢できないくらいに辛かった。
私は公衆電話の横で立ち止まった。もう足が前に進まなかったのだ。振り返るローズに、坂をこのまま登って最初の十字路を左に曲がり、少し行った左側の白い建物がそれだと伝えた。
「外階段があるからすぐに分かる。階段を上がった二階の左はじの部屋。」
ふとローズの抱える桔梗の花にまた見られている気がした。私がタカとの間で一線を越えてしまった原因を、桔梗が静かに語っている。今、目の前にいる女性に対するJealous、嫉妬だったのでしょう?桔梗は確かにそう語っている気がした。私は息を飲んで桔梗の花を見つめ返す。
Fateの日、長者丸で見かけたタカはまるで恋人を求めるような一途さで、彼女のアパートメントを探していたと見えないこともなかった。もしかして私はそれに深くJealousを感じてしまったの?それで、嫉妬のエネルギーに流されて、後先考えずに彼の胸の中に飛び込んで行ってしまった、とでも言うの?そんなの、絶対説明になっていない。
それでは、この息苦しさは一体何?どうしてタカと一線を越えたことをローズには話せないの?ローズには口がすっぱくなるくらい、気をつけろ、表に出るなと言い続けているくせに。そして、その後ろめたさも手伝って、あの夜、夢中で抱き合ってしまえば、もう何も残らないとでも考えてしまったの?ああ、もうほんとうに自分が信じられなかった。そうだとしたら、救いようのない話だった。
「Sharon, What’s the matter? You look different.」
ローズの声が私を現実に引き戻す。私は混乱した。今はあいつを好きなのかどうかも、もう分からなかった。
「I’m going.」
私は彼女にそう告げるのが精一杯だった。そして、背中で聞こえ始めたローズの声を振り切るように、ひとり坂道をかけ下りていった。
| 三辻 孝明(みつじたかあき) 「CUBE IT AUSTRALIA」のCEO(最高経営責任者)。早稲田大学人間科学部環境科学科卒業。1989年より豪州在住。2020年8月10日永眠。 |
【関連記事】
関連記事:【新型コロナウイルス関連】日豪物流業界のパイオニア。死と向き合い、激動のパンデミックの中を生きる。
関連記事:ドロップアウトの達人
関連記事:Madison






