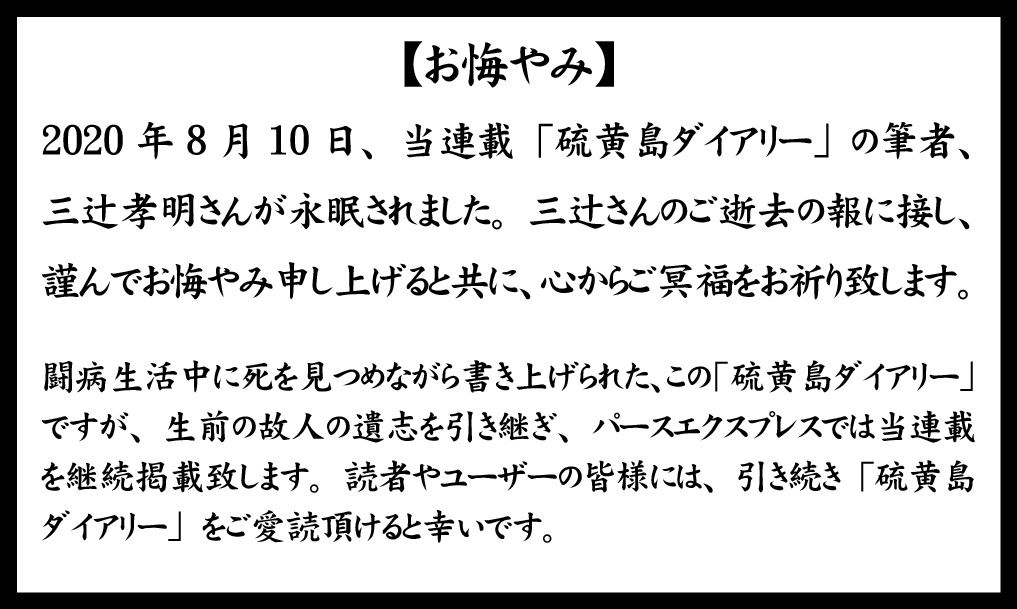
筆者三辻孝明さんは、昨年の2019年8月に癌の告知を受けました。三辻さんは以後、自然療法や抗癌剤治療を経て、癌の摘出手術を受けた10ヶ月間、「静かに死を見つめながら、久しぶりに文章を残すことができました」と話しています。そして「レポートに毛の生えたようなものですが、過去の自分自身の経験を形にできたことは少し肩の荷が降りたような気持ちです。よろしければ、ご一読ください」と生前に語っていました。
<第二章『ROSEMARY & SHARON』5話はこちらから>

【連載小説】
硫黄島ダイアリー
三辻孝明
第二章『ROSEMARY & SHARON』6話
その男を私は知っていた。ママさんのパトロンで、クラブのオーナーの結城という男だった。結城は店では目立たない印象だった。でも、あの晩マリオの部屋に後から入ってきた結城からは、むき出しの暴力の匂いがした。
「なんだ。お前か。」
部屋にいる私を最初に見た時の結城の反応だった。マリオが、すいませんと謝る声が聞こえた。
「このやろう、人をまくような運転しやがって。」
「結城さんだったんっすか。最近、変な奴につけられてるんで、俺、後ろばっかいつも気にしてるんっすよ。」
「そうか、そういうことか。で、見つかったのか?」
「いえ、まだっす。」
話の途中に結城は寝室からパイプを持ってくると、ポケットから出した粉を細かく砕いてからあぶり始めた。私は2人が耐熱ガラスのパイプから煙を吸うところを黙ってみていた。しばらくして結城が顔を上げた。結城は、それまでにもまして遠慮の無い目で私を見ている。
「隠してるんじゃないだろうな?」
その質問は私に向けられたものか、マリオに向けられたものかはっきり分からないものだった。
「結城さん、信じてくださいよ。見つけたらすぐ連絡入れてますよ。」
最初に答えたのはマリオの方だった。
「バカやろう、お前には聞いていない。」
結城の目は血走っていた。私は答えなかった。怒りが胃の辺りから込み上げてきて、それを押さえるのに必死だったのだ。なぜなら結城の手の甲にはかさぶたが取れた後に残るピンク色の傷跡がはっきりと残っていたからだ。それは人を殴ったあとに必ずできる傷跡だった。
「シャロン、答えるんだ。答えればすぐに帰してやる。」
「結城さん、質問の意味が分かりません。」
私には考える時間が必要だった。
「ローズマリーだ。あの女は店の金を持ち出して行方がわからなくなっている。お前と一緒に暮らしていた女なんだから、連絡ぐらい入れてくるはずだろう?」
「ローズがお店の金を持ち出したのですか?」
「ああ、それで3週間前にホテルにあいつを呼び出して問い詰めた。ちょっとやりすぎたが、最後まで吐かなかったよ。頑固な女だった。だが、こっちにも証拠がある。」
そう話しながら結城はマリオを見た。マリオは目を反らしながら力なくうなずいている。
「証拠って?」
「お前の相棒が売り上げをくすねるのを見た奴がここにいる。」
「ローズが売り上げをくすねるのを、あなたが見たというのですか?」
私はマリオを見た。彼は貝のように閉じたまま顔を上げなかった。
「ああ、それも1回や2回じゃない。あんな大人しい顔しやがって、すっかり騙されていたこっちの身にもなってみろ。」
「結城さん、そこまではっきりしているのなら、どうして警察に知らせないのです?どうして現金がなくなったことを隠そうとされるのです?」
「バカやろう、お前はそれでいいのか?ホステスの中にはビザの無い奴も混じっている。それに、お前らだってこいつから草やら粉やら面倒見てもらっているんだろうが。」
確かに観光ビザのまま働いているホステスの割合も少なくなかったし、彼女たちの何人かがそういうものを必要としているのも事実だった。
「私には必要ない話です。」
「誰もお前のことなんか聞いていない。いいか、お前の連れはな、こいつの商売道具までくすねたんだぞ。言ってることがわかるか?」
「商売道具?」
「この粉だよ、それもなくなっている。売り上げの被害はせいぜい数十万ってとこだが、シャブは100万や200万じゃきかねえんだぞ。」
「ちょっと待ってください、どうしてそれがローズの仕業だと分かるのですか?」
「この2ヶ月なんだよ。そういうことが起こり始めたのは。お前があの女を店に連れてきてからなんだよ。」
もしも結城の話が本当なら、3週間前に私たちの三田のアパートメントなんてとっくにやくざの黒塗りベンツで囲まれている。でも、そんなことは起こらなかった。結城が作り話をしていることは明白だった。マリオがどうして結城に加担しているのかはわからなかったが、私はひるまなかった。ひるむ理由などあるわけがなかった。
「結城さん、もう作り話はよしましょう。それよりも今晩、私をつけていた理由を聞かせてください。」
「作り話なんかしていない。これは調べ上げた事実だ。」
「わかりました。じゃあ、そういうことにしておきます。それで私をつけていた理由は?」
「条件はあの女の居所だ。それと交換に金も、なくなった粉のことも忘れてやる。」
「ローズが体で返すってことですね?それでもしも、あなたの提案を聞かなかったら?」
「あの女は断れないだろう。散々迷惑をかけたんだ。夜のお勤めなんて楽なもんだろう、それにあいつは好きもんだ。粉もあるし病みつきになるだろうな。」
「そうではなくて、ローズに伝えてくれというあなたの提案を私がここで断った場合は、どうされますか?」
結城は笑い出した。
「こいつはこの3週間、仕事以外の時はずっとお前のアパートを張っている。いずれあの女は見つかる。そうなってからだとただじゃすまなくなる。今なら、お前の方にとっても悪くない取引のはずだ、突っ張ってないでその辺をよーく考えるんだな。」
私はマリオを見た。マリオと目が合ったが彼が何を言いたいのか、読み取ることはできなかった。とりあえずローズの引越しを夜に、マリオが働いている時間にしておいたことだけは正しかったようだ。私は深呼吸をすると、息を整えてから言った。
「あなたのようなレイプをするような人に友達を引き渡すとでも思っているのですか?」
「レイプ?」
結城が口笛を吹いた。
「レイプされたのは俺の方かもしれないよ、ベイビー。」
こみ上げてくる怒りに、私はもう限界だった。
「結城さん、よく聞いてください。逆に私から条件を出しましょう。ローズをこれ以上追いかけないのなら、私は今うかがったことを他言しません。あなたたちのことも不問に付します。ただし、今後ローズの周りをうろつかないことが絶対条件です。それが約束できないのなら、私はこの足で今から警察に行きます。」
結城がまた声を上げて笑い出した。隣のマリオが腰を上げた。どうするのだろうと思っていると、私と結城の間に入って座りなおした。
「結城さん、落ち着いてください。この子はまだ何も知らないっすよ。」
「マリオ、お前、何でこのアマをかばう?お前ら、もしかしてできてるのか?」
「い、いや、そんなんじゃないっすよ。ただ、もうこれ以上この子に話さない方がいいような気がして。」
「いいような気がしてだと?お前、いつからこの俺に意見できるようになったんだ?」
結城とマリオが立ち上がるのは同時だった。マリオは私をかばおうとして体を張ったようにも見えたが、次の瞬間、結城に下半身を蹴り上げられ後ずさりしながら後ろの壁に激しくぶつかった。そして、すいませんとうめいたまま壁の前でうずくまってしまった。
「いいか、俺に二度と意見するんじゃねえ。」
私は今までに経験したことのない危険を目の前の結城から感じた。結城も同じことを考えていたらしく、“あんた、逃げもしないでいい根性だねえ。男なら立派な構成員だよ”と言った。
「構成員?」
結城は答える代わりにまた粉をあぶり始めた。結城は冷たい目で私を見ていた。殺されるかもしれない、そう思った時、ついに蛇のような手が伸びてきた。私はもとよりこの男の自由になるつもりはなかった。だから大きい声を出して結城を威嚇した。
「今3時10分です。3時までに私が帰らなかったら、警察に連絡することになっています。だから、もうすぐ警察がここにやってきます。」
「連絡することになっているって誰が?」
「誰だっていいじゃありませんか?」
「警察に連絡を入れるのはローズマリーなんだな?墓穴を掘るっていうのはお前みたいな“こ賢い女”をいうんだ。これでわかった。ローズマリーは三田のアパートに隠れている。」
結城が勢いよく立ち上がった。私が内心ホッとしたのもつかの間、突然、振り向きざまに結城は襲い掛かってきた。あごの辺りを殴られ、床に押し倒され、シルクのブラウスを引きちぎられて、体を乱暴にまさぐられた。そして結城は私を押さえつけながら言った。
「ふん、時間があれば可愛がってやるんだがな。」
あごにもらったパンチが効いて、私はもう動けなかった。結城が玄関に向かうのが見えた。結城は電話線を引きちぎり、玄関のたたきで立ったまま靴を履いた。それから部屋の中を振り返ると勝ち誇ったように笑顔を浮かべた。
「マリオ、その女にもう用はない。縛り上げたら押入れにでも放り込んでおけ。おれは下の車で待っている。」
その時だった。誰かが外でドアを叩き始めた。その音に玄関を出ようとしていた結城は凍りついた。誰かがすごい力でドアを叩いている。ロープを持ったマリオの顔も驚きで引きつっている。けれども結城の方はすぐに落ち着きを取り戻したようだった。
「夜中に何してるんだ、この野郎!」
野太い声でドアに向かって怒鳴り返した。すると直ぐドアの向こうから声が返ってきた。
「警察だ、開けろ。」
結城は素早く私の顔を見た。
「くそ、本当だったのか!」
結城はうめくようにそう言うと、奥の部屋に取って返した。マリオがおろおろしているのが目に入った。結城は窓を開けて退路を確かめていたようだが、飛び降りるのが難しいことが分かると次の瞬間、すごい勢いで玄関の方に戻ってきた。そして、ドアを突き破るように飛び出していった。それから少しして背の高い若い刑事が部屋に入ってきた。
英語が苦手なのか“POLICE?それともHOSPITAL?”と聞いてきた。POLICE?ってあなたのことでしょう?私は思わず笑いそうになる気持ちを抑えて、私は大丈夫ですと答えた。その若い刑事が奥の寝室に入っていくのを見届けてから、私は音を立てないようにアパートを後にした。そして1ブロック先の商店街にある公衆電話からローズに電話を入れた。始めに3回鳴らしてから一度切る、そして直ぐにかけ直すという約束を守って電話した。
「HELLO」
聞きなれたローズの声が返ってきた時のことをどう表現したらいいのだろう。私は、これで全てが大丈夫だと確信した。ローズは約束どおり長者丸のアパートメントにいてくれた。当分、三田の部屋には近づかないよう繰り返し注意してから私は電話を切った。
時計を見ると、午前3時半をまわったところだった。私は思い切り叫びたい気持ちだった。最高のタイミングで登場してくれた日本の警察に。勇敢にも独りで飛び込んでくれたあの若い刑事に。それよりも何よりも私の放った苦し紛れの嘘を現実にしてくれた神様に。神様は私たちのそばにいた。奇跡を目撃した今なら100%それを信じることができる。私は第二京浜国道まで歩いてからタクシーを拾った。そして、運転手に告げた。
「三田にお願いします。たぶん、つけられていると思いますが気にしないで。」
私は、そこまでバカではないつもりだ。結城の仕掛けたトリックくらい簡単に察しがついた。結城は必ず私をつけている。今夜、私にさんざん怖い思いをさせて開放した後にローズの隠れている部屋に私を向かわせるためのトリック。マリオは始めから私を縛るつもりはない。そんなことをしたら警察沙汰になってしまう。それよりも彼は私をなだめ、そして部屋から結城に見つからないように私を逃がす。たぶん、そんなシナリオだったはずだ。たまたま警察に邪魔はされたけれども、私をつけていることにかわりはない。
私は三田のアパートメントの前で車を降りた。降りがけに運転手が言った。
「お客さん、確かにつけられてますよ。ここで降りて大丈夫なんですか?」
私は、大丈夫ですと答えてから車を降りた。
翌日、私は六本木交差点近くにある麻布署に出向き、大使館への守秘義務を条件に昨日起きたことと結城から聞いた話を警察に伝えた。その日の夕方、クラブに顔を出したマリオは身柄を拘束され、店の金を数回にわたって横領したことと、結城にたのまれて覚醒剤を売りさばいていた事実を数日のうちに全て認めた。マリオの部屋に隠してあった覚醒剤も押収された。
ただ、結城の行方が分からないことが気がかりだった。結城はマリオをおとりに使い、私が本気で戦う気があるのかどうかを確かめたに違いなかった。そうでなければ、あんなことがあってすぐにマリオがクラブに顔を出すはずがなかったから。その後の数日、私は何回か麻布署に足を運び、警察の捜査に協力した。あの晩、飛び込んできてくれた刑事のことは最後までわからなかった。調書を作成していた刑事も不思議な話だとは言っていたが、他所の縄張りの刑事がたまたま居合わせて現場に飛び込んだのではないかということで落ち着いたようだった。あるいは本庁のマル秘捜査と関係していたために、名乗り出ることができなかったとか、そんなことのようだった。
ローズはその年の終わりに、国際学級の教員の仕事を見つけた。11月に入って秋が深まり出した頃、マリオが小菅から長野刑務所に移されたことを知った。初めてではないので、服役は4年近くかかるらしかった。マリオは結城がローズマリーにしたことを警察には話してはいないようだった。余罪の多い結城は現在、警察が追いかけている。
1990年が終わろうとしている。年の瀬が好きだと感じたことは、これまでに一度もなかった。何かが終わることをお祝いしたいと願う気持ちを私は、多分持ち合わせてはいない。
| 三辻 孝明(みつじたかあき) 「CUBE IT AUSTRALIA」のCEO(最高経営責任者)。早稲田大学人間科学部環境科学科卒業。1989年より豪州在住。2020年8月10日永眠。 |
【関連記事】
関連記事:【新型コロナウイルス関連】日豪物流業界のパイオニア。死と向き合い、激動のパンデミックの中を生きる。
関連記事:ドロップアウトの達人
関連記事:Madison






