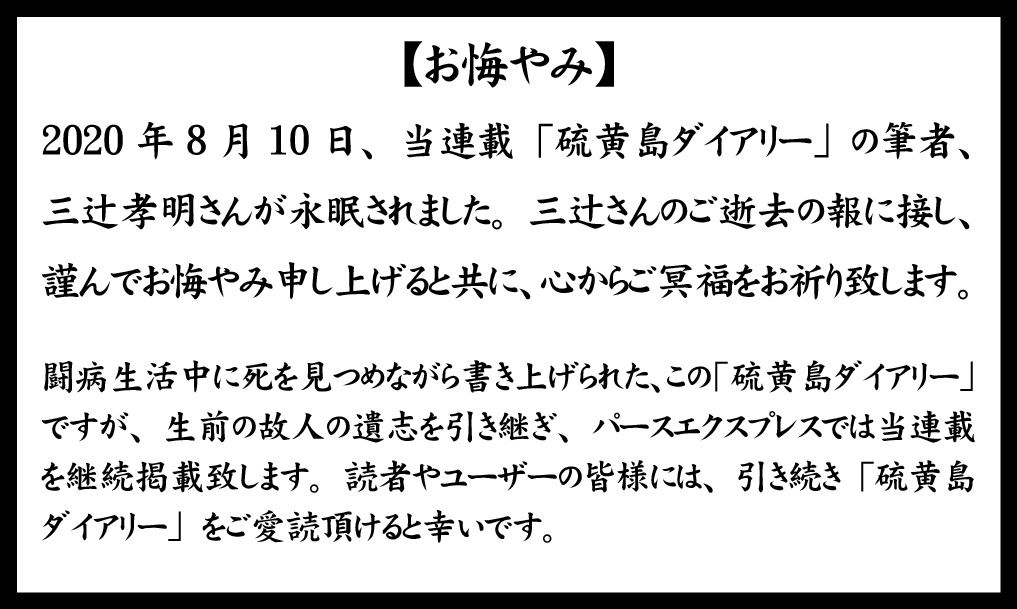
筆者三辻孝明さんは、昨年の2019年8月に癌の告知を受けました。三辻さんは以後、自然療法や抗癌剤治療を経て、癌の摘出手術を受けた10ヶ月間、「静かに死を見つめながら、久しぶりに文章を残すことができました」と話しています。そして「レポートに毛の生えたようなものですが、過去の自分自身の経験を形にできたことは少し肩の荷が降りたような気持ちです。よろしければ、ご一読ください」と生前に語っていました。
<第二章『ROSEMARY & SHARON』2話はこちらから>

【連載小説】
硫黄島ダイアリー
三辻孝明
第二章『ROSEMARY & SHARON』3話
彼女は自転車のペダルを踏みながら考える。わずか15分足らずのこの朝の時間が気に入っている。冷たい風が頬を打ち、ハンドルを握る指先がかじかんでいる。あの日、成田空港に降りてからもう直ぐ2年が過ぎようとしている。もしも、あのままムンバイに行っていたら、今頃は大学でまだ机に向かっていたはずだ。でも、後悔はしていない。
今は国際学級で美術の教師をして働いているけれども、あの日からこの街で暮らすためにいろいろな仕事にトライをした。英語の家庭教師や下着のモデル、それにクラブのホステスも。ちらしの下着のモデルは3ヶ月。1年続けた英語の家庭教師の、最初の生徒は長身の政治家だった。元阪神のピッチャーでまじめな人だったけれども、半年たってもまるっきり英語を話せないのには困り果ててしまった。もうひとりは芸術家だった。11PMという深夜のテレビでイラストを描いていたおじいさん。教えている最中、彼はいつもズボンを脱いでしまう。彼が言うには、ペニスをいじっていると集中力が沸いてくるのだそうだ。それが彼の力を引き出すやり方なのだと言っていた。
オーストラリアに戻っていたら決してできなかった不思議な体験の数々。誰も彼女のことを知らないという自由と開放感の中で、彼女はこの街に恋をしていった。だから、ここで暮らせるのならどんな体験でも受け入れられると、知らないうちに自分を過信してしまっていたのかもしれない。そしてその過信が頂点に達したとき、ローズマリーはホテルの一室に監禁され、暴力を振るわれ、男にレイプされたのだった。
その頃、彼女は霞町のクラブで週に2日、シャロンに誘われてホステスのアルバイトを始めていた。その日は、いつも一緒だったシャロンが大使館の仕事で神戸に出張していて、ローズマリーひとりで男と食事をすることになっていた。場所は、紀尾井町にあるホテルのレストランだった。食事が進み1時間ほどした頃だったように思う。突然、男が体の異変を訴えはじめた。
「キドニーストーン、腎臓の石が動いた。」
後から思い出しても、とても何かを企んで演技をしているようには見えなかった。
「少し横になっていれば治ると思う。すまないが部屋まで連れて行ってくれないか。」
彼女は彼の腕を支えながらレストランを出て、ロビーの人ごみを通りエレベーターで上の階に向かった。7階でエレベーターを降り、厚い絨毯の廊下で足を止め、鍵を探す彼を支えていた時、ホテルの制服を着たスタッフとすれ違った。そして部屋に入った。その途端、その人は男に、獣に豹変した。その人はドアの前に立って、ローズマリーの退路を素早く遮断した。まるでジキルとハイドだった。彼女は言葉を失った。今起きていることが信じられなかった。恐怖はひざの力を奪い、その震えに立っているのさえ難しいほどだった。今叫んだら先ほどすれ違ったホテルのスタッフが戻ってきてくれるかもしれない。でも、そう思うだけで息が上がり声が出せなかった。男はゆっくりと彼女に近づいてくる。そして乱暴に髪をつかむと、勝ち誇ったように唇を奪った。
「気持ちよくしてやるから。」
タバコとウイスキーの混じった口臭を感じた。そして抗うローズマリーに男は本気で手を上げはじめた。何回も顔を殴られた。口が切れ出血し、激しい痛みの中でこのままでは殺されると思った。その時の彼女には、もう男の思いを遂げさせて一刻も早くこの部屋から逃げ出すことのほか何も残されてはいなかった。数時間後に解放された時、唇の出血は止まっていたけれども、右側の目の周りと左のあごの下にひどいあざが浮き出ていて、人目につく場所を歩ける状態ではなかった。彼女はホテルから出るまでの短い間に、周りから受けた視線でそのことを理解した。そして、だいじょうぶですか?と誰からも声をかけられなかったことが、彼女には本当に堪えた。あなたなんか始めからこの国には要らなかったのよと言われているようだった。
外は土砂降りだった。バスや電車を乗り継ぐ気力などあろうはずもなく、ローズマリーはタクシーでアパートメントへ戻った。そして、傘もささずに銭湯まで走った。一刻も早く汚れた体を洗い流したかった。あの熱いお湯に浸かりたい一心だった。けれども銭湯は休みだった。崩れそうになる自分を励ましながら金物屋に向かい、一番大きいたらいを買った。部屋に戻るとお湯を沸かした。そしてそこまでが、限界だった。彼女は堰を切ったように声を上げて泣いた。獣の咆哮のように泣いた。内臓を吐き出すほどに泣いた。泣きながら服を脱いだ。たらいに入り、うずくまるようにして体を洗った。お湯を沸かしては一晩中たらいの中で体を洗い続けた。
ローズマリーは警察に届けることや、ママさんに報告することは全く考えなかった。彼女の本能で、彼らが話を信じて彼女を守ってくれるとは決して思えなかったからだ。彼女は男と一緒に食事をし、腕を取ってロビーを通り、混んだエレベーターに乗って部屋まで歩いていった女だった。たくさんの人やホテルのスタッフがそれを見ていた。日本人の男と彼女のような長身の外国人が一緒に歩いていれば、たとえ高級ホテルでも周りの目に止まらないわけがない。彼の暴力を訴えたとしても、一体あそこに居合わせた何人が彼女の言うことを信じてくれただろう。
翌日ひとりで病院に行った。検査の結果は数日で分かるということだった。翌週、シャロンにたのんで病院に電話を入れてもらった。結果は白だった。病気や妊娠の心配はないと言われたが、それを聞いたからといって傷ついた心が元に戻るわけではなかった。クラブの仕事はそのまま辞めた。その月の終わりに、長者丸のアパートメントに越した。シャロンの提案で、用心して目立たないよう暗くなってからの引越しもした。越した部屋には大きいバスタブがあった。そのことだけが少し嬉しかった。
部屋の窓からは、自然教育園の森が見える。昼間、ひと気のない森を歩く。東京には珍しく、たくさんの野鳥や昆虫がいる。ベンチに座って目の前の毛虫をずっと見つめていた。そんな時、怖いのは人間だなと思った。人間くらい予測のできない生き物はいないと思った。私が一体何をしたというのだろう。私はあの日、偽善やポーズであの男を部屋まで連れて行ったわけでは決してない。男が食事の途中で気分が悪いと言い出した時、確かに玉の汗をかき、自分の腕の辺りをつかみながら、苦しそうにしていたのだ。彼女はそこで、また息をつめて地面を見つめた。何よりも辛かったのは、自分の体が反応してしまったことだった。男は勝ち誇ったように思った通りだと言った。お前はこれが好きで好きでたまらない女なんだと言った。彼女を押さえつける男の顔が、水泳部のキャプテンの顔に、愛していると言いながら繰り返し体ばかり求めてきた初恋の男の顔に重なっていく。もう何も信じたくはなかった。
自分はたぶん、海岸に打ち上げられたガラスのビンのようなものなのだと思う。一大冒険のつもりで海を渡り異国に流れ着いたそのビンは、浜辺を歩いていた見知らぬ男に拾われて、粉々に打ち砕かれてしまった。そのガラスの破片が、砂の上に無残に散らばって見えている。
レンガの建物が近づいてくる。門を入り、いつもの場所に自転車を止め、キンダガーデンと書かれたドアから建物の中に入る。壁の時計は8時50分を指している。風邪を引いている子どもが多いのか、今日も生徒は6人だけのようだった。天気予報では今日は気温が上がって晴れると言っている。雨でなくてよかったと思う。ふと、あの土砂降りの雨の日のにおいを思い出す。誰かに話してみろ、その時はお前にではなくシャロンを必ず同じ目にあわせてやる、そう脅されてホテルを出たあの日。ローズマリーは、また度の強いメガネをかけて髪を束ねる。そして、何も見せないだぶだぶの服の中の自分に戻っていく。
| 三辻 孝明(みつじたかあき) 「CUBE IT AUSTRALIA」のCEO(最高経営責任者)。早稲田大学人間科学部環境科学科卒業。1989年より豪州在住。2020年8月10日永眠。 |
【関連記事】
関連記事:【新型コロナウイルス関連】日豪物流業界のパイオニア。死と向き合い、激動のパンデミックの中を生きる。
関連記事:ドロップアウトの達人
関連記事:Madison






