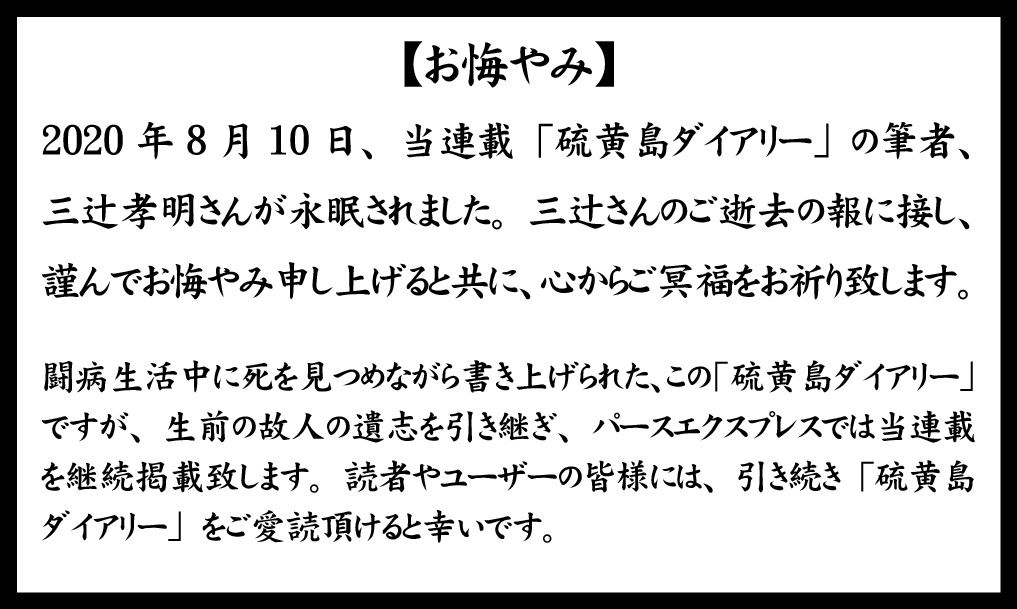
筆者三辻孝明さんは、昨年の2019年8月に癌の告知を受けました。三辻さんは以後、自然療法や抗癌剤治療を経て、癌の摘出手術を受けた10ヶ月間、「静かに死を見つめながら、久しぶりに文章を残すことができました」と話しています。そして「レポートに毛の生えたようなものですが、過去の自分自身の経験を形にできたことは少し肩の荷が降りたような気持ちです。よろしければ、ご一読ください」と生前に語っていました。
<第二章『ROSEMARY & SHARON』1話はこちらから>

【連載小説】
硫黄島ダイアリー
三辻孝明
第二章『ROSEMARY & SHARON』2話
「私たち、きっといいコンビになれるわよ。」
初めて会った日に、寮の部屋でシャロンから言われた言葉である。彼女の夢は外交官になって東京で暮らすことだった。
「どうして東京なの?」
そう聞き返すローズマリーにシャロンはこう答えた。
「私、白人の男にそんなに魅力を感じないの。ほら白いって言っても、東洋人と違ってこっちの人の肌って、なんかピンクでガサガサしてる感じでしょう?それに、あの汗の匂いも苦手だし。」
「じゃあ、あなたはどんな肌ならいいの?」
「理想は忍者ね。」
「忍者?」
「あなた、小さいとき忍者のテレビ番組見なかったの?」
「見た見た。かっこよかった。」
「でしょう!私の中ではあれ以来、忍者が理想になったわ。いつか忍者の彼氏をつくりたいって本気で思ってる。」
シャロンにそう言われてみると、ローズマリーもかなりあの番組には憧れていたことを思い出した。口には出さなかったけれども忍者になりたいと思ったことが確かにあったし、付き合うなら自由で何でもできてしまう忍者みたいな人がいいと同じようなことを考えていた。
「ほら、だから日本なの。東京に行って現代の忍者を探すのよ。スベスベした肌の。ねっ、いいでしょう、この考え。」
ローズマリーは思わず吹き出してしまった。この人となら、きっとうまくやっていける、そのことが何よりも嬉しかった。シャロンには自由な空気があった。教会の施設ではしてはいけない、守らなければいけないことばかりだったから。
「ルールは自分で作ればいいと思う。だってあなたの人生でしょう?自分を信じていれば、怖いものなんて何もないわ。」
「で、あなたの夢は?」
彼女にそう聞かれて、結局ローズマリーは何も答えられなかった。
「ローズ!」
そう、シャロンはローズマリーのことを親しみを込めていつもそう呼んでくれた。
「ローズ、怖がっちゃダメよ。もう、水泳部のキャプテンのことなんて忘れなさいよ。」
それが寮の部屋での、彼女の口癖だった。なんとなく悪い予感はしていたけれど、同じ大学に進んでみると水泳部のキャプテンにはすでにガールフレンドができていた。まだ大学に入学して間もない新入生歓迎パーティーで、彼らを見ることになってしまったのだ。それでもまだ未練があったローズマリーは、それからしばらくしてキャプテンからの誘いに応じてしまった。キャンプに行こうと誘われたのだ。その話をするとシャロンは、初めから反対した。
「どうせ浮気の相手をするんなら、もっとましな奴としなさいよ。」
「そうじゃないの。彼、けがをして今泳ぐことができないの。だから、わたし、少しでも力になってあげたいの。」
「あなたがあのビスケットの力になるのは自由だけど、言っとくけど、あいつ絶対オリンピックになんか出れないわよ。」
「どうしてそんなことがわかるの?」
「人はね、うまくいってる時には、みんな素敵に見えるものなの。でもね、何かの壁にぶつかって、挫折を味わって初めて、本当にその人間の価値が分かるものなの。あのビスケットは今、挫折を経験している。でも、女は必要なんでしょう?ローズ、壁を乗り越えられるかどうかはビスケット自身の問題なのよ。あなたがいくら尽くしても、あいつのトイレになるだけだってこと、どうしてわからないの?」
「トイレ?あなたに私たちのことがどこまで分かると言うの?彼は少なくともわたしと出会うまでは、普通の記録しか残せない選手だった。でも、私たちが親しくなればなるほど、愛し合えば愛し合うほど、記録も飛躍的に伸びていったし、州を代表する水泳選手としての自信も体中にみなぎっていった。私は彼がそうやって人とは違う才能を発揮していくプロセスをずっと近くで、ずっと寄り添って、ずっと一緒に見てきたの。それをトイレだなんて。」
「ローズ、お願いだから少し頭を冷やして考えてみて。確かにあなたがひとりの男の子の成長していく軌跡に立ち会ったのは事実かもしれない。でも、彼はあなたの持ち物じゃないし、あなたの夢を代理に叶えるための人でもない。彼は彼の幸せのために生きているのよ。だから、あなたがそうやってずっと思い出に縛られながら、知らないうちに自分を犠牲にしていくやり方を続けていたら、間違いなくあなたたち、ふたりともダメになってしまうのよ。」
でもローズマリーは焚き火を囲みながら、彼との時間を共にできる喜びで、シャロンの忠告には聞く耳をもてなかった。傷ついた彼は今、私を必要としている。また、昔のように時間をかけてふたりで過ごせば、分かり合えると信じていたのだ。でもキャンプは楽しい思い出にはならなかった。グループで行ったといってもシャロンの言うとおり、彼の目的ははじめから彼女のそれとは違っていた。けがをしたことで彼の中にあった揺るぎないはずの自信がすっかり失われてしまっていた。水泳王国オーストラリアのユース代表として日の当たる場所を歩いてきた彼にとって、初めて経験する挫折だったに違いない。わずか一年会わない間に彼の瞳の中にあった澄んだ輝きが影を潜めていた。代わりに彼はキャンプの間中、輝きを失った目で彼女を求め続けた。
「ローズ、便利な女はもう終わりにしましょう。」
シャロンの忠告に従って彼との関係を清算したのは、一緒にキャンプに出かけてから、3ヶ月経った頃のことだった。自分がすでに十分女であることはわかっていたけれども、ただ目的を失い寂しいというだけで求められる関係に応えることは、もう続けたくはなかった。そのことがわかるのに費やしたのが3ヶ月だったと思いたい。閉じ込められ、快楽を塗りこめられていくような関係にではなく、シャロンの周りにある自由で解放された、深呼吸のできる、心の底から笑い合える、そんな関係を彼との間にも作りたかった。ローズマリーにはもっと優しい気持ちが必要だったのだ。それが19歳の彼女自身が見つけた真実だった。そして、その気持ちや価値観は今でも変わってはいない。
彼と別れて以来、それからの3年間、寮の部屋にこもって机に向かっていたローズマリーは、次第に周りから忘れられる存在になっていった。だからもしもあの日、シャロンが成田空港に迎えに来てくれなくてもローズマリーは驚かなかったと思う。忘れられることには慣れていたし、予定通り2日間東京で過ごしてから、ムンバイに向かっていただけなのだ。そしてアジアの旅を終えたら、またあのインクと紙とカビのにおいのする世界に帰っていくだけなのだ。けれども日本に着いた日、シャロンは待っていた。成田空港の到着ゲート。2月の寒い午後だった。雪がちらついていた。ゲートの人ごみの中で、ふたりは何度も互いの名を呼び合い、抱擁を繰返した。
「ねえ、銭湯に行かない?」
「SENTOU?」
「そう、おふろ屋さん。」
東京の街までは、道が混んでいて3時間はかかったように思う。着いた部屋の寒さはシドニーでは体験のできない種類のものだった。お風呂もないらしかった。その代わりに家賃が安いことと、大使館に歩いて通えるとシャロンは話していた。時間が早かったせいかふたりで出かけた銭湯は空いていた。ローズマリーはそこで初めて、ボーイフレンド以外の男性の前で裸になる体験をした。番台に初老の男が新聞を読みながら座っていたのだ。浴室ではお年寄りから声をかけられた。声をかけられたといっても言葉が通じるわけではなかったから、身振り手振りでの会話しかできなかったのだけれども。バスタブのお湯は入るには少し熱すぎる気がした。でもお年寄りたちは長い時間をかけて肩までつかっていたから、彼女も少し我慢をしてそれにならった。
「それでこれからどうするつもりなの?」
「明後日、ムンバイに行く。」
「そういうことではなくて、これからのあなたの人生について聞いているのだけれど。」
ローズマリーはインドの旅を終えたら、大学院に戻る予定だと話した。
「あなた、またあの刑務所に帰るつもりなの?」
シャロンは在学中から大学のことを刑務所と呼んでいた。
「ハイスクールが少年院で、大学は刑務所。あなた、そこから先はもう終身刑よ。」
「だって、そう言われても、私もう復学する書類にサインしてきてしまっているもの。それに奨学金のことではとてもお世話になっているのよ。」
「なに馬鹿なこと言ってるのよ、あなたはもう自由なのよ。立派な成績を収めて、もう十分あの大学に貢献してきたのよ。施設のシスターも、口うるさいオールドミスの寮長も、女狂いのビスケットも、ここにはもう誰もいないじゃない?」
シャロンは、ここは東京だと言った。
「今、シドニーは真夏だわ。ここは真冬なのよ。ねえ、ローズ、あなたこの4年間、一体何を勉強してきたというの?」
ローズマリーには彼女の言いたいことがわかっていた。せっかく旅に出たのだから先のことはいったん白紙に戻して、今いるところをもっと大切に考えなさいと言いたいに違いなかった。
「私はね、病気をしてから、もう誰にも、どんなことにも、遠慮をすることをしなくなってしまった。自分が興味のあること、わくわく感じられることに真っすぐに歩いていけるようになったの。どうしてそうなったと思う?」
シャロンは大学時代に腫瘍の摘出手術を受けていた。
「あなたにはあなたの砂時計があり、私には私の砂時計がある。砂の量は人それぞれで違うわ。もしかしたら私の砂は、普通の人よりも少ないかもしれない。でも誰でもみんな生まれた瞬間からその時計の砂が毎日毎日、確実に減り続けていくことを知っている。命という砂が全部下に落ちておしまいになるまでね。おしまいになるって死んじゃうってこと、この世からいなくなっちゃうってことなんだけど。だったら、どうして誰かに遠慮したり、気配りしたりして人生を決めていく必要がある?そんな暇があったら、真っすぐに好きなことを続けていきましょうよ。命の火が燃えている間は、砂時計の砂がまだ残っている間は、自分の気持ちに正直に、悔いの残らないように自分の一番歩きたい道を堂々と生きていきましょうよ。」
銭湯を出ると夕方だった。アパートに戻る途中にブランコのある小さな公園があり、その入り口の脇に屋台が出ていた。シャロンに続いて屋台の青いビニールシートに入り、ビール瓶用のプラスチックケースに2人並んで腰を下ろした。シャロンとローズマリー以外に、まだ客はいなかった。屋台の“シェフ”とシャロンはすでに顔見知りのようで、彼らはひとしきり他の客の噂話をしていた。そこでローズマリーは、生まれて初めておでんという食べ物に出会った。大根、昆布、ちくわ、それにごぼう巻きも悪くなかった。スープも美味しかったけれども、とても寒かったので勧められるままに日本酒を重ねた。
すっかり暗くなって2人とも酔いが回り、驚くほど安いお金を払ってビニールシートの表に出てみると、街全体に薄っすらと雪が積もり始めていた。どんなに寒くてもシドニーに雪が積もることはない。ローズマリーにとっては生まれて初めて見る本物の雪だった。灰色の細い路地から大通りに出るまでの間に、車は一台も通らなかった。モノクロームの雑然としたアジアの街並みに、静かに雪が舞い落ちている。灰色の街に薄暮の青が残る淡い光の中で、空から純白の花びらのような雪が後から後から無数に舞い落ちてくる。立ち止まりそのまま真上の空を仰いでいると、まるで自分の体が白い花びらをかき分けて空の彼方に上り詰めていくように錯覚してしまう。ローズマリーは息を呑んだまま、いつまでも彼女の顔に舞落ちてくる雪の一片ひとひらを眺めていた。
「ローズ、今、この瞬間、この場所から始まるのよきっと。あなたの砂時計の命をかけた本当の旅が。」
「雪って、なんて繊細で贅沢な贈り物なの」
ローズマリーの子どものような様子にシャロンは声を上げて笑いだした。
「この外人の酔っ払い!」
ローズマリーにならって雪の舞い落ちる空を見上げながら、シャロンがそう叫んだ。
「ガイジンノヨッパライ?」
「そう、ここではね、今夜の私たちみたいな幸せな奴らのことを、みんなそう呼ぶのよ。」
「ガイジンノヨッパライ、ガイジンノヨッパライ。」
ローズマリーは、今覚えたばかりのその言葉を繰り返しながら、度の強いメガネをはずし、束ねていた髪を解き、胸のふくらみをもう隠すことも忘れて生まれ変わったように大胆に歩き始めた。日本酒の酔いが身体中に回って、信じられないくらいいい気持ちだった。それは、彼女にとって生まれて初めて感じる、生きることに何の負い目も感じない、ほんものの自由への手応えだった。
| 三辻 孝明(みつじたかあき) 「CUBE IT AUSTRALIA」のCEO(最高経営責任者)。早稲田大学人間科学部環境科学科卒業。1989年より豪州在住。2020年8月10日永眠。 |
【関連記事】
関連記事:【新型コロナウイルス関連】日豪物流業界のパイオニア。死と向き合い、激動のパンデミックの中を生きる。
関連記事:ドロップアウトの達人
関連記事:Madison






