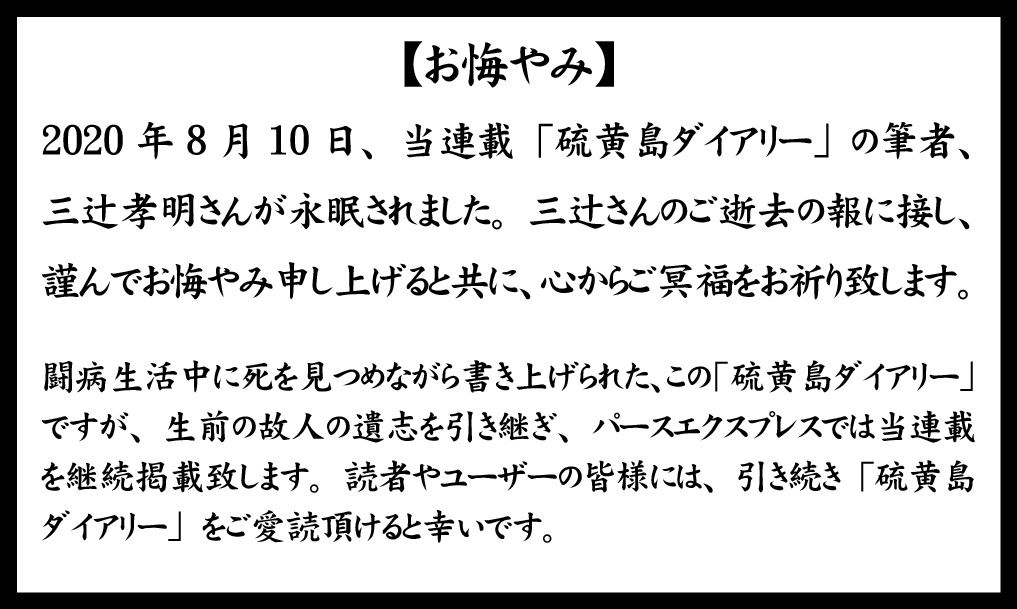
筆者三辻孝明さんは、昨年の2019年8月に癌の告知を受けました。三辻さんは以後、自然療法や抗癌剤治療を経て、癌の摘出手術を受けた10ヶ月間、「静かに死を見つめながら、久しぶりに文章を残すことができました」と話しています。そして「レポートに毛の生えたようなものですが、過去の自分自身の経験を形にできたことは少し肩の荷が降りたような気持ちです。よろしければ、ご一読ください」と生前に語っていました。
<第一章『硫黄島』4話はこちらから>

【連載小説】
硫黄島ダイアリー
三辻孝明
第一章『硫黄島』5話
その日、僕は4号室のひろしと洗濯物の当番をしていた。
支給される作業着には番号や名前が振ってあり、週に一度溜まった汚れ物をまとめて洗濯する。洗濯物はかなりな量だから朝から午前中いっぱい、2名がその日は作業現場には行かずに専任で洗い終わった洗濯物を干していく。まだ20代で長身のひろしは珍蔵と潜水士の仕事を一緒にしていたという。潜水士の仕事はスキューバダイビングのようなホビーの潜水とは違い、厳冬のダム工事現場の水中溶接であったり、深夜の港での一家心中の車の引き上げだったりする。ボンベを背負ってスキューバのように潜る方法とラインと呼ばれる空気の管で結ばれたヘルメットをかぶって潜る方法とがあるらしい。
「けっこうね、船の喫水線から下の汚れを取る作業が金になったですよね。」
ひろしはそう話しながら四つん這いになって、洗濯物で埋まった物干場の床を凝視している。
「ほら、雨が続いて物干し場の木の床に、こういっぱい水がしみ込むと、今朝みたいにお日様が差してきた時、もやが立つですよね、ティンカーベルの粉みたいなきれいなもやが。」
「なんの粉ですか?」
「ティンカーベルの粉っすよ」
確かに洗濯物のすき間から差す強い日の光にさらされて、物干し場の床がみるみる乾いて行く。乾きながら小さなきらきらした湯気をもやのように吐き出している。それをひろしはティンカーベルの粉と呼ぶ。ピーターパンに出てきた妖精のことらしい。
「ピーターパンが好きなんですか?」
「生きてた頃、田舎のばあちゃんが何回も読んでくれたんです、ピーターパンの話を。」
「ティンカーベルの粉か、詩ですね。」
「いやあ、そうでもないっすよ。」
僕は年下のひろしと話しているうちに、この島に来てたぶん初めて身構えないで人といることに気がついた。ひろしのオーラには人を傷つけるための尖ったものが、初めからなかった。いつも控えめで、食堂でたまに目があうような時も謝るような柔らかい、悲しそうな視線を向けてくる。はにかんでこちらに顔を向けるそのひろしに前歯はない。細面で日に焼けたひろしは、笑わないと精悍な顔立ちなのだけれど、前歯がないためにずいぶんと損をしている気がする。うまく言えないけれども彼の人生が大きく違ってしまったような気がする。
「俺の歯、やっぱ、気になります?」
てるおにやられたのだそうだ。同じ部屋で2年近くも一緒にいたからこうなってしまったのだという。
「でも、てるちゃん、歯折ってから手出さなくなったから、このままにしとこうと思って。」
ひろしがどうして新潟刑務所に送られたのかは、ここではみんなが知っている。本牧で珍蔵と組んで船の底に付いた貝殻を取る仕事をしていた時、そのクルーザーの持ち主にそそのかされて運び屋をしてしまったのが原因らしい。
「新潟刑務所は、ほんとこわい所だったすよ。」
刑務所の図書室からは雪に覆われた田舎の景色が見える。春になると野外作業で塀の中から外に出る機会も多かったようだ。けれども初めて受刑したひろしにとっては、はじめから大変厳しい場所だった。二度と思い出したくないとひろしは口にした。斉藤の話によると、ひろしはひとけのない雨の物干し場で、繰り返し陵辱されティンカーベルの粉のことを知ったのだそうだ。出所してこの島に来て以来、雨のあとの物干し場に行くとうつろな目をしたひろしが両膝をついたまま何かを探すように床を見つめている。もしかしたらひろしは戻りたいのかもしれない、雨の降る前の、犯される前の物干し場に。あるいは、陵辱の後で見つけたティンカーベルの粉のことを、忘れないようにしたいのかもしれない。ひろしにとってはティンカーベルの粉は、雨の物干し場の先に見えた生きる希望の光なのかもしれない。
その頃、島に駐屯するコーストガードの通訳が、体調不良で岩国の病院に帰還してしまうというアクシデントがあり、そのため誰か現場で英語のわかるものはいないかという話が持ち上がっていた。結局、該当者がいないまま山中さんと僕の“見た目”が、顔面に大きな傷もなく小指も前歯も揃っていることから、一番まともに見えるということで、その通訳の代役をすることになったのだが、山中さんの英語はフランス語訛りが酷く、また極めて学術的だったため、コーストガードたちからの評判も良くなかった。
そこで僕がその代役をすることになるのだが、これが僕の島での地位を飛躍的に引き上げることにつながった。理由は、自衛隊関係の滑走路拡張工事の現場の方は、かなり肉体的にきついものだったが、コーストガードのお世話をする方は、当時の思いやり予算のこともあり、待遇がとても良かったからだ。例を挙げると、彼らが使うかまぼこ型の建物の中には、冷蔵庫やエアコンがあり、バドワイザーやハーゲンダッツのアイスクリームは、飲んだり食べたりしていいことになっていた。しかも、オフィサーが頼んでくる仕事は、せいぜいが1、2時間で終わる程度の雨どいの清掃やシャワーの交換などで、あとはステーキやバーベキューをご馳走になり、ビールを飲んで、マスターベーションの個室も使うことが許され、ハードコアのビデオ(注:男女のもの、男性同士のもの、女性同士のもの多数)を何回鑑賞しても怒られなかったため、誰もがコーストガードの仕事に行きたがった。
コーストガードの仕事は、滑走路拡張工事の現場と違い、必ず3人一組で赴くことと決められていた。それには理由があり、2人だとカップルになる可能性があるからだった。実際、男しかいないこの島で、コーストガードは半分がゲイだと噂されていたし、鹿島建設下請けの宿舎の方も、ひろしだけではなくそういう噂はときどき耳にしていた。別にそういうことに強い拒否反応があったわけではないけれども、あの頃の自分には性別に関係なく、誰かと裸になるという気持ちが豊かでないとできないような行為とは縁がなかったから、そういう地味なところも通訳の代役として評価されたのかもしれなかった。
必然、コーストガードの仕事に同行する残りの2人は僕が指名することになり、お風呂は最後ではなく一番風呂に入れるように変わったし、指名して同行した作業員からの付け届けも3号室に届くようになり、僕の布団も風通しのいい窓側に、黙っていても斉藤が敷いてくれるようになったのである。なんだか斉藤の様子も随分違ってきて、食事や作業の時も、僕のそばを離れなくなっていた。何か用?と聞いてみると一緒にいるのが誇らしいと返事をする。それに部屋への付け届けも、普段口にできない虎屋の羊羹やバームクーヘン、博多明太子やスコッチウイスキーといった貴重品ばかりだったから、受け取る斉藤も目を丸くしていた。
「パイロットルートよ。」
珍蔵の話すパイロットルートとは、厚木や三沢から練習に来る戦闘機のパイロットに予め頼んでおくルートのことなのだそうだ。もちろんタダということはなく、彼らの喜びそうなものと交換しているということだった。
「どういうものと交換するとパイロットの人は喜ぶの?」
斉藤の質問に珍蔵が答える。
「そりゃ、ご法度ギリギリのものに決まっとるわい。」
「ご法度ギリギリのもの?」
「コーストガードのカマボコに行ってみい、内地にないものがぎょうさん出てくるわい。」
珍蔵の話では、日本では手に入らないドラッグ、特に短時間に集中力をマックスに持っていけるグリーンタブレットというのに人気が集中しているのだそうだ。
「それってシャブみたいなものなの?」
「グリーンは、今のところ内地では合法になっとる。戦闘機乗りは空自でもとびきりのエリートやから、チームの中での競争も凄まじい。それに奴らはシャブのような手が後ろに回るものには、絶対手を出さん。その辺が選挙のたんびにシャブなんか使っちょる日本の政治家なんかよりもはるかに上をいっちょるちゅうことよ。」
「でも、どうして英語もできない作業員が、コーストガードと交渉できるの?」
「なあ斉藤よ、おのれだって言葉が喋れなくともよ、ガキは作れるんゃないかい?」
このカラクリには、僕に取っても見過ごせない事実が隠されていた。彼らと仕事を始めてわかったその訳は、コーストガードの担当オフィサーからもたらされた。はじめは気がつかなかったのだが、彼はことあるごとに僕と2人きりになりたがった。そして、一緒にシャワーを浴びて欲しいとか、同じ男同士だからありえないくらい気持ちよくしてあげられるのにとか、隙を見ては哀願してくるようになるのである。コーストガードの仕事は楽だったけれども、だから僕は、彼らの施設に出かけて仕事の手配が終わると、できるだけそこから歩いて鹿島建設の事務所まで戻るようにしていた。鹿島の事務所の方でも、前例があったのかそういうことには慣れているらしく、昼前に帰ってきた僕を見ても、誰も何も咎めるような言葉は口にしなかった。
僕は昼近くになって戻ってくる滑走路拡張工事のチームと一緒に食堂で昼食をとった。ステーキやマスターベーションの方には、興味が持てなかった。ずっと身構えて暮らしていたこともあり、豊かさや娯楽の匂いのする世界の方がかえって苦痛に感じられたのだ。滑走路拡張工事のチームの乗ったトラックが午後の仕事に出て行ってしまうと、食堂は急に静かになり、何もすることがなくなってしまう。僕は誰もいない食堂で本を読んだり、料理を作る見習いの少年と将棋を指したりしながら時間を潰した。そして透き通るような午後の一番風呂に手足を伸ばして入り、夕方になると坂道を下ってコーストガードの施設に戻って行った。最後にその日の仕事の終了を示す書類にオフィサーからサインをもらい、部屋を出る時、後ろから強く抱きしめられたりしながら「今は仕事中だから」などとありえない言い訳をして、3人で鹿島建設への坂道を戻るのだった。
僕はまだ彼に与えてもいいと思ったことはなかったけれども、いつかはオフィサーの思いを遂げさせてあげるからと匂わせる今の対応は、やはり断じていいものでなかった。でも僕はその恐怖心以上に、島に来て初めて手に入れたこの環境を心底手放したくないと思ってしまったのだ。
「そんなことしていると、いつか取り返しがつかなくなっても知りませんよ。同性愛の情愛は男女の比ではありませんから。」
極上の宇治茶で虎屋の羊羹を食べながら山中さんが嬉しそうに言う。山中さんも半分くらいは本気で心配して、そんな風に声をかけてくれはしたが、肉体的にもやはり、あの灼熱の滑走路拡張工事の現場から離れられるという特権はそう簡単に捨てられるものではなかった。
コーストガードの通訳になって2ヶ月が過ぎた。慣れを感じ始めたこの頃は抱き寄せられたり、首筋にキスされたり、耳を軽く噛まれたりするあたりまではなんとか許容範囲になり始めていたこともあり、とりあえずこのままでいこうと決めていた。片言の英語を使って、屈強な男たちの上に立ち、彼らの手配までできるこの環境は弱虫のくせに“こがしこい”、それでいてええかっこしいの自分には蜜の味ように美味しいものだったのだ。もっとも、コーストガードの仕事は毎日くるわけではなかったから、普段はいつものルーティンで滑走路拡張の肉体労働に勤しむことになる。それでも作業を終えた夕方、牛のように進むトラックの荷台に揺られている時の心地よさは格別だった。紺碧をたたえる太平洋と頬をなでるオンショアの風、まるで儀式のように茜から薄墨にかわる色彩のグラデーション。島全体が沈み行く今日という日を深く慈しんでいるように感じられた。そうやって過ぎていく月日の中で僕はいつしか気がつくと、この島の生活も悪くないかもしれないと思うようになっていたのだった。
「三辻さん、失礼を承知で質問をしますよ。」
「ええ、」
「わたしには、あなたが奥さんを刺すような人には見えない。よかったら話してください、我々でよかったら。」
「おお、じじい、そりゃええ質問じゃのう。」
それは夕方、宿舎に戻るトラックに揺られている時のことだった。僕たちは貰い物のスコッチの小瓶を回し飲みしているところだった。自分にはこんなふうに目上の人たちから改まってかまわれた記憶がなかったし、長く働いた会社を辞める時も実にあっさりしたものだったから、山中さんの襟を正したようなもの言いには正直驚いてしまった。そして、その日の彼らの様子から決して興味本位だったり、からかいの気持ちだったりからその言葉が出たわけでないことも理解できた。後から思い出すとこんな風に彼らを近くに感じられたことが、僕に話をする勇気を与えてくれたのだと思う。
「妻とは3年暮らしました。背伸びして一戸建ての家を購入したのも、妻の希望からでした。田舎育ちの妻は家庭菜園をするのが夢でしたから。トマトやキュウリ、パセリやセージを庭の菜園で摘んでは食卓に並べる生活、そういうのに憧れていたんです。健康な子どもが育つ気がしない?妻の口癖でした。」
「でも結局、子宝に恵まれることはなく、取れたての野菜が食卓を飾ることもなく、妻はわたしを残して家を出て行きました。これからどうするつもりなの?聞いても仕方がないことをすがるように口にしたわたしに来年のテーマはね、とらわれない心って決めているの、そう答えて駅の改札の向こうに消えていったのです。それが2年前の冬の出来事でした。わたしはクリスマスのイルミネーションから逃げるように離婚届を役所に提出し、家を売り、住宅ローンを清算した後の残金を妻の口座に振り込んでから、10年努めた会社に辞表を出しました。」
「年が明け、多摩川に近い部屋を借り、少ない退職金と失業保険が続く間は粘ってみることにして、新しい生活に踏み出しました。ところが会社を辞めてみると毎日することがありません。通勤電車に乗る必要もないし、時間に追われる心配もない。それでも部屋にじっとしていると、じくじくと気持ちが腐ってまいります。しまいには洗髪も歯磨きもおっくうになり、万年床の上でゴロゴロする日が続くようになりました。」
「なるほど、私らは幸いなことに刑務所の中でしたから、規則ただしい生活そのもので、おかげさまでその心配はなかったです。」
「じじい、刑務所のどこが幸いじゃい、どこがおかげさまじゃい、黙っとれちゅうに。」
「わたしを見る人の目が気になりました。だからやがて自転車に乗るようになったのも、わたしにとっては自然なことでした。歩行者でいるよりも自転車に乗っている方がよっぽど街に溶け込みやすいのです。それは立ち止まっていない、物事が絶えず後ろの方に流れて行ってくれるからなのだと思います。見たくないものや誰かの視線にとらわれることが、歩いているよりもはるかに少なくなるのです。自分のような負い目を負い神経が弱っている人間は、普通に歩いていても、つい無意識のうちに見たくないものや人の視線を拾ってしまいます。きっと同じくらいに温かい眼差しや胸のすく眺めがあったのでしょうけれども、貧乏性と言いますか、とにかくスピードを上げて動いていないと居場所がなくなってしまうような気持ちでした。わたしはその日、土手の草の上に仰向けになっていました。長い距離を走った後だったので体中から汗が噴き出していましたが、何かを成し遂げた後のような爽快な気分を久しぶりに味わっていました。ふと目を向けると土手下の車の中で、若い男が助手席の女性に何かを話しています。助手席の女性は半年ぶりに見る妻でした。その時の妻は見違えるように輝いて見えました。何がうれしいのか幸せそうな横顔を見せています。その横顔を美しいと思ううちに、捨てたはずの、すでにけじめをつけたはずの未練が鮮やかに蘇ってきました。色白の若者の方は少し開けた窓の隙間からせわしなくたばこの煙を吐き出しています。エンジンをかけたままエアコンを効かせている車内にたばこの煙は要らないということなのでしょうか。見てはいけないものを見た気がしました。妻のことではありません。一緒にいる見るからにホスト風の男の全てがとても安っぽく感じられたからです。少なくとも自分はあのような安っぽい人間ではなかったはずです。でも妻はわたしではなく、その男を選んでいるのです。」
「男と女のことは複雑ゃから、なかなか額面通りにゃいかんて。」
「ええ、今ならそういうことも少しはわかります。正しいことをしている人間が魅力的であるとは限らないと言うことも。でもあの日の自分は激しい嫉妬から、妻があの若造と裸で抱き合っている姿まで瞬時に想像してしまったのです。妻が時折見せてくれたわたしにだけしてくれると信じていた大胆でまぶしい行為の数々までが、何もわたしだけのためのものではなかったのだと、そんなことまで考えていました。」
「そりゃ、アウトじゃ。」
「ええ、アウトです。でも、心のどこかで妻が後悔し、自分のところに戻ってきたいと思っているのではないかという、淡い期待を温めていたのも事実です。それがまさか、よりによってホストのようなあの若造なのです。その間にも駐車している車はなかなか動き出しそうにはありません。」
「しっかりせえよ、そういうええことはな、女は惚れた男とならきっといつでもしとるんじゃい、それが女の魔性ちゅうもんよ。」
「でも、あの日の自分にはそれがわからなかった。気がつくと自分は車に近づいていました。でも、一方ですごく冷静だったのです。ウエストポーチの中にスイスアーミーナイフが入っていることもわかっていましたから。」
「刺したのか?」
「覚えてないです、この島に来た翌日の、あのさそりの儀式のときと一緒なんです、何かに集中すると周りが真っ白になり見えなくなってしまう。妻に逃げられてからはずっとそうでした。そのときも白いベールがなくなると車もいなくなっていました。そして車の止まっていた場所に血のりのついたナイフが落ちていたのです。」
「警察には行ったんか?」
警察に行く前に、静岡にいる妻の妹さんに電話をしました。そして河原での事情を話しました。
「推理小説は好きですよ、コナンドイル、アガサクリスティ、レイモンドチャンドラー。それでどうなったのでしょう?」
「妹さんからは、何かあったらすぐに連絡するから警察に行くのはそれからにして欲しいと言われました。けれどもいくら待っても彼女からの連絡はありません。翌朝、こちらからもう一度連絡を入れてみると、もうその電話番号は通じないものになっていたのです。」
「なるほど、それでそれからあなたは警察に行かれたのですね?」
「ええ、でも警察ではそういう被害届けは出ていないと言われただけでした。」
「不思議な話ですね。あなた自身に思い当たることはありませんか?」
「思い当たることがあるとすれば、仕事にとらわれ、住宅ローンにとらわれ、妻を幸せにするんだという、今振り返ってみると“ひとりよがり”な思いにとらわれ、タチの悪いことに決して自分は間違っていないという思いにもとらわれて、一人風を切って歩いていたわたし自身の生き方についてでした。そのとらわれの砂浜に建てた家や家庭は波にさらわれて今は跡形もありません。あの日、妻はとらわれない心と確かに言ったのです。もしかしてあの言葉は彼女自身に対してではなく、ずっと確信犯のように夫として“正しいこと”を繰り返してきたわたしに対して投げられた、最後のメッセージだったのかもしれません。そんなボタンの掛け違いから始まった結婚生活に終止符を打ち、きっと彼女は何もかも壊したかったのに違いありません。そのためには愛する対象を通して、彼女自身が違う電車に乗り換える勇気が必要だった、その相手があのホストのような男の子だったということなのかもしれません。」
「三辻、そういう理屈っぽいことではなくてよ、おのれのチャンカーは無事だったのかどうかと聞いちょる。」
「たぶん自分は誰かを傷つけたのだと思います、ナイフには血のりがついていましたから。けれども何かの事情で事が表立って騒がれることはありませんでした。」
「何かの事情?」
「何かの力が働いて、自分にもう一度チャンスをくれたと言うことなのかも知れません。」
「三辻さん、構成概念を駆使して説明を求める心理学とは違い、行動分析学においては全ての行動は100%環境によって決められるものと定義されています。細かいことはわかりませんよ、細かいことは。ですが、今のお話ではあなたには自転車がある。あなたをよりあなたらしい世界に導こうとしてくれる。ちょうど私にとってのシャンソンと同じじゃないですか、それを忘れてはいけません。」
「ええい、じじい、なんでそこでおのれのシャンソンが出てくるんじゃい。話をややこしくすな。いずれにしてもだ、ヤクザの世界でも何でも、命取りになるのは、いつも女よ。いい女が本気になってみい、どんな男も必ず骨抜きにされる。だから政治でもマフィアでも、最後に使うのは女と相場が決まっちょる。」
「でも珍蔵さん、自分の話は政治やマフィアの世界のことではなくて、どこにでもいる普通のカップルに起きたことなんです。」
「普通のカップルに、何が起きたと言いたいんじゃい?ただおのれのチャンカーがおのれ以外の男とおのれの大好きな特別なことをしただけやないんか?そんな細まいこと、別れて何年もして、よくもまあしゃあしゃあと口にできるわな。」
本当に珍蔵の言う通りだと思った。性風俗の世界ではそんなこと日常の業務の一環だと聞いているし、何も何年も思い悩むような特別なことではない。それでも自分がこだわってしまうのはどういうことなのだろう。
「たぶん、自分はきっと妻の言っていた通り、偽善者なんだと思います。」
「まずいなあ三辻さん、今、偽善者と表現されましたね、そんなことをいつまでもつぶやいているようでは、あなたはまるでチャタレイ夫人の不能になってしまった夫そのものですよ。完全に性にとらわれてしまっている。あなたの奥様はこれからはとらわれない心で生きましょうとおっしゃいましたね。なるほど思い出を美しいまま、心にしまっておきたいという気持ちはアマデウスを葬った後のサリエリにも通じる自分本位の考えです。でも、三辻さん、矛盾するようですがあなたはそのままでいいように思います。いや、サリエリの真似をして生きていても仕方がないじゃないですか。あなたがご自分を偽善者だと思うのならそれでいいと吹っ切ることです。それもあなたの個性の一つとして、大切にされることです。奥様のおっしゃられた通り、もう、何からもとらわれることなく、自分を信じて歩いていい時を迎えているのです、きっと、それが今のあなたには必要なことなのです。」
「ねえねえ、ギゼンシャって何? さっきから聴いてると、自転車に乗る人のことを多摩川ではそう呼ぶの?」
「斉藤よ心配すな、ギゼンシャの意味はな、お前と正反対の考えの人のことをまとめた言葉よ。人に見せたくて正しいことをする野郎のことよ。それにしてもじじい、たまには良いこともいいよるわい、まったくその通りじゃい。それによ、男と女のアレは理屈じゃあない本能よ、体の相性よ、チャンカーにはチャンカーにもきっと言い分がある。許すも何も忘れることよ、偽善者のおのれに今できることは、もうそれだけよ。」
その日から半月後、事務所に呼び出された僕は、そこで現場監督から通訳の交代が今朝島に着いたこと、そのためコーストガードの施設にはもう近づかなくていいことを知らされた。合わせて次の揚陸艦で僕が帰還できるよう書類の手配もすでに済ませているということだった。
「来週早々、横須賀から薩摩と牡鹿が来ます。この揚陸艦二隻に8台の車体を乗せて日産の整備工場まで運ぶ作業があるのですが、それに同行してください。この6ヶ月随分足止めをしてしまいましたが、現場の通訳の方も続けていただき助かりました。」
部屋に戻り珍蔵にそのことを話すと、よかったじゃないかと言う。斉藤も山中さんも同じ意見だった。僕は正直どうしたらいいのかわからなくなっていた。いや、その時の自分ははっきりと内地になど、あんな狂ったバブルの東京になど金輪際帰りたくはなかった。ここに来たばかりの頃、あんなに内地に戻りたいと思っていたのが嘘のように、いざ帰れるとなると逡巡する気持ちが入道雲のようにわき上がってくる。
「そりゃ、おのれ、天邪鬼ちゅうものよ。帰りたくとも帰れん奴ばかりのこの島から、おのれは次の船で帰ることができる。素直に乗らんかい、その話にも船にも女にも。」
けれども僕にとって考えてみれば、ここでの生活は内地では決して体験できないことばかりだった。長い間忘れていた人を信じる気持ちや仲間という意識が、ここでは駆け引きなしに存在している。そして、ここに吹きだまった多くの作業員が、あるいは戦死した霊魂の多くが、多分これから先もずっとここから出られないことを知っている。その諦めにも似た、抜け駆けも出し抜きも何もない、素の人間の世界の居心地の良さを知ってしまった今、自分に取ってバブルに沸く内地での生活に戻りたいという理由はもうどこにもなくなっていた。しかもこの半年の間に僕は見違えるように鍛えられた体まで手に入れている。自分はここで生まれ変わることができたのかもしれなかった。
「10人では都市ではないと話しました。三辻さん、なにを悩んでいるのです、ここで学んだことを忘れないうちに持っていくのです、そして、あの狂った大都会の真ん中であなたの都市を見せるのです。この島にいてきれいな気持ちでいることはそれほど難しくはありません。でも、あそこにこの島の都市を持ち込むのは容易ではありませんよ。そしてそのとき本当の審判が下る、たぶんあなたは今までとは違った時間を歩き始めます、それはこの島の地下都市にひしめく多くの魂の代表としての時間が始まるということでもあるのです。」
「この島の都市を持ち込む、、、のですか?」
「そうです、バージェスも指摘しているじゃないですか。三辻さんの持ち込んだ都市も新陳代謝を繰り返し、鉄道や道路の整備とともにやがて郊外へと発展し、ゲットーやスラムの再開発までの長い歴史を刻んでいくのです。一人一人の人生とはシカゴ学派の指摘する都市の変容そのものと言えるのです。」
| 三辻 孝明(みつじたかあき) 「CUBE IT AUSTRALIA」のCEO(最高経営責任者)。早稲田大学人間科学部環境科学科卒業。1989年より豪州在住。2020年8月10日永眠。 |
【関連記事】
関連記事:【新型コロナウイルス関連】日豪物流業界のパイオニア。死と向き合い、激動のパンデミックの中を生きる。
関連記事:ドロップアウトの達人
関連記事:Madison






