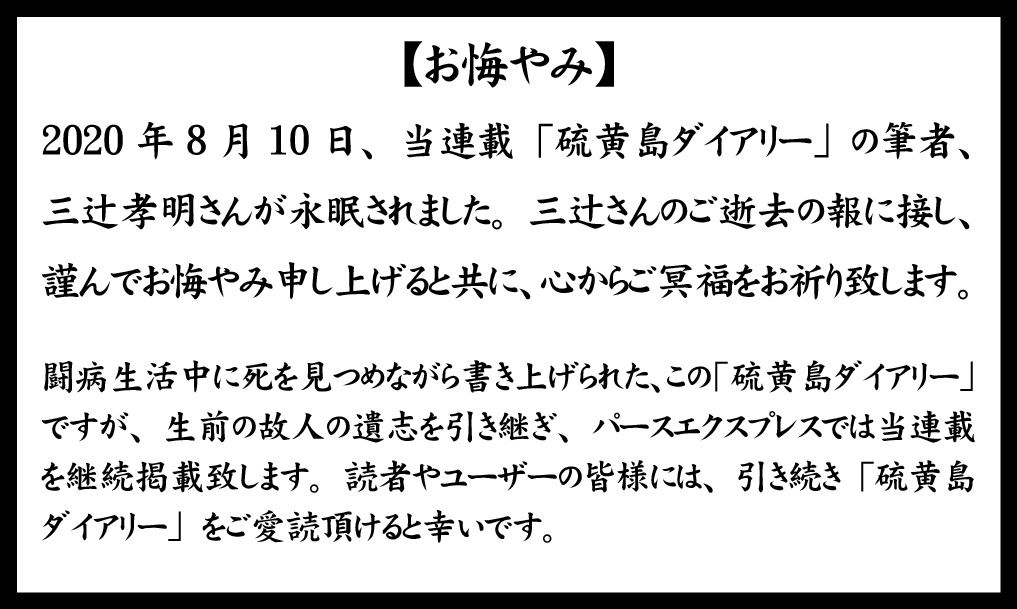
筆者三辻孝明さんは、昨年の2019年8月に癌の告知を受けました。三辻さんは以後、自然療法や抗癌剤治療を経て、癌の摘出手術を受けた10ヶ月間、「静かに死を見つめながら、久しぶりに文章を残すことができました」と話しています。そして「レポートに毛の生えたようなものですが、過去の自分自身の経験を形にできたことは少し肩の荷が降りたような気持ちです。よろしければ、ご一読ください」と。
<第一章『硫黄島』3話はこちらから>

【連載小説】
硫黄島ダイアリー
三辻孝明
第一章『硫黄島』4話
5月に入り、待っていた新人が同じ部屋に来た。
60過ぎの山中さんである。あんなじいさんで大丈夫なんか?朝の食堂でそんな声が上がったからかわからないが、彼がここで使い物になるのかどうか少しの間様子を見ることになった。その山中さんは、今はシャンソンの歌手だそうだが、嘘か本当かその前は大学で教えていたのだという。そういえば自己紹介の時、島に来た理由をたずねられてこんなことを口走っている。
「簡単に申し上げますと、わたし自身の独立変数を操作することで従属変数がコントロールされるという関数関係を検証する必要があったのです。」
仔細はどうあれ僕はこれでこの島から脱出できると思うと、そのことが本当にうれしかった。島に来てからはずっと息を詰めて、言いたいことも口にしないで暮らしていたようなもので、塀の中の世界を知る恐怖の男たちに囲まれ、亡くなった少年兵からの、あの世からの手紙まで届いてしまったのだ。だから、ここでの生活から何か新しい喜びを見つけようとか、そういった余裕のようなものはほとんど持てないでいたのだった。周りを見てみても、みんな強そうなことは言っているけれども、大なり小なりここでのありえない体験に心を閉ざして見て見ぬ振りをして生きていることは、僕とそうは違わないようだった。長くここにいる人ですらそうなのだから、僕のような新人はなおさら、この島からは一刻も早く立ち退いた方がいいに決まっていた。
ところで、新人の山中さんは若い頃何かの事情で大学を辞め、その後シャンソンの歌手になったのだそうだ。けれどもある時、勤めていた店で傷害事件に巻き込まれ、ホステスを刺した罪で刑務所に送られてしまった。
「実は身代わりで入所しました」
ところが刑期を終えて出所してみると、身代わりをした人も芸能の世界に顔の利いていたはずのその事務所も無くなってしまっていた。
「出てきたらもっと良いところで歌わせてやるってそれが約束だったんですけれども・・・」
結局、山中さんに残ったのは身に覚えのない前科だけだった。
「私が馬鹿でした」
あとは坂を転げるようにしてこの島にやって来たのだそうだ。
「じじい、おのれの話には落ちがない。聞いているこっちまでむかむかしてくるわい。」
山中さんは煙草を吸わない。正確には表向きは煙草を吸っていないことになっている。理由はまたいつかシャンソンを歌うことになった時のために、タバコで喉をやられたくないからだそうだ。けれども温厚な山中さんですらここでの生活は、やはりタバコぐらい吸わないとやっていけないらしい。そこで山中さんは自衛隊の売店でタバコを買うと、まず一服して、それからタバコの箱をどこかに隠す。それもできるだけどこに隠したか分からなくなるような厄介なところに隠す。それが風呂場のボイラー室の棚の奥だったり、脚立がないと手の届かないトイレの水タンクの後ろだったりする。
「どうして隠すのですか?」
「それは惰性でタバコを吸いたくないからです。」
「でも、隠しておいて忘れてしまったら?」
「実はね、忘れたいのです。忘れてしまって本当に吸いたい時に見つけるのが理想なんです。でも、そうはならない。どんなに複雑な場所に隠しても覚えているものです、執着心なんでしょうか、タバコに縛られてしまっている。あなたにもそういう覚えがありませんか、自然につきあえるまで忘れていたいと思うことが。」
その時の自分にも確かに心当たりがあった。先月、受け取ったキヨシ少年からの手紙にしても、初めは誰かが巧妙に僕をかついで面白がっているのかもしれないと思い、何日も息を詰めて周りの様子をうかがったのだけれども、そういう兆候はどこにもなく、斉藤に問いただしてもキヨシからの手紙に違いないと言い張るのだった。イタズラでないことがわかったからといって、それで気持ちが楽になるものでもなかった。
「影響が強すぎるとどうしても近くにいられなくなってしまう。女性も一緒です。どんなに素敵な女性でもできれば自然につきあえるまで距離を置いていたい。でもいったん執着し、絡め取られてしまうと彼女を忘れることがこれまた難しい。」
となりで箸を動かしていた珍蔵がいう。
「あたりまえじゃ。夕方隠しに行って、その晩にのこのこ吸いに行くんだから忘れるわけがないわい。」
「お言葉を返すようですが珍蔵さん、あなたは本当のタバコの吸い方をご存じない。いえ、この“大切なものとの距離”という概念は人が生きて行く上でもっとも重要な作法なのです。自然におつきあいできるまで、静観し物事との距離を保つということは、ジェンントルマンとしての大人が身につけなくてはいけない基本的な作法なのです。」
「おお、そんな訳の分からない作法なんてな、初めから知りとうもないわい。」
「まああなたのおっしゃる通り情けない話ですが、せっかく苦労して隠したのに夜中にどうしても吸いたくなって宿舎を抜け出して吸いに行くこともあるのです。」
結局、山中さんの話すジェントルマンの距離とは、暗がりのために脚立から足を踏み外し、結局タバコ一本を吸うために怪我までして帰ってくることを指すのである。でも喉を傷めないため、シャンソン歌手復活を目指す山中さんはここでは表向きタバコを吸わないことになっている。
「なにが表向きじゃい。どいつもこいつもこんなド裏の人生歩いているくせに。」
それにしても雨の多い年だった。6月の梅雨はないはずなのに降り始めた雨はなかなか止みそうになかったし、山中さんの採用テストの方も当分終わりそうにない。自衛隊の売店では日本酒もハイライトももう売っていない。輸送機がこなくなって1週間が過ぎようとしていた。いや、正確には一回輸送機は来ている。姿は見えないけれども厚い雲の向こうに、確かにプロペラのエンジン音を響かせていた。入間基地からここまでは往復で6時間近い飛行を強いられるから降りられずに帰って行く輸送機の方も大変に違いない。厚木からの練習機もこの天気のおかげでこの2週間姿を見せない。食事ばかりではなく、島での作業が中止になっているため宿舎の作業員たちも収入を失っている。けれども食事はとらなければならないし、とる度にこれからもらうはずの給料から天引きされるのだからたまらない。最近は食事を一日一回しかとらない作業員が増え、残り少ない島の食料事情にうまく協力する形になっている。そんな状況が続くある日、今までとは違う金属音が島をおおう雨雲の向こうから聞こえて来た。
「ありや、ジェジェジェットだ」。
食堂でお茶を入れていたてるおが呟いた。ジェットだと何か違うのだろうかと隣の斉藤に尋ねると、たぶん横田からの米軍の輸送機が来たんじゃないかなという答えだった。それに応えるようにコーストガードのジープが目の前の坂を滑走路に向かってのろのろと上って行く。
「この横風じゃ降りないな。」
飛行機は風を真正面に受けて着陸するのが一番良いとされる。理由は向かい風の強い分スピードを落としても浮力を保てるからだ。遅いスピードで降りてくる飛行機は短い滑走路にも降りられるけれど、速いスピードで降りなければならない飛行機は、着陸してからもなかなか止まれない。それと横風を受けて着陸する場合、機体が真横からの風で持ち上げられてひっくり返りそうになるため、できるだけ斜めに風を正面から受けるようにして進入する。雪道で車がドリフトしている状態に似ている。そして、タイヤが地面に触る寸前にそれまで斜めを向いていた機首を正面に戻す。コーストガードの通訳の話だと、海外の飛行場は滑走路が2本ある所が多く、だいたい十字にきってあるのでどの方向から強い風が吹いてきても、滑走路への侵入ルートを変えることで真横からの風を受けないようにできている。
横田基地と違い島の滑走路は短いし、十字には切っていない。目の前のすりばち山も見えないほどの視界の中を、鋭い金属音を残してスターズアンドストライプスを吹き付けた銀色の輸送機が現れては消えて行く。それを見守る作業員のほうも切実である。特に出所したばかりの作業員にとっては、テレビもラジオもなく食い物まで制限され、生きようが死のうがニュースにもならないこんな奴隷のような境遇は、刑務所じゃあるまいしもうたくさんのはずだった。それが今わずか20人足らずのコーストガードのために、アメリカは最新鋭のジェット輸送機を投入して彼らの好物のバドワイザーとステーキの肉を届けようとしている。結局一時間ほどして輸送機は着陸した。
「燃料の関係で横田にすぐ戻るそうですから、みなさん手を貸してください。」
自衛官のかけ声で機体後部からの搬出作業が始まる。窓のない倉庫のようなむき出しの機内の前方に鉄階段が見え、その上にジャンパー姿の2人が立っている。暴風の中で輸送機を降ろしたパイロットだった。
「あいつらはすごい」
確かにその通りだった。なぜならヘルメットを脱いだ2人のパイロットは、いずれも若いアメリカ人の女性だったからである。
「絵に描いたようなマーチャンダイスです。」
食堂で山中さんの講義が始まっている。
「米軍は時々やるんです、こういうゲーム見たいなマーチャンダイスを。」
山中さんの話しによると思いやり予算なのだそうだ。自衛隊と違いお金も人も余っているからこんなふうに半分遊びのようなこともできてしまう。この島にはあの戦争以来40年以上女子がいなかった。それがふたりも輸送機から降りて来たのだから島の空気が変ってしまっても仕方のないことだった。何を見てもあまり反応しない作業員の間にも、熱気のようなものが生まれている。ただしそれは、ここではどこにも吐き出すことのできない熱気だった。
「島での暮らしは逃げ出すことができません。内地のようなシャンソンのクラブもないし、付き合ってくれるホステスさんもいない。でも、誰だって人肌恋しいし一人では生きて行けないこともわかっています。」
確かに口には出さないけれども、全員があれから女のことを考えている。
「そうそう私の好きなアリストテレスの言葉を思い出しましたよ。10人では都市はできないが、10万人ではもはや都市とは言えないと。その定義ですと、さしずめここは巨大地下都市の島ということになりますな。」
「“マージャン”がどうの“ダイス”がどうの“クリトリス”がどうしたの、じじい黙って聞いちょれば、さっきからおのれ、一体なにが言いたいんじゃい?それにここではな、ダイスなんて言わんでええ、サイコロじゃい、サイコロ。」
「あなたのご質問に簡単にお答えしますと、秩序が守られるためには絶え間なく壊されなければならない、あるいは、生が一カ所にとどまるためにはいつも走り続けなければならないということです。」
「走り続けるて、おのれこんなちいぽけな島でどうやって走り続けるんじゃい?」
結局、山中さんには多重人格者という烙印が押された。シャンソンの山中さんの方は話がわかりやすいけれども、大学の先生の方はたちが悪いというのだった。そんなわけで現場監督も持て余す山中さんに、いつまでも合格の決定は下されず、そのため心待ちにしていた僕の内地への帰還の話も、いつの間にか棚上げになってしまったのだった。
*****
三辻様、あなたが手紙を読んでくださるだろうことは分かっておりました。自分のような存在と積極的に関わりたいと思う人は、斉藤さんを除いてここにはおりませんから、こうしてまたあなたに手紙を渡せる幸せを、あなたに対する深い感謝の気持ちとともに伝えさせてください。日本が戦争に負けたことは斉藤さんからも伺いました。自分もこの戦争は負けるのではないかと思っておりました。ただそれを口にすることができなかっただけでしたので、負けたことについては残念ですが、それほど驚いてはおりません。生きていた時とは違い、この島で亡くなった兵隊にとっては日本兵もアメリカ兵ももう境はないのです。亡くなってしまった、もう生きて祖国には帰れない、生まれ育った町には帰れないという厳然とした事実の前に、敵や味方という考えはあまりにも小さいことなのです。ただただ全てに終止符を打ち、両親からいただいた肉体から離れなければならない現実を前に、勇敢な兵士の全員が言葉を失ってしまうのです。旅立つまでの間ずっと声を上げて泣いているものもおります。黙って自分の亡骸を見つめているもの、取り乱しているもの、祈りながら静かに旅立ちを待つもの、様々ですが二度と今までいた世界に戻れないと分かって初めてことの重大さに気づいている点では、たぶん全員が一緒なのです。
そこでは英語も日本語もありません。自分の隣でうずくまるアメリカ兵の痛みや悲しみも、言葉を解す必要もなく自分には分かりました。旅立ちは死を受け入れた順番と申しますか、納得した順番から自然に行われてまいります。みな最後には平和な気持ちでこの世に生を受けたことに深く感謝をし、そして肉体に縛られていたことからの解放を素直に受け入れながらひとりずつ旅立ってまいります。怪我を負った兵隊がいます。誰も助ける人が現れない日本の兵隊の場合、痛みに苦しみながらも長い間、死と戦い続けます。それが何週間も続くことがあります。やがて精も根も尽き果てて旅立つ瞬間を迎えるのですが、その時には本人も安らかな気持ちに包まれているのです。でも、その数週間は本当に苦しい戦いです。
同じような場合でも多くのアメリカ兵は、旅立ちの途中から、また今生きているこの世界に戻ってまいります。たぶん野戦病院などで適切な治療を施されてなんとか一命を取り止めたのだろうと思います。不思議な話ですがそんな時、逆に彼らは戻ることに抵抗をおぼえるのです。安らかな旅立ちの世界からあの激痛の世界、肉体という制限のある世界に引き戻されていくわけですから、もうそっとしておいてほしいという気持ちのほうが戻りたいという気持ちに勝っているのだと思います。地上では地獄絵のような戦闘が続き、絶命したものたちの世界では最後まで望みを捨てない日本兵の多くが旅立って行きましたが、足や腕を吹き飛ばされ、訪れる死を素直に受け入れはじめていたアメリカ兵の多くが、激痛の待つ現世に戻されていくという皮肉が繰返されておりました。
ただ、あの島から生還できなかった日本兵のほとんどが、勇敢に散ったのではなくて最期まで帰りたいと息をつめながら痛みや飢えに向き合っていたものたちなのです。そのことだけは分かっていただきたいと思います。あなたに直接関係のない話を繰り返し大変申し訳なく思います。自分は伝令が仕事でありましたので、どうぞ過去からの伝令だと思って、お聞き流しください。
| 三辻 孝明(みつじたかあき) 「CUBE IT AUSTRALIA」のCEO(最高経営責任者)。早稲田大学人間科学部環境科学科卒業。1989年より豪州在住。2020年8月10日永眠。 |
【関連記事】
関連記事:【新型コロナウイルス関連】日豪物流業界のパイオニア。死と向き合い、激動のパンデミックの中を生きる。
関連記事:ドロップアウトの達人
関連記事:Madison






