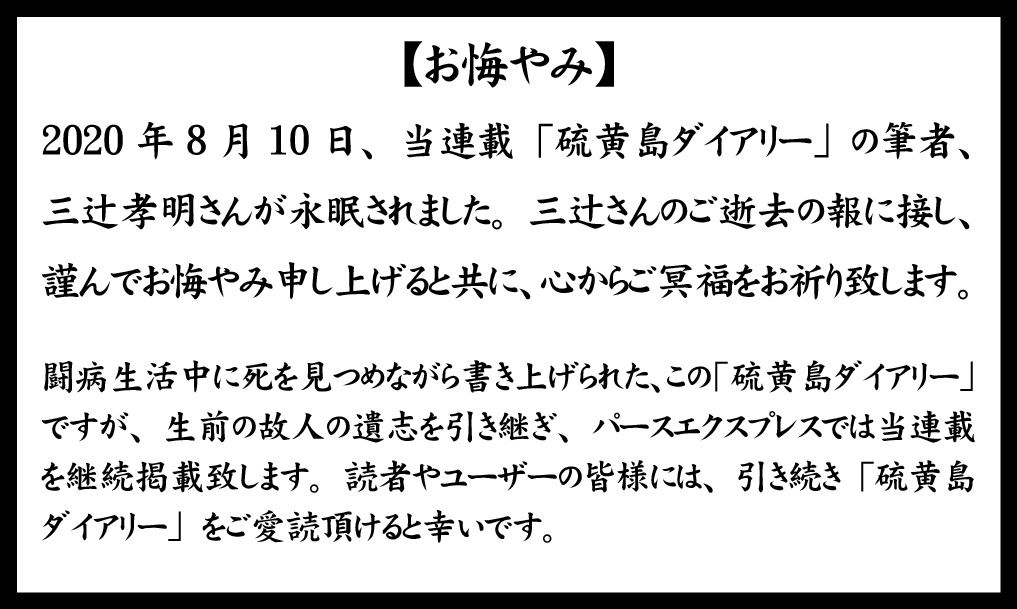
筆者三辻孝明さんは、昨年の2019年8月に癌の告知を受けました。三辻さんは以後、自然療法や抗癌剤治療を経て、癌の摘出手術を受けた10ヶ月間、「静かに死を見つめながら、久しぶりに文章を残すことができました」と話しています。そして「レポートに毛の生えたようなものですが、過去の自分自身の経験を形にできたことは少し肩の荷が降りたような気持ちです。よろしければ、ご一読ください」と生前に語っていました。
<第二章『ROSEMARY & SHARON』3話はこちらから>

【連載小説】
硫黄島ダイアリー
三辻孝明
第二章『ROSEMARY & SHARON』4話
シャロン・ワイズブロットを語る時、彼女の病気との闘いを抜きにこの話を進めることはできない。
タスマニア島出身のシャロンが最初に発病したのは、ニューキャッスル大学に進学して2年目のことだった。幸い発見が早かったことで、胸の腫瘍の摘出手術は成功し、その後も定期的に継続される検査と抗がん剤治療のおかげで彼女は無事大学を卒業し、日本語を専攻していた関係で今の仕事、三田のオーストラリア大使館に勤めている。1987年7月のことだから、あれからもう3年になる。
だが腫瘍の摘出とその後の再発を防ぐ抗がん剤治療は、若いシャロンの美しい髪をうばい、また集中治療の施される度に尋常でない肉体的苦痛を彼女に与え続けていた。その中で、シャロンは他の誰よりも生きること、今を大切にすることを学んだ。彼女の出入りする癌病棟の仲間のほとんどが、若くしてこの世を去らねばならない運命の下にいた。彼女自身も例外ではなかった。担当の医師からは、はっきりと若い肉体に生まれた腫瘍はたいへん危険であることを告げられていた。そのことで、病気が再発し、自分が死に向かうことになったとしても、じたばたしない覚悟だけはできているつもりだった。だから、彼女が向き合う、彼女の生きようとする「今」は、他の若い人とはちがう奥行きを持っていた。そしてそのことがシャロンの誇りであり、彼女の生きる支えに他ならなかった。
家族は両親を含めて5人、シャロンは三姉妹の長女だった。父親の勤める中学校のあるタスマニア島第2の都市、ロンセストンが彼女が生まれ育った街だ。ロンセストンの近くには、人の手の入らない自然のままの湖がいくつも残っている。幼いころのシャロンは父親のがっしりとした背中に腕を回しながら、彼の運転する古いトライアンフでその湖をめぐるツーリングに行くことを何よりも好んだ。鼓動のようなオートバイのエクゾーストノート、湖に通じる道の両側に広がる樹齢数百年の原生林。そして何よりも、誰もいない湖で父を独占できる喜びが彼女の心をいつもツーリングへと駆り立てていた。
タスマニア島には、今でも無傷の自然がたくさん残っている。200年前、この島で暮らしていたアボリジニと入植しようとやってきた白人との間に争いが起こった。同じような争いは、その頃のオーストラリアの至る所で起きていたにもかかわらず、タスマニア島だけは抵抗するアボリジニを女子どもに至るまで皆殺しにしてしまうという凄惨な歴史が残っている。この島はそれほどに、守るアボリジニにとっても、入植しようとした白人たちにとっても、目もくらむほどの魅力を備えた誰もが安住できると信じるに足る、豊かな自然をもった場所だった。
シャロンは白人がアボリジニを制圧した、そんな島の歴史を憎んだ。自分たちの先祖がしたことは紛れもなく殺人であり凶悪犯罪であると主張して、小学校に両親が呼び出されたことも一度や二度ではなかった。だから、タスマニアの自然がどんなに無傷でも、若い彼女はその中にかならず血のにおいをかいでしまう。タスマニア島から遠く離れたニューキャッスルの大学に進学を希望した彼女の気持ちは、そういうところにも起因していたのである。
シャロンはローズマリーと違い、小柄な女性だった。身長は160cm、帽子をかぶると端正な顔立ちの日本人の少年に見えないこともなかった。彼女は完璧にちかい日本語を話した。瞳は黒に近い青、日に焼けると赤くなってしまう白い肌や、顔にそばかすが残っているところはローズマリーと一緒だった。ふたりは共に水泳部でシャロンはブレストストローク、ローズマリーはフリースタイルの選手だった。シャロンはいつも黒い色の服を好んで身に着けた。型にはまらない服装だけでなく、彼女は何事にも子どものような冒険心を持ってのぞんだ。だから下着のモデルも、クラブのホステスの仕事も彼女が見つけたものだった。事件があった日、シャロンは大使館の仕事で神戸にいた。翌日、出張先から戻った彼女は、カーテンを引いたままの部屋で口もきけなくなっているローズマリーを見つけ、話をする前にそのおおよそを理解したのである。
*****
翌週、私は今までどおりクラブに顔を出した。クラブのママからはローズのことを聞かれたけれども、家を出てしまって行方が分からないとだけ伝えておいた。たぶんレイプされた時に脅かされていたのだろう、ローズの様子から男の名前だけは決して口にできないと決めていることがうかがえた。彼女に起こった災難は間違いなく私が呼び込んでしまったものだった。ローズがお金で体を売るような子でないことは私が一番よく知っているし、彼女は決してはっきりものを言う子ではなかったから、男に付け入られてしまったに違いなかった。日本に来て日の浅い彼女にとって、日本の男性の持つ女性観や女性に対する接し方というものは、まだ未知の部分がほとんどのはずだった。だからホステスのバイトも、ほんの冒険の延長で始めたはずなのに、私たちはどこかでボタンを掛け違えてしまった。
ローズは美しかった。
長い金色の髪、グレーブルーの瞳、ボーイッシュな細い体に似合わない形のいい胸、透き通るような繊細で白い肌、それに少女のような微笑、そのすべてが旬だった。だからといって、それを暴力を使って奪っていいという法はない。もしもこの国の男性の多くが、つまるところ力ずくで女性を陵辱できると考えているのだとしたら、そして陵辱される方の女性も実は心の底で密かにそれを望んでいると男どもが信じているのだとしたら、こんなに残念な話はない。シドニーではほとんどのビーチで女性のトップレスを見ることができる。だからといって、彼女たちが力づくで貞操を奪われたいと思っているとは、誰も考えていない。東京のような先進都市の裏側で、今もやくざや暴力団が市民権を得て存在している。タレントやエンターテイメントの世界にも大変な力を持っていると聞く。そして何百年も続いた男性社会の価値観が、当たり前のように幅を利かせている。レイプに代表される性差別は明らかな犯罪であり、黙って見逃していいことではない。そうでないと、この街のもつ自由な空気はやがて行き詰ってしまう。ローズのようなこれから花開こうとしているつぼみが育たない街になってしまう。例えバーゲンセールの下着でもローズが身に着けると神々しく見えてしまうように、ローズの美しさには、その控えめな性格が作り出す奥行きのようなものがあった。彼女は自分の意思や意見はきちんと持っているけれども、相手のことを考えていつも一歩下がって見ている人だった。恵まれない生い立ちにも道を外すことなく、彼女が身に着けたひたむきで誠実な生き方を貫いていた。
ローズは何も間違ってはいない。彼女は100%被害者のはずだった。あれ以来何も話そうとはしない彼女を守るためにも、彼女の自由を取り戻すためにも、私はそのことをきちんと証明しなくてはならなかった。
もうひとつ、私たちの住んでいるアパートメントの住所と電話番号は、クラブに伝えてしまっているので、直ぐにも引越す必要を感じた。長者丸のアパートメントは大使館の職員が3年住んでいたものだった。入り口がオートロックになっていて、部屋のモニターで訪問者を確認できるようになっている。家賃は安くはなかったが、ローズの安全にはかえられなかった。その月の終わりの雨の夜に彼女は越していった。私はやはり状況がどうあろうとも、大使館を動かして日本の警察に男を調べさせるべきだったのかもしれない。彼女の去った後の押入れの中に、大きな金だらいがひとつ残っていた。それ以上の悲しい眺めを私は知らない。
| 三辻 孝明(みつじたかあき) 「CUBE IT AUSTRALIA」のCEO(最高経営責任者)。早稲田大学人間科学部環境科学科卒業。1989年より豪州在住。2020年8月10日永眠。 |
【関連記事】
関連記事:【新型コロナウイルス関連】日豪物流業界のパイオニア。死と向き合い、激動のパンデミックの中を生きる。
関連記事:ドロップアウトの達人
関連記事:Madison






