筆者三辻孝明さんは、一昨年の2019年8月に癌の告知を受けました。以後、自然療法や抗癌剤治療を経て癌の摘出手術を受けるなど、その約10ヶ月間、「静かに死を見つめながら、久しぶりに文章を残すことができました」と話しています。また「レポートに毛の生えたようなものですが、過去の自分自身の経験を形にできたことは、少し肩の荷が降りたような気持ちです。よろしければ、ご一読ください」と語っていました。
そして、2020年7月16日に当「硫黄島ダイアリー」の連鎖がスタートすることになりましたが、翌月の8月10日、残念ながら三辻孝明さんは帰らぬ人となってしまいました。
闘病生活中に死を見つめながら書き上げられた当連載「硫黄島ダイアリー」ですが、生前の故人の遺志を受け継ぎ、パースエクスプレスでは連載を継続掲載致します。読者やユーザーの皆様には、引き続き「硫黄島ダイアリー」をご愛読頂けると幸いです。
<第四章『CHEMISTRY』3話はこちらから>
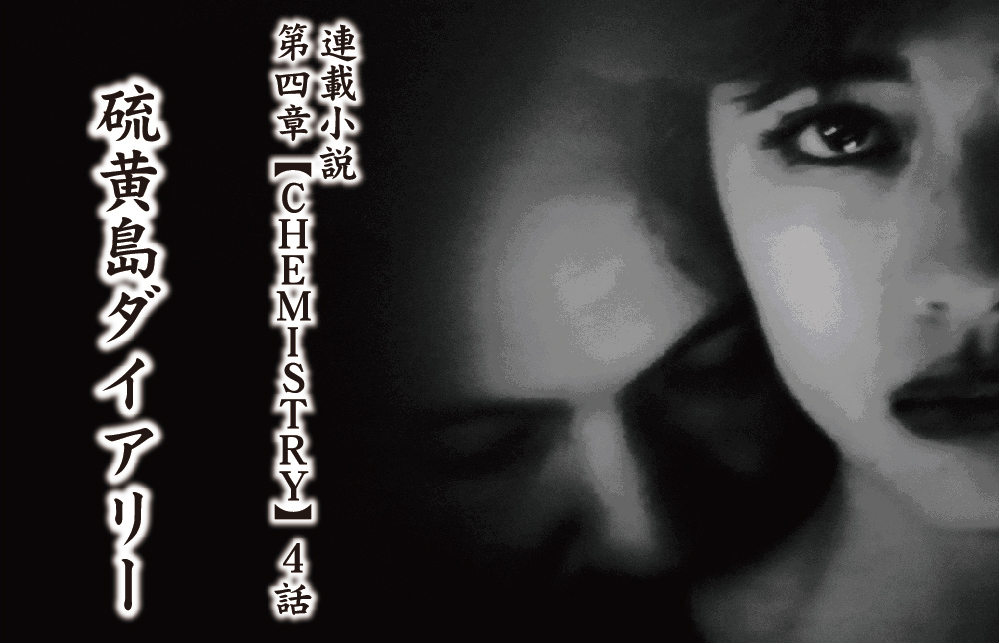
【連載小説】
硫黄島ダイアリー
三辻孝明
第四章『CHEMISTRY』4話
辺りはすっかり暗くなってしまった。いくつもの坂を登ったり下ったりした。そして、私はついにあの夜、ローズに電話をした公衆電話を見つけたのだった。
そこからは簡単だった。坂を登り、登り切った十字路を左に曲がり100mも歩くと、ついにマリオのアパートメントの前に出た。なぜか懐かしさがこみ上げてきた。あんなに怖い思いをした場所なのに、あのドラマの様な展開が急に目の前に蘇ってきて、私はしばらく動けなくなってしまっていた。
あの夜、偶然の中に、私は確かに神の存在を見ていた。苦し紛れに口をついて出た言葉が、私を助けるために寝静まった深夜の街から、刑事を連れて戻って来てくれたのだから。
あれを奇跡と呼ばないで、なんと呼んだらいいのだろう。そして私を救ってくれた三辻孝明という男の子は、きっと神様からの使者に違いなかった。どんなに意地を張ってみても、ローズの言うとおり私の記憶の中で彼はずっと輝いている。そしてあの出来事は、消えようとしている私の未来への希望を、もう一度強く思い出させてくれる。
そう考えた時、私は急に目の前の部屋を訪ねることが恥ずかしく思えてしまった。今の私は神様の使者に、好きな人に会いに行くのに、ワインもチョコレートも、花束さえも持ってはいなかった。
********
「突然で申し訳ないけど、もう二度と私たちの周りをうろうろするのはやめてください。」
ドアをノックしていたのは、キヨシ少年ではなくて黒い髪の外国人の女性だった。僕はそこに彼女が立っていただけでもすごく驚いたのに、彼女は初めから完全に怒っていた。
二度とうろうろするのはやめろって?
いきなり、一体何のことをこの人は口走っているのだろう?声に出して問いただしてみようと思うのだけれども、どうして彼女と会う時には、いつもこんな風に、相手のペースについていけなくなってしまうのだろう。そう思うと、言葉が続かなかった。とにかく突然訪ねてきた黒い髪の外国人の女性は、怒っていた。僕もそのまま黙っていると、彼女は目の前で踵を返してしまった。
「どれだけ心配していると思っているのよ。」
しかも最後のその投げつけるような言葉には半分泣き声まで混じっているではないか。彼女は背中を向けたまま階段を急ぎ足で下り始めた。僕は放っておくわけにも行かずに、急いで彼女の前に回りこんだ。そして次の瞬間、倒れてくる彼女の体を腕の中に感じたのだった。
********
あいつの話では、私は高い熱を出してそのまま一昼夜、彼の部屋のベッドの中でうなされていたらしい。目覚めてみると知らない部屋の天井が目に入った。彼が隣の床の上に座布団を並べて眠っているのが見える。私はベッドから這い出すと、トイレで解熱用の座薬を使った。手洗いの鏡の中に、青い縞模様のパジャマを着た自分の姿が映っている。服も着せ替えてくれていたみたいだった。
「もしよかったら、ヨーグルトでフルーツでも食べませんか?コーヒーはやっぱり体に悪いから。」
バスルームから出ると彼はキッチンに立って、フルーツを細かく刻んでいるところだった。そして近づいてくると、私の額にレモンの匂いのする湿った手のひらを当てて、だいぶ下がったけれども、もう少し横になっていた方がいいと思います、と言った。彼は親切だった。私は言われたとおりに、ベッドに横になった。
あいつはやっぱり宇宙人なのかもしれない、半分熱にうなされながら、でも私はそのことがうれしかった。
********
倒れる直前、彼女は下を向いていた。泣き顔を見られたくなかったのだろうけれども、その時の彼女は、こんなことを言う立場じゃないけれども、マスカラが流れてしまったことも含めて、胸が痛くなるほどにキュートだった。
部屋に彼女を運び入れ、ベッドに横にしてから、少し躊躇したけれどもスカートとブラウスを脱がせて、パジャマを着せた。額に手をやると、すごい熱だった。氷枕を作り、頭の下に入れ、氷嚢でわきの下を冷やした。子どもの頃、熱が出ると祖母が決まってそうしてくれたからだ。途中で氷が足りなくなり、近くのコンビニに買いに行った。そして明け方、睡魔で横になるまで、額のタオルを変え続けた。
「バスタオル借りちゃった。」
翌日の夕方遅く、バスルームからシャワーを使い終えて頭にタオルを巻いて出てきた素顔の彼女は、とてもボーイッシュに見えた。昔見たローマの休日という映画のオードリーヘップバーンのようだった。その時、僕はマグカップにレモンを絞ったお茶を注いでいた。
「ハチミツ、入れますか?」
「ブラックのままでいい。」
あんなに高かった熱は、嘘のように引いていた。風邪を引いたのではないらしい。マグを渡し、並んでテーブルの椅子に腰掛ける。風のある夕方だった。レモンの香りが部屋の中に広がっている。隣の家の窓辺に桔梗の鉢植えが見えている。
「この部屋、なんだか懐かしい、それにとても静か。」
「静かなだけがとりえの部屋ですよ。」
「私たち、まだ自己紹介もしてなかったよね?」
「ええ、急にこんなことになってしまって、無断でパジャマを着せてしまったり、すまないと思っています。」
黒い髪の女の子は「シャロン・ワイズブロットです。シャロンでいいわ」と言いながら、レモンティーを口に運んだ。そしてリンパ腺が腫れると決まってこんな風に高い熱が出るのとつけ加えた。
「でも、いざという時には薬があるから大丈夫だけど。」
桔梗を見ると京都を連想すると言いながら、彼女はくつろいだ表情を見せている。美しい横顔だった。僕も自己紹介をしようとすると、彼女はその言葉をさえぎった。
「もう知っている。三辻孝明、34歳、離婚暦一回、大型特殊の運転手。この間、逃げて行った後に警察に行って調べておいた。それで、ここからは君のこと、なんて呼んだらいい?」
「タカでどうですか?」
「オーケー、じゃあタカ、それじゃどこから話そうか?」
「そうですね、伺いたいことはたくさんあるのですけれども、シャロンさんは、高い熱を押してどうして僕を訪ねてきたのですか?あの日、僕が急に逃げ出してしまったことに関係があるのですか?」
「そのことは、もういいの。」
「もういいのってシャロンさん、でも、あなたは僕にうろうろするなとか、とても心配したのだとか、倒れる前に、そういう言葉も投げかけていました。僕には一体何のことをあなたが伝えようとされていたのか、本当にわからないのです。」
「もうしつこいなあ、ねえ、ほんとうにもういいのよ、済んだことなんだから。」
「タカ、ところで今日は何の日か知ってる?」
しばらくすると彼女はそう口を開いた。僕の質問にはもう答えるつもりはないようだった。
「今日ですか? 一年で一番忙しい日の次の日かな。」
「何それ?昨日はそんなに忙しかったんだ?」
「昨日は神奈川の海辺の街を訪ねて、それから品川から寄り道をして部屋に戻ったら、いつものおかしな夢で島の友達に会って、目が覚めたら君がそこに立っていたんです。」
「いつものおかしな夢?」
「いや、説明すると長くなるし、気にしないでください。」
「何よそれ、長くなっても構わないから、よかったら説明してくれないかな?」
僕はこういうオカルト的な話をするのは嫌だなと思いながらも、硫黄島の少年兵との出会いから、今日までのことを彼女に話した。意外なことに彼女はそれまでとは違い、一言も言葉を挟まないまま僕の言葉に耳を傾けていた。
「自分でもこういう体験をすることになろうとは、思ってもみなかったです。それに、その小柄な少年兵からつい昨日、これから何が起きようとも、勇気を持って見守ってほしい、逃げるようなことはしないでほしいとアドバイスを受けたばかりなのです。」
「とても興味深い話ね、そういうことが昨日に集中して起きたわけなのね?」
「ええ、いろんなことが起きて、ほんとサプライズ・デイだったのです。」
「サプライズ・デイ?」
「びっくり、びっくりの連続の日っていう意味で使ったのですけれども、何かおかしいですか?」
「タカ、英語では絶対サプライズ・デイなんて言わないよ。」
「じゃあ、何て言うのかな?」
「A day full of surprises.」
「でも、サプライズ・デイでも通じたのでしょう?」
「うん、通じたけど。」
「じゃあ、大丈夫でしょう?」
「だめよ、だって私こっち長いから、だから日本人の英語が分かっちゃうのよね。それよりタカ、さっきの質問の続き、今日は何の日でしたっけ?」
「A day full of surprisesでしょ?」
「まじめに答えてよ、今日は七月七日、七夕よ。あなた日本人なんだから七夕ってどういう日か知っているんでしょう?」
「一年に一回だけ天の川を越えて、乙姫様とどこかの野郎が会っていい日だったと思う、確か。」
「どこかの野郎? あなたって面白い人ね。」
言いながらシャロンが笑い出す。網戸の向こうから少し涼しい風が入ってきた。彼女の体の匂いがする。香水にライムの香りが混じっている。そして、そのとき突然彼女の顔が近づいて来たのだった。
「七夕は、一年に一回しか会えない2人のための日。違う?」
彼女はそのまま僕の唇にキスをした。
「初めて会った夜から、ずっと意識していた。でも、誤解しないで、私がこの気持ちであなたに会うのは今日が最初で最後なんだから。」
僕にはこれも意味のわからない言葉だった。
「七夕の夜だからキスしてくれたのですか?」
「七夕には来年があるけど、私たちにはきっと来年はない。私、誰とも将来の約束をしないことに決めている。あなたのこと、白状するとずっと好きだった。だからその気持ちを空の果てまで昇らせたいの。分かるかしらこういう気持ち? 地べたに這いつくばってずっとうじうじ、好きなんじゃなくて、まっすぐ飛んでいくロケットみたいに今ここでどこまでも打ち上げたいって気持ち。好きだという気持ちをきれいに今夜燃やして、七夕の空の上に昇らせてあげたいの。どこまでも高く遠く未来永劫ずっと。その一回きりの儀式につきあってほしい。」
「一回きりの儀式?」
「ええ、一回きりの儀式。」
「今の僕は君のあこがれた刑事の僕じゃないけど。それに離婚もしてるし。」
「離婚をしたから今は自由だって言いたいの?」
「いや、そういう意味じゃなくて。ただ、自分には自信がないのです、女性と向き合うというか、心も体も裸になってしまうということ自体が、うまくできるかどうか、自信がないのです。」
彼女は微笑みながら首をふった。
「心も体も裸になれるなんて、最高な気分じゃない?」
そしてまた唇を重ねてきた。今度は息がきれるくらいの丁寧なキスだった。僕はこみ上げてくる気持ちにあえぎながら分かりました、その儀式につきあいますと答えた。
「ありがとう。分かってくれて。それに、来年こうして会える保障なんて誰にもないわけだし。」
静かな夜だった。彼女はなんだか少し寂しそうに微笑みながら僕を見つめている。
「あの、おなかすいていない?」
言ったあとで後悔したが、後の祭りだった。
「ねえタカ、わたしたち、今することは他にあるのじゃなかったかしら?」
| 三辻 孝明(みつじたかあき) 「CUBE IT AUSTRALIA」のCEO(最高経営責任者)。早稲田大学人間科学部環境科学科卒業。1989年より豪州在住。2020年8月10日永眠。 |
【関連記事】
関連記事:【新型コロナウイルス関連】日豪物流業界のパイオニア。死と向き合い、激動のパンデミックの中を生きる。
関連記事:ドロップアウトの達人
関連記事:Madison






