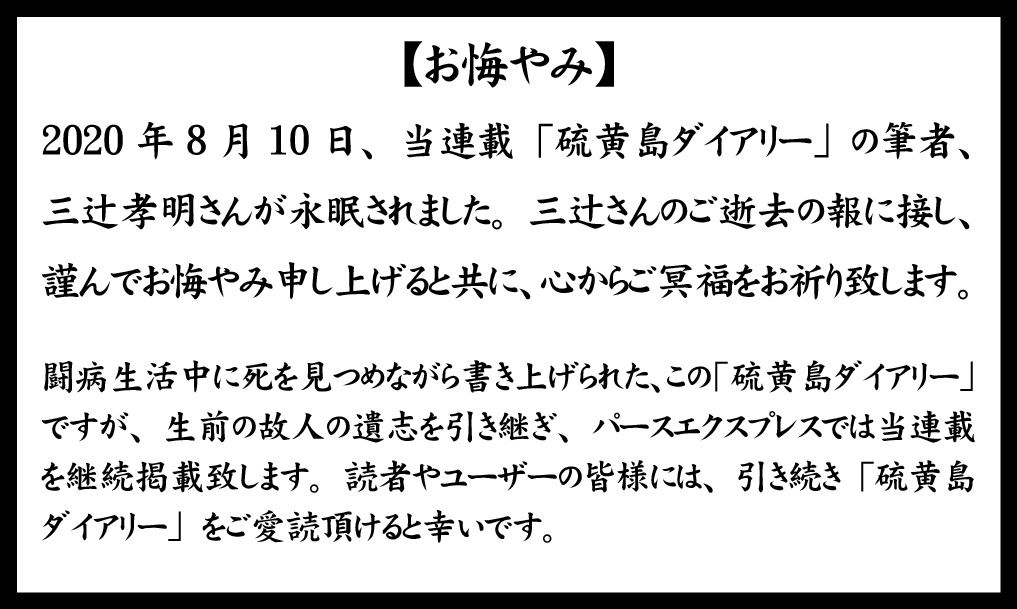
筆者三辻孝明さんは、昨年の2019年8月に癌の告知を受けました。三辻さんは以後、自然療法や抗癌剤治療を経て、癌の摘出手術を受けた10ヶ月間、「静かに死を見つめながら、久しぶりに文章を残すことができました」と話しています。そして「レポートに毛の生えたようなものですが、過去の自分自身の経験を形にできたことは少し肩の荷が降りたような気持ちです。よろしければ、ご一読ください」と生前に語っていました。
<第二章『ROSEMARY & SHARON』4話はこちらから>

【連載小説】
硫黄島ダイアリー
三辻孝明
第二章『ROSEMARY & SHARON』5話
マリオがレモンを入れたミネラルウオーターを私の前におく。彼はスキンヘッドで背が高く、この店のボデイガードの役割も担っている。鍛えた敏捷な体をしていた。彼はバレーボールのセッターだった。しかも、全日本の。たまに彼のことを憶えているお客さんが来て、そういう時はバレーボールの話で盛り上がる。たぶん元全日本のセッターも本当のことなのだろう。40は過ぎていると思うが、今でも垂直跳びなら1m近くは飛べると言うのが彼の口癖だった。もちろんマリオという名も本名ではない。マリオにはフィリピンのミンダナオ島に仕送りをしている妻子がいる。今はビザの問題で別居しなければならないらしかった。
その日、マリオは機嫌が悪かった。私が声をかけても彼は上の空だった。
「What’s the matter with you?」
「どうもしないよ。それよりシャロン、持ち合わせがないんだ。少し都合してくれないかな。」
「別にかまわないけど、すぐに必要?」
「できれば今日中に。」
クラブの場所は六本木から霞町に向かった左側の、大通りから一本入った裏通りにある3階建てのビルの1階だった。20人も入れば満員になる小さな店だったけれども、ホステスを全員外国人でそろえていたことが人気を呼んで、クラブは盛況だった。ローズはその中で人気のあるホステスではなかった。指名するお客さんもほとんどいなかった。私はマリオが活けるゆりの花を眺めながら、ひとりの男のことを考えていた。その男が最後にクラブに来たのは、1ヶ月くらい前だったように思う。歳は40くらいで、日に焼けていた。そう頻繁に来る客ではなかったが、来るときはいつも独りだった。そしてローズを横において、カウンターでバーボンを飲むと帰っていった。
その晩のクラブは1時過ぎに終わった。夕方から降り出した雨のせいで客の少ない日だった。私はタクシーの拾える大通りに向かって、モンスーンのような夜の街を歩いていた。信号の手前に白いセダンが止まっている。それは10時前に早引きしたはずのマリオの車だった。
「今頃だとタクシーは拾えない。送っていくよ。」
マリオは長い腕を伸ばして、助手席のドアを開けた。私は迷った。お金を貸してほしいと言うマリオの話を信じるつもりは初めからなかった。すでにローズマリーが事件にあってから3週間が過ぎようとしている。このままひとりで壁に向かっていても何もつかめないことに正直私はあせっていた。
「どうする?乗る?それとも歩いて帰る?」
私たちのやりとりを後ろで見ていた数台の車がついにじれて、けたたましくクラクションを鳴らし始めている。私はその音に背中を押されるように、セダンの助手席に体を滑り込ませてしまった。白いセダンは霞町の交差点を左に曲がり、広尾に向かって地中海通りをスピードを上げながら走り始める。
「ローズマリーからの連絡は?」
「ないわ。」
私は嘘をついた。ローズのことをクラブの用心棒に話すわけにはいかなかったからだ。セダンが広尾タワーズのある交差点の赤信号で止まる。隣のマリオはバックミラーを見たまま、動きを止めている。
「つけられている。」
私はふとあの日、ローズが何回も殴られたことを思い出した。信号が青に変わる。車は天現寺の交差点を左に曲がる。そのまま行くと慶応大学と、私の部屋のある三田に出る。私を部屋まで送っていくつもりなのだろうか?道は緩やかにカーブしている。マリオはカーブに向かってアクセルを踏み、セダンが後続の車の視界から消えるまで十分引き離してから、Uターンして反対車線に車をまわした。そして、左側の路側帯に車を止め素早くライトを消した。カーブを曲がって現れた車の群れが四の橋方向に通り過ぎていく。最後の一台が走り去るのを見届けてから、彼は天現寺の交差点に向けて来た道を戻り始めた。
「どういうことなの?」
「もしかしたら、思い過ごしかもしれない。」
「つけられていることが?」
「ああ、気のせいだといいんだけど。」
「私に関係のある話なのね?」
マリオはその質問には答えずに思い過ごしかもしれないともう一度繰り返した。セダンはさっき曲がった天現寺の交差点を今度は左に折れた。
「どこに行くつもりなの?お金のことなんて初めから嘘だったんでしょう?」
マリオは返事をしない。黙ったままハンドルを握っている。何かを考えているようだった。白金トンネルに入る。トンネルの中のオレンジ色の光が、緩い左曲がりの向こうから次々に現れては消えていく。
「シャロン、明日も仕事?」
「いいえ、明日は休みだけど。」
トンネルを抜けると左側に自然教育園の黒々とした森が現れる。首都高速の橋げたの下に続く先の信号は、五反田まですべて青だった。
「どうして嘘をつく?」
マリオが口を開く。
「嘘って何のこと?」
「君がそういう態度なら、俺もそれなりの対応になる。」
繰返すが彼はクラブの用心棒だった。そしてあの忌まわしいクラブでさえ働かなければ、ローズマリーがひどい目に遭うこともなかったのだ。セダンはスピードを上げながら夜の街を走り過ぎる。こうして一緒にいること自体が危険なことは十分わかっていた。でも、私には情報が必要だったのだ。
「分かったわ。嘘をついた私が悪かった。あなたの考えている通りローズとは連絡を取り合っている。」
「そうか。」
「でも、どうしてあなたがそのことを知っているの?」
「そのことって?」
「ローズが事件に巻き込まれたってこと。そのことを知っているのは当事者以外では、私だけのはずだけど?」
「い、いや、ただ最近クラブに来ないからどうしてるかと思っただけだよ。」
「あなた、自分が言っていることわかっているの?人を嘘つき呼ばわりしておいて、何か知っているのならちゃんとあなたも話しなさいよ。」
マリオは煙草に火をつけた。それから運転席の窓を少し下げて、そのすき間に煙を吐いた。
「OK、わかった。もしよかったら俺の部屋で話さないか?」
あの日、暗い部屋にしゃがんだままのローズのあざだらけの顔が頭をよぎった。どうしようかと最後にもう一度考えた。
「Trust me」
ここまできたら、彼のつぶやきを信じるしかないのかもしれない。五反田で右折したセダンは、一号線、第二京浜国道に入っていく。戸越銀座通りを左に入り、大崎駅に近いあたりの路地をいくつか曲がってセダンは止まった。
「ここって、どこ?」
「住所は西品川。寄っていく?それとも嫌なら三田の君の部屋までこれから送るけど。」
人通りの無い路地の向こうに、2階建てのアパートメントが見える。
「長くなりそう?」
「かもしれない。」
「コーヒーはある?」
「もちろんある。」
「じゃあ、NON ALCOHOLで話しましょう。」
「OK。」
私は車を降りた。もう後戻りはできなかった。マリオに続いて、半分切れた蛍光灯が点滅する鉄の階段を登っていくだけだった。
******
あの夜のことはよく憶えている。夕方から降り出した雨が、夜半に上がったのに風もなく明け方まで蒸し暑い夜だった。その日は金曜日で、島から戻ってからちょうど1年が過ぎた頃だった。なぜ、そんなことを覚えているのかというと、島に行く前に住んでいたアパートの大家から、部屋の修繕費用の請求が郵便ポストに届いていたからだった。そこには要約すると、このまま支払いを行わない場合、法的措置をとるらしいことが書かれていた。どうやって、僕の新しい住所を調べたのだろうということも不思議だったが、そこに記載されていた金額が払えないものではなかったこともあり、あまり深く考えないまま銀行が開く週明けの月曜日には支払いを済ませようと考えたのだった。だから、その日は金曜日に間違いなかった。
島から戻った僕は、スポーツ新聞に載っていた宅配の運転手の仕事に応募し、今は川崎にあるクロネコヤマトの集配所で働いている。
その日もアパートに戻る途中、いつものように商店街で晩の惣菜を買った。部屋に戻り、ひとりで夕飯を食べていたら、あまりこうゆうことは書きたくないのだけれども、涙が止まらなくなってしまった。涙の理由は、多分あの島で何かを掴んで戻ってきたはずなのに、ここで暮らしているうちにその何かを忘れてしまい、自分自身を情けないと嘆く気持ちと、これでは島の人たちにも会わす顔がないという気持ちが合わさって、それが言い訳のように涙になって流れているのだった。“島の土の中に息をひそめる都市を、この狂った東京に持ち込むのです。その時、本当の審判が下る”と予言していた山中さんの言葉ではないけれども、これでは自分は初めからできない役をもらってしまった役者のようなものだった。結局、この1年の間、何も新しい人生に踏み出したようなことは起きなかったし、そんな自分の様子に失望したのか、島から持ち帰ったキヨシ少年も、あれ以来一度も姿を現してはいない。
それでも時間は、東京に戻ってからのこの1年のように容赦なく残酷に停滞する。島に戻りたいと思い、三浦興行に連絡してみたのも一度や二度ではなかった。けれども、三浦興行の方でもあの島でしか働けない人のための優先順位があるようで、何回問い質しても今は求人をしていないという返事が返ってくるだけだった。斉藤も山中さんも珍蔵もひろしも、ずいぶん遠くの人になってしまった気がした。
そればかりか、あれから1年も経つというのに僕には相変わらずガールフレンドも職場以外で口を聞く人もいないのだった。正直に白状すると内地に戻ってきてから、自分にはハイな瞬間なんて全くと言っていいほど訪れなかった。それなのに、落ち込む瞬間は頻繁に必ずやってきてしまう。こんな風にありとあらゆることで落ち込める自分は、もしかしたら落ち込みの天才なのかもしれなかった、あるいは自分はまだ病気なのかもしれない。だから一人でいる時に限って涙を流してしまうのかもしれない。
僕は考えのないままにアパートの部屋を出ると表の鉄階段を降りて、雨の中を近くのサウナに向かった。そして、そこで知らない男たちと肩を並べながら、プロ野球を見て時間をつぶした。金曜日の夜にサウナに来ている男たちには、独特のにおいがあるような気がする。硫黄島ほどではないけれども、何か世の中から外れてしまって吹き溜まっているにおいをサウナに来ている男たちは大なり小なり身に着けている。時間をつぶしているうちに野球中継もニュース番組も終わり、夜も更けてサウナの中には僕以外誰もいなくなってしまった。表に出るとまだ雨はじとじとと降っていた。
ルーザーという言葉が、このところずっと頭の中を回っている。途中で缶ビールを半ダース買って部屋に戻った。そして考えのないままビールを続けて飲むうちに、いつのまにか眠ってしまったらしかった。
時計を見ると午前3時を少し過ぎている。窓を開け放しにしていたため、蚊の羽音で眠りを邪魔されて目が覚めた。その時、隣の部屋から確かにもの音が聞こえた。男の怒鳴るような声に続いて、何かが強く壁にぶつかる音がしたのだ。聞き耳を立てていると女の叫ぶような声が続いた。隣の部屋には体格のいい男が一人で住んでいるはずだった。夜の商売をしていて深夜でないと帰ってこない男と、朝の早い仕事の自分が言葉を交わす機会はそれまでに一度もなかったけれども、男は以前テレビで観たことのあるバレーボールの選手に似ていた。
よりによってこんな日に、隣は何をしているんだ。僕はスニーカーをつっかけて廊下に出ると、隣の部屋のドアの前に立った。そして次の瞬間、自分でも驚くくらい力強くドアを叩き始めていた。島を離れて以来の平凡な日々への鬱憤がドアに向かって爆発したような感じだった。一度火がつくと、何だか気持ち良いような気分になってしまい、度胸も据わってきてドアを叩くことを抑えることはもうできなかった。僕はそのまま機械のように無言のまま、隣の部屋のドアを叩き続けた。
「夜中に何してるんだ、この野郎!」
気がつくと部屋の中から男の怒鳴り声がしている。
「警察だ、開けろ。」
僕は面白くなってきたぞと思った。いたずら半分にビールの勢いでそんなことまで口走っていた。その時、急にドアが開いた。と同時に部屋の中にいた男が飛び出してきた。僕は身構える間もないまま、まともに男のタックルをくらってしまい、背中から廊下に叩きつけられた。瞬間、腰のあたりを強打した痛みで息ができなくなる。男はその隙に階段を下り、路地に出ると表通りの方へ走り去っていった。しばらくして、息ができるようになるのを待って部屋に入ると白人の女性が玄関脇のキッチンにしゃがみこんでいた。衣服は乱れていたけれども、怪我はないように見えた。
「POLICE?HOSPITAL?」
問いかける自分に彼女は大丈夫です、とはっきりとした日本語で答えた。そして彼女は奥の部屋の方に視線を向けた。僕はスニーカーを脱ぎ、玄関のたたきの上に揃えてから部屋に上った。奥の寝室に入るとダブルベッドがひとつ置かれていた。正面の窓は開いたままだった。南の島を思わせる原色のカーテンがゆれている。窓に近づき下を覗いてみたが、暗い通りが見えるだけで人の気配はなかった。
いつの間にか雨は上がっているようだった。窓を離れ寝室からキッチンに戻ると、今度はさっきの白人の女性がいなくなっていた。なんだか悪い夢でも見ている感じだった。一応、階段を下りて通りに出てみたが、深夜ということもあり人影はどこにも見えなかった。僕は階段を戻り、スキンヘッドの部屋のドアを閉め、そのまま自分の部屋に戻って鍵をかけた。もしかしたら大きい物音が続いていたこともあり、誰かが警察に連絡したのかもしれないとしばらく様子をうかがってみたが、人が来る気配はなかった。こんな程度のことは事件にもならないのか、さすがに東京だなと思った。
幻を見たような不思議な出来事だった。それが金曜日から土曜日の未明にかけての、今も自分が覚えている全てだった。
| 三辻 孝明(みつじたかあき) 「CUBE IT AUSTRALIA」のCEO(最高経営責任者)。早稲田大学人間科学部環境科学科卒業。1989年より豪州在住。2020年8月10日永眠。 |
【関連記事】
関連記事:【新型コロナウイルス関連】日豪物流業界のパイオニア。死と向き合い、激動のパンデミックの中を生きる。
関連記事:ドロップアウトの達人
関連記事:Madison






