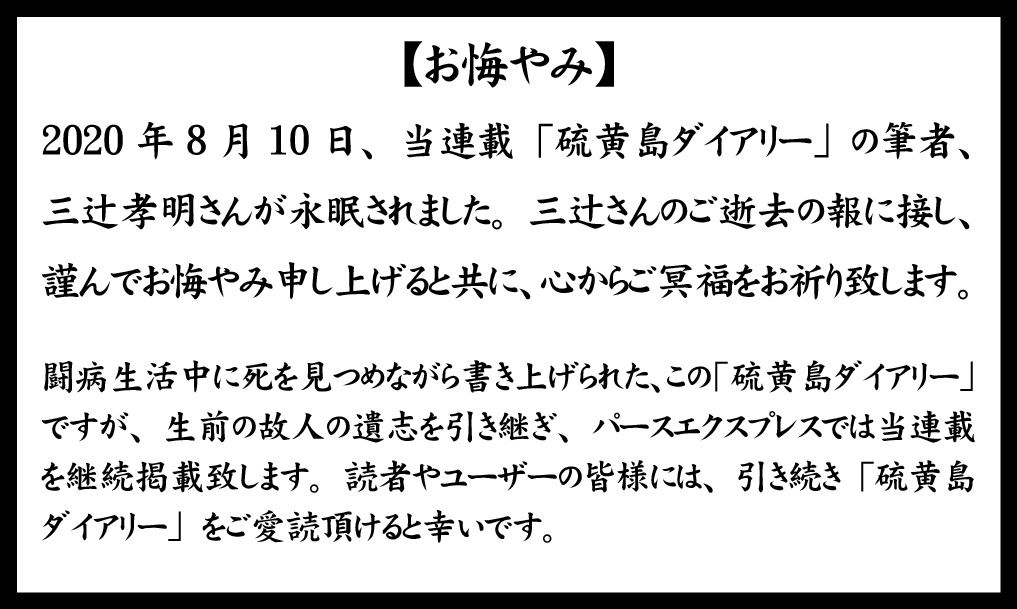
筆者三辻孝明さんは、昨年の2019年8月に癌の告知を受けました。三辻さんは以後、自然療法や抗癌剤治療を経て、癌の摘出手術を受けた10ヶ月間、「静かに死を見つめながら、久しぶりに文章を残すことができました」と話しています。そして「レポートに毛の生えたようなものですが、過去の自分自身の経験を形にできたことは少し肩の荷が降りたような気持ちです。よろしければ、ご一読ください」と生前に語っていました。
<第一章『硫黄島』6話はこちらから>

【連載小説】
硫黄島ダイアリー
三辻孝明
第二章『ROSEMARY & SHARON』1話
表はよろこび
裏はかなしみ
ときどき不思議なコインが落ちている
危ないから、おとなは絶対ひろわない
それでもわたしは手を伸ばす
そして手の中で輝き始めたコインに、私は未来をかけてみる
ローズマリータウンゼントはいつものように自転車で麻布にある国際学級に向かっている。彼女の住んでいる品川区長者丸から港区南麻布までは、自転車だと15分はかからない。彼女が初めて日本に来た日も、ちょうど今日のように底冷えのする晴れた日だった。来日した理由は、大学で少数民族のエスノヒストリーを専攻していたことで、卒業を前に一度アジアを旅してみたいと考えていたことと、東京のオーストラリア大使館にシャロン・ワイズブロットが勤めていたからだった。
「ローズ!」
2年前のその日、成田空港でシャロンに声をかけられた時、彼女は新しい運命に足を踏みいれようとしていた。
彼女は22歳で、アジアでの旅を終えたらシドニーに戻り、大学院修士課程への道に進むことを決めていた。将来の夢は静かに机に向かいながら自分の研究を進める日々を得ることだった。ローズマリーは模範的な学生だった。彼女は高校を卒業するまでの13年間を教会の施設で暮らしていた。
ローズマリーの母親は彼女を産んだ翌々年に、出産の際の出血が原因で亡くなり、当時航空機の技術者だった父と、2歳になったばかりの彼女だけが残されたのだった。父はもともとはロンドンに生まれロンドンに育った生粋のイギリス人だった。その父ジョンが、なぜ大戦前にイギリス中から集められた子どもたちといっしょにオーストラリアに連れて来られたのかは、後にイギリス政府の強制児童移民政策が暴露され、小説や映画を通して世界中を震撼させたことで公になるのだが、幼かった当時のジョンに事実を知る術はなかった。
初め、ロンドン郊外のティルバリーを出港した船は“オーストリア”に向かうらしいと、噂されていた。けれども航海は2ヶ月にも及び、途中ケープタウン、シンガポールに帰港する頃になると、目的地は“オーストリア”ではなく“オーストラリア”に違いないということが、無理やり船に乗せられた子どもたちにもわかってきた。まだ8歳だったジョンは、2ヶ月の航海の間に誕生日を向かえ、その祝いに船の乗組員からナイフをプレゼントされている。当時は、ナイフを持つことが少年から大人になるシンボルとされていたからだ。プレゼントをもらって以来、ジョンは船の柱に自分の名前を刻んでいく。
曰く、「ジョン・タウンゼント、確かにここにあり」
その時のジョンは、すでにもう生きてロンドンに帰れるとは思っていなかった。いくら貧困だからといって、どうして両親が三男の自分を捨てることを選んだのか、そのことが本当に悲しかったし、到底理解できるものではなかった。この先の人生、何が待っているのかわからない8歳の彼にとって、だからせめても、自分の生きていた証を船の柱に刻みたかったに違いなかった。そして、こんな風に自分たちを騙して、地球の果ての国に捨てるようなことを決めた両親を含めた大人たちを生涯を通して彼は心底憎むようになったのである。
ティルバリーを出港して10週間後、“オーストラリア”に上陸した子どもたちは、100以上のグループに分けられ、一次産業を支える労働力としてそれぞれの受け入れ先に、家畜のように運ばれて行った。ジョンは、シドニー郊外のピクトンという村の共同農場に、他の8人の子どもとともに運ばれ、着いたその日から大人たちに混じって朝から暗くなるまで、厳しい農作業に従事していった。ピクトンに送られた子どもたちの全員が、この国での身寄りがなく、騙されて連れて来られた状況を誰に相談することもできなかった。そして、シマウマのように群れて固まり、長い苦渋の年月を経て、それぞれが成人する日を迎えたのだった。
成人し、農場を巣立ったジョンは、後にエンジニアの資格を取得する。そして、ローズマリーの母になるジャッキーと出会うのだった。
ジャッキー・マクドエルは、シドニー生まれのオーストラリア人だが、彼女の両親はダブリン出身のアイルランド人だった。アイリッシュは大家族が多く、ジャッキーも四人の姉妹と三人の兄に囲まれ、貧しいけれども愛情豊かな環境の中で思春期を過ごしていた。ジョンとジャッキーがどこで知り合い、どうして付き合うようになったのかをローズマリーは知らない。けれどもふたりは1958年には一緒に暮らすようになり、そして翌年、ローズマリーが産まれ、続いて次の子どもの出産をする途中に、ジャッキーは帰らぬ人となったのである。
ジョンは生い立ちから不遇が続き、愛情の薄い思春期を過ごし、絶えず孤独の影に怯え、幼少から自立して生きていかねばならなかった境遇から心を閉ざした極めて難しい青年であった。一方で聡明だったジョンは、肉体労働の後の僅かな時間を机に向かい、独学で航空技師の資格を習得した。そしてその資格を得て、カンタス航空に就職が決まった時、ジョンは知り合って日の浅いジャッキーに求婚をしたのである。ただし、ジャッキーとジョンとの交際は初めから順調だったわけではなかった。イギリス本国のアングロサクソンをルーツとするジョンと、アイリッシュをルーツとするジャッキーとの間には、同じ白人同士でありながら当時、今では考えられない差別が存在していた。
それとジョンの性格だった。ジョンは人前に出ることが苦手で、ジャッキーの家に招かれ、たくさんの兄弟姉妹に好奇の目で見られることが耐えられなかった。ジョンは、だからジャッキーにだけ蚊の鳴くような声で話しかけた。そして周りの一切を無視しているようなその行為が、絆の強いアイルランド人の家庭に拒否されるようになっていくのに、そう時間はかからなかった。だから、ふたりの結婚は駆け落ちに近かった。ジャッキーは、けれどもジョンを愛していた。なぜならジョンはハンサムだったし、聡明で、そして何よりも世界中で自分にだけ心を開いてくれる男性だったからである。
ふたりはシドニーの西、セブンヒルズにある住宅地に居を構えた。寝室が2つの小さい家だったが、庭が広く家庭菜園が趣味のジャッキーにはうれしかった。それと、家には暖炉があった。週末にワインを飲みながら暖炉の火を眺める喜びを若いジョンが知ったのもこの頃のことだったに違いない。
1959年にローズマリーが生まれると、冷えていたジャッキーの実家との関係も雪が解けるように良い方に向かっていった。当時、母方の兄弟の一人が、北の海岸沿いの町ノースヘイブンに大きな牧場を構えていた。ローズマリーの記憶にはないけれども、自分がジャッキーに抱かれて子馬に乗っている写真が残っている。しかし、ジョンとジャッキーの幸せは、そう長くは続かなかった。先にも書いたとおり、ジャッキーは2度目の出産の際、難産による大量の出血がもとで母子ともに落命してしまったのである。
2番目の子どもの出産に際して、母方の勧める専門の病院を拒否して、地元の市民病院を選んだのはジョンの判断だった。ジョンにしてみれば、自立心の強い彼にとって人に頼らない選択は自然なことでもあった。けれども、自分たちの好意を否定され、頑迷に己の信じる道だけを歩こうとするジョンの姿勢が、母方の唯でさえ家族の絆の強いアイリッシュに受け入れられたとは思えない。もともと体の丈夫でなかったジャッキーを心配しての専門医の手配が、拒否されたばかりか、かけがえのない娘を、妹を、失った家族の悲しみは計り知れなかった。必然、ジャッキーの死後、母方の人たちとジョンとの間に修復不能な溝ができてしまう。
当時のパラマッタ郊外の市民病院は、市内の私立病院とは比べようがないほどの粗末な設備であった。それが分かっていて、粗末な病院の方を選んだジョンを母方の人たちは、まるで殺人者のように呪うようになった。ジョンはジョンで、もともと口数の少ない性格の上に唯一の理解者だったジャッキーを失い、しかも幼いローズマリーとふたりきりになって、もうそれどころではなかった。妻を失った絶望を乗り越える術もなく、ジャッキーの家族から逃げるようにブラックタウン周辺に転居を繰返すうち、やがて彼は酒を飲んで正体をなくすようになってしまったのである。
ローズマリーは5歳の時に役所の職員に連れられて、ブラックタウンの施設に入っている。それ以来、高校を卒業するまで彼女はその教会の施設から学校に通うことになる。当時の教会もやはり今とは比べものにならないくらい貧しかったから、彼女は6年の間、同い年の女の子とシングルベッドをシェアしなければならなかった。そして、その子のおねしょには、ほんとうに苦労させられた。毎朝、明け方近くになると、決まってふとんの中に“お湯”が広がるのだ。それが小学校を卒業するまでの間、ほとんど毎晩続いた。その女の子にも身寄りはなく、無口で引きこもりがちだったこともあって、ローズマリーは、彼女に文句を言うことができなかった。教会のシスターの話によると、彼女は棄てられる前にやはりアルコール中毒だった父親から虐待を繰り返し受けていたのだそうだ。そのトラウマから、意識が一番遠くなる明け方の深い睡眠の中で、失禁を繰り返してしまうということだった。だからローズマリーはせめても、明け方近くに目が覚めた時には、彼女を起こしていっしょにトイレに行くようにした。晴れた日の施設の庭には、決まって彼女たちのマットレスが干されていた。そして雨が続く季節になると、シーツのしたに青いビニールのマットを敷いて寝かされた。雨の中ではマットを乾かすことができなかったからだ。ハイクスクール、日本でいう中学校に上がる年になって、初めてローズマリーに自分専用のベッドが与えられた。最初の夜ひとりで手足を伸ばして朝まで眠ったときの開放感を、彼女は忘れない。自分が将来どんな大人になるのかなんてわからなかったけれども、あの日、このベッドだけは手放さないと、強く思ったことをおぼえている。
ハイスクールでの成績は優秀だった。普通の家から通って来る他の子どもたちと違って、良い成績を残すことだけが学校での自分の立場を守ってくれると施設から通う彼女は信じていた。初めて恋をしたのは高校2年の時だった。相手は一学年上の、同じ水泳部のキャプテンだった。彼は裕福な家の一人息子で家には大きなガレージがあり、その2階がロフトになっていた。ふたりは、親の目を盗んではそのロフトでの逢瀬に没頭するようになった。今振り返っても、彼女の方が彼に夢中になっていた。けれども彼の両親は彼女を歓迎してはいなかった。
やがて彼は、ニューキャッスル大学に進学し、その日を境に連絡が取れなくなってしまう。その時、ローズマリーは17歳でオーストラリアでいう12年生、日本の高校3年生になっていた。考えてみれば、施設から高校に通う身寄りのない女の子と、ビスケットの会社を所有している裕福な家の息子では、はじめからバランスが取れるわけがなかった。でも、ローズマリーにとって彼は、初めての肉親と呼んでいいような、唯一自分を見せることのできる存在だった。肉親を奪われた彼女の中に、彼への強い執着が生まれた。そして、それは気持ちの上だけのことでは済まなかった。気がつくと、彼女の体が麻薬患者のように彼を求めてしまうのだ。眠りの浅い、まくらを両足の間にきつく挟んで眠るような悶々とした夜が続いた。そして、それが彼女を繰り返し求めた水泳部のキャプテンが残していった足跡だと気づくのに、そう時間はかからなかった。
ローズマリーは以前にもましてその12年生の1年間を机に向かって過ごすようになった。希望通り奨学金を得て彼と同じ大学への進学を果たしたのは、その年の終わりのことである。そしてその進学した大学で彼女を待っていたのは2年先輩のシャロン・ワイズブロットだったのだ。
| 三辻 孝明(みつじたかあき) 「CUBE IT AUSTRALIA」のCEO(最高経営責任者)。早稲田大学人間科学部環境科学科卒業。1989年より豪州在住。2020年8月10日永眠。 |
【関連記事】
関連記事:【新型コロナウイルス関連】日豪物流業界のパイオニア。死と向き合い、激動のパンデミックの中を生きる。
関連記事:ドロップアウトの達人
関連記事:Madison






