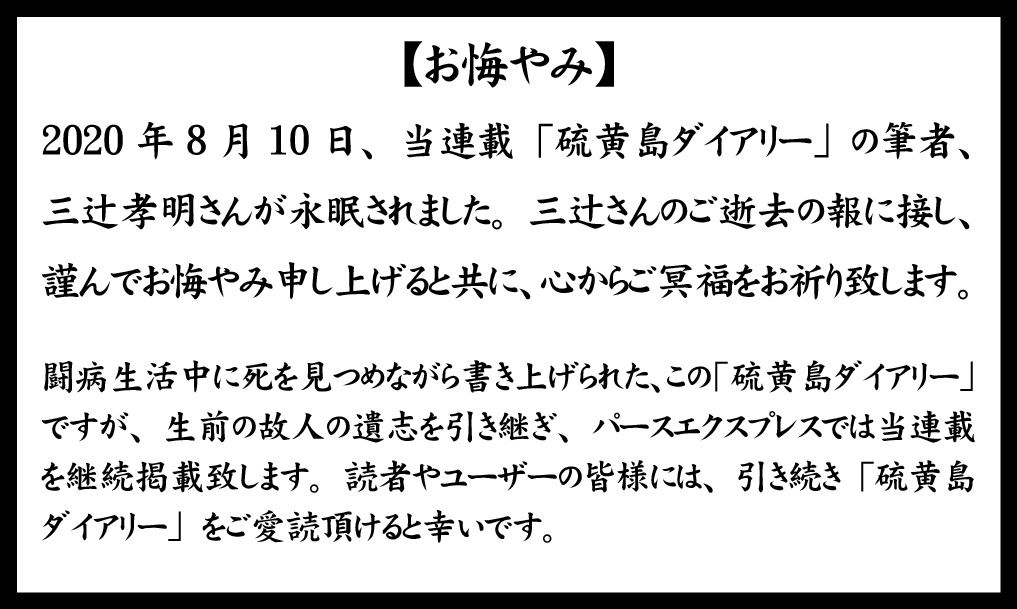
筆者三辻孝明さんは、昨年の2019年8月に癌の告知を受けました。三辻さんは以後、自然療法や抗癌剤治療を経て、癌の摘出手術を受けた10ヶ月間、「静かに死を見つめながら、久しぶりに文章を残すことができました」と話しています。そして「レポートに毛の生えたようなものですが、過去の自分自身の経験を形にできたことは少し肩の荷が降りたような気持ちです。よろしければ、ご一読ください」と生前に語っていました。
<第一章『硫黄島』5話はこちらから>

【連載小説】
硫黄島ダイアリー
三辻孝明
第一章『硫黄島』6話
暗闇に強いカビのに匂いがしている。その匂いの中にあの少年兵が立っている。
「行きましょう!」
迷っている自分の上に、有無を言わさぬ少年の声が聞こえる。その晩、少年が向った先は宿舎近くの近づいてはいけないと言われている地下壕だった。
少年は背をまるくして鍾乳洞のような洞窟を降りて行く。外の爆発が中までストレートに貫通しないよう右左に蛇行して掘られた洞窟の中は、奥へ進むほどに自分の手も見えないほどの濃い闇となり、その闇の中で不思議なことに自分には少年だけが見えている。突然、遠くで花火を打ち上げるようなお腹に響く音が始まる。何の音なのだろう?頭上の洞窟の入り口の方で炎が上がる。その火柱で洞窟の中の闇が飛び、僕は少年と自分自身を確かめることが出来る。さっき建設会社の宿舎を作業着で出たはずの僕は、いつの間にかUS NAVYと胸に書かれた迷彩色の戦闘服に身を包んでいる。頭には頑丈なステンレスのヘルメットを冠って、Red Crossの描かれたショルダーバッグを右肩に抱えている。おびえた目で僕を見る目の前の少年は日本軍の兵隊に違いなかった。その時の自分がどうしてそんな風に考え始めたのか、本当にわからなかった。僕は少年を知っていたのではないのか?彼は2回も僕に手紙を書いてくれていたし、一緒に連れ立って建設会社の建物からこの洞窟までやって来たのではないのか?僕の目は、改めて少年を見る。彼のまわりに銃やライフルのような武器は何も見当たらない。粗末な通信用の機械と袋を抱えているだけのようだ。何かが自分の中で入れ替わり始めていおる。いや、僕に新しい何かが入り込もうとしてる。
「Are you OK?」
僕がそのことばを口にしたとたん、記憶に刻まれていたはずの少年が完全に失われた。自分が日本語で話したつもりの言葉はすでに英語だった。衛生兵の僕は、今生まれて初めて本物の日本兵と向き合っていた。幼い感じのする目の前の日本兵はけがをしている。具体的には右足のくるぶしから下が無くなっていた。止血をするためなのだろう、ひざの下を汚れた布で縛り上げている。僕は消毒液と止血帯を取り出した。バッグの中身はわかっていた。懐中電灯をつけ、痛み止めのモルヒネを打つところから応急手当を始めようとした。日本兵はなにも抵抗をしなかった。座ったままおびえた目をこちらに向けてはいたが、もう歯向かう力も残っていないようだった。
「You alight?」
僕は日本兵を励ましながら手当てを急いだ。思ったよりも出血がひどく、ひざ下をもう一度止血帯を使って縛り上げ、彼を岩の上の平らな場所に移してから腰の水筒を取り出した。日本兵はみな2週間以上水なしで戦っていると上陸用舟艇の中で聞いていたから、水筒のコルクを抜いて日本兵の口に近づけてみた。すると少年はすぐにむさぼるように水を飲み始めた。そして何度もむせながら、水筒の水を飲み干した。
「Yummy?」
僕は日本語でおいしいかと聞いてみたかったが、その言葉が分からなかった。日本兵は初めて僕の目を見た。そして、うなづいた。それは言葉や文化の壁を超えた血の通う素直なしぐさだった。アメリカ海兵隊の衛生兵である自分は、その時に受けた衝撃を忘れない。パールハーバー以来、悪魔の代名詞としてしか考えたことのなかった日本兵に、その時の僕は心を打たれてしまったのだ。僕たちはここでいったい何をしているのだろう。これは、もはや戦闘ではなかった。この島で今起きていることはゲームのような海兵隊によるただの人間狩りだった。相手にはもう弾薬も水もない。それが分かっていて来る日も来る日も僕達は洞窟の中を火炎放射器で焼き払い手榴弾で爆破し、這いずり出て来た日本兵をマシンガンで蜂の巣にして、最後に海水を流し込んでから入り口に蓋をする。その作業が繰り返されるだけなのだ。
確かに上陸した最初の三日間で多くの兵隊を失ったのは事実だった。彼らは南太平洋の島々を転戦したベテランの兵士たちだった。上陸したあの黒い砂浜と左側のすりばち山を制圧するために、6千人近い歴戦の勇士がわずか1日で亡くなり、その倍以上の兵士が手足を吹き飛ばされて、後方の艦船に送り返された。僕たちの怒りは頂点に達し、動くものは全て殺すようにという決意で島の掃討作戦に入っていた。でも目の前の幼い少年が現実を物語っている。もう戦闘はとっくに終わっているのだ。もう何日も弾も何も飛んでこないではないか。僕達は占領した飛行場の滑走路を整備し、もうすぐテニアンやサイパンから輸送機も飛んでくることになっている。
少年が苦しそうな息をしている。懐中電灯で探ってみると右の背中にもけがを負っていることがわかった。銃弾を背中から受けて肩に貫通してしまったらしい。肺にも傷を負っていることが考えられた。ここではもう手のほどこしようがなかった。唯一の方法は、この洞窟から素早く運び出し、野戦病院で本格的な手当てをすることだった。助かるかどうかは分からなかったが、衛生兵としてこのまま少年を置き去りにするわけにはいかなかった。僕は立ち上がると、さっき炎が見えていた洞窟の入り口に向かって歩き出した。そして、その時はじめて少年の声を聞いた。
「ありがとうございます」
少年は渾身の力で上体を起こすと、確かに僕にそう言った。感謝の言葉を口にした感じだった。そして、通信機材の入った袋の中から震える手で本を取り出した。
「Book?」
僕が本を指差しながら聞くと少年はうなずいた。
「What do you want me to do?」
僕にどうして欲しいのだろう?持って行って欲しいのだろうか?僕は少年から本を受け取って、彼に見えるようにショルダーバッグの中にしまった。その様子を見て少年はやっと安心したようだった。それが少年を見た最後になった。
僕たちがいたのは複雑に入り組んだ洞窟の横穴のようだった。だから直接火炎放射器の炎も届かなかった。洞窟を登り、表に出ると僕は海兵隊員を探した。近くで展開中の部隊の中に通信兵を見つけた。そこで野戦病院に連絡を入れ、搬出用のストレッチャーを至急持って来るよう頼んだ。場所はC12マウントタマナから破壊されたゼロの並ぶモトヤマストリップ(飛行場)に向かう、途中にあるC14サウスビレッジ周辺だと伝えた。僕は、洞窟に引き返した。その間20分くらいだったように記憶している。一応、洞窟の中に衛生兵がいるということを知らせるために、入り口に医療用のショルダーバッグを目印として置いておいた。そして、懐中電灯を頼りにまた暗闇の中を降りていった。少年のいる横穴はなかなか見つからなかった。探しているうちに頭上の入り口の方で話し声が聞こえ始めていた。野戦病院から担架が運ばれてくるには少し早い気がして上を見ていると、そのとき安全ピンを抜いた手榴弾がばらばらと雨のように降って来たのだった。
気がつくと島を離れるまでもう残された時間は1日を切っていた。どしゃぶりの雨の中を珍蔵の背中が見え隠れしている。宿舎のある島の反対側、西海岸に鯨があがっているらしい。朝から自衛隊の売店でそのことが話題になっていた。僕は昼前、珍蔵に誘われたのだ。
「なあ、いつか言ったじゃろ、この島にあまり深入りするとろくなことが起きんて。」
四国出身だという珍蔵はこの島に来て初めの日に風呂場で言葉を交わして以来、ずっと優しい。そこにはいつも変わらない彼の不器用なぬくもりがあった。明日の朝にはその珍蔵ともさよならしなくてはいけない。そのことが今の僕には何よりもつらかった。ふたりの向かう千鳥が浜は、米軍の上陸した二ツ根浜の反対にある。
「なんじゃい子クジラか」
元山飛行場のはずれから見下ろすと、確かに黒いまるい背中が小島のように浮き出して見えている。パイプラインにそって左に折れ、沈没船の手前でジープを降りた珍蔵が、潅木の間を砂浜に向かって駆け下りて行く。雨脚は激しさを増し珍蔵を見失いそうになりながら、僕もあとを追う。やがて前を行く珍蔵の足が止まった。珍蔵は目の前の断崖に、行く手を阻まれているようだった。右に沈没船を見る位置で正面の入り江に10mはあろうかと思われる黒々とした鯨が腹を砂に取られたまま打ち上げられている。僕の立っている場所からは距離にして30mくらいだった。
「死んじょる。」
動かない鯨の背を見つめながら珍蔵が叫び始める。
「どうにもならん。」
「死んだら、逝ってしもたら、もうどうにもならんじゃい。」
珍蔵はその言葉を繰り返している。珍蔵の銃弾のような叫び声が、雨粒を突き抜けて砂浜に突き刺さる。すぐ脇の木っ端微塵に破壊されたトーチカの残骸が、赤くさびた鉄の壁越しに入り江を見下ろしている。フードをはずしたままの珍蔵も僕ももうずぶ濡れだった。
「珍蔵さん、潜水士だったって聞きました。」
「おう、ヤクザな稼業よ、桟橋から落ちた車とか飛び込み自殺とか、俺の行くとこ行くとこ死体ばかりよ。」
そう話す珍蔵の声は明るかった。
「なあ、おまえここを出たらどうするつもりじゃい?チャンカー取り戻すんかい?」
僕はその時、半年の間、ほったらかしにしたままのアパートの部屋のことを思い出していた。あの部屋にはもうとっくに誰かが越してきているに違いなかった。小さいくせにサーモスタットのうるさかった冷蔵庫も、引きっぱなしだった布団も、押入れのプラスチックの引き出しに突っ込んでおいたシャツやズボンも、きっと粗大ゴミとして跡形もなく捨てられているに違いなかった。未練があるとしたら、鉄階段の下に置いてきた自転車くらいのものだった。
「いいえ、内地に帰ったらそういうことはもう考えないように、過去にはとらわれないように生きて行くつもりです。そして、彼女の残してくれた思い出も無理に忘れようとしたりせずに、いつか自分から離れていく日まで一緒に生きていこうと思います。やっぱり、自分なんかに残してくれた宝物ですから。そしてたぶん山中さんの言うこの島の都市も、あっちの世界で表現していくことになると思います。」
「ふん、おのれは相変わらず真面目だな。」
あれから月日が過ぎ、一心に刃物を研ぐ必要も、一晩中、眠れない夜をすごすことも、水しか口にしないことも、今の珍蔵には必要なくなっている。その事実が、もうすぐさよならしなければならない自分には、言葉にできないくらいに嬉しかった。
出発の朝は昨日の雨が嘘のように晴れあがった。部屋の入り口で斉藤が“草枕”を持って立っている。たとえ掟を破る事になったとしても、自分に断る理由はもうなかった。黙って本を受け取ると斉藤が体を投げ出すように抱きついてきた。
「さいならギゼンシャ。また会えるよね?」
「ああ、またすぐ戻ってくるよきっと。」
「そうこなくっちゃ。」
この朝の斉藤の少し汗の匂いのするぬくもりは、揚陸艦が横須賀に入港した4日後も、まだ僕のシャツに残っていた。今朝も作業員たちは早くから滑走路拡張工事の現場に向っている。食堂では誰もが無言で箸を動かしていた。彼らの上をあずき色のはえがジュルジュル飛び回っていたのもここに来た日と変らないし、山中さんが独り言のようにギブソンのアフォーダンスについて解説していたことも、それを聞いている珍蔵が“じじい、そりゃ阿波踊りのことじゃろ?”と聞き返していたことも、いつもの朝の景色だった。
二つ根浜では前面のゲートを大きく開いた揚陸艦が船首を浜に突き刺すようにして太いエンジン音を響かせている。ウニモグほか8台の大型車両の揚陸艦への移動作業は、2時間ほどで全てが終了した。自分は揚陸艦薩摩の甲板に立って朝日に輝く硫黄島を眺めていた。島の左端にすりばち山が見える。すりばち山から右に続く二つ根浜の黒い砂丘が見渡せる。その砂山の上に不器用に帽子を振る影が動いている。太っているのが山中さん、真ん中の上半身裸なのが斉藤、そして頭にタオルではちまきをしているランニングシャツが珍蔵さん、3号室のかけがえのない仲間たちだった。
船の揺れが急に激しくなった。船底が砂浜から離れたようだった。薩摩は太いエンジン音を残してだんだんと浜から離れて行こうとしている。自分は今生きてこの島をあとにする、そしてきっともう二度とここに戻ることもできないのだろう、そう思うと僕の心にこれまで想像もしなかった激しい痛みが広がった。
ここから自分に出来ることはこの島に残る彼らの分まで与えられた時間を大切に生きる以外にない。僕は震えだした体をおさえるように手を振って応えた。小さくなって見えなくなっていく3人も砂山の上から手をふり続けている。オフショアの風が吹き始めた。そのなかに少しだけゆで卵の匂いが混じっている。体の震えは激しさを増していく。僕は何かに取り憑かれたように腕を振り続けた。そして、それ以外にはもうすることを思いつかなかった。
| 三辻 孝明(みつじたかあき) 「CUBE IT AUSTRALIA」のCEO(最高経営責任者)。早稲田大学人間科学部環境科学科卒業。1989年より豪州在住。2020年8月10日永眠。 |
【関連記事】
関連記事:【新型コロナウイルス関連】日豪物流業界のパイオニア。死と向き合い、激動のパンデミックの中を生きる。
関連記事:ドロップアウトの達人
関連記事:Madison






