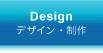|
Vol.192/2014/01
|
「抗いの彷徨(2)」

4×5のカメラで、下宿先の世話焼きおじさんを撮した一枚。シャッターを切るまで我慢強く待ってくれた。
「どうしてこの場所で写真を撮ったのか?」という質問に対して「雰囲気が良いと思ったから」という答えでは意味をなさない。「どうして雰囲気が良いと思った」かを、説明しなければならないのである。「被写体と背景のバランスや光の陰影が気になった」とかである。そこでまた質問される。「どうしてそういうバランスが気になったのか」と。「それは…」と、まるでラッキョウの皮むきのように、延々と答えが出ない。
後で気づいたことだが、それらの問答で重要だったのは、答えを出すことではなく、自分の持つイメージに疑問を持ち続ける、ということであった。
暗室で作業をしていたある時、ある画像が現像液に浸けた印画紙に浮かび上がってきた。そのとき、ああ、こういう写真を撮りたかったのだ、と心底、思ったことがある(たぶん、街角の風景写真だったのだが、実はそのイメージをよく覚えていない)。
そのことをインストラクターに告げると、「ああ、そういうことなんだよ」と納得してくれた。つまり、こういうことだ。ヒトは、20数年も生きてくると、生まれてからこの方、いろんな画像・映像情報に囲まれて育ってくる。その中で、自分でも知らないうちに、あるパターンの映像イメージを頭の中に植え付けられてしまっていく。写真を撮るという行為は、まず、そういったこれまでにでき上がってしまった、無意識の画像イメージのパターンを壊すことから始まるのだ。壊すことができないまでも、自分の頭の中には、知らず知らずのうちに既成の映像が存在している、ということに気づいていることが必要なんだ、と。
そのとき、リセットのスイッチが入った。
写真を撮るという一連の行為から私は、単に机上で学んだ理論ではなく、自分の身体を使い、時間をかけて体得したものがあった。それは他の事柄にも応用できることだ。これら一連の作業は、単に画像や映像に対してだけではなく、自分自身を含めたモノのとらえ方全般を良くも悪くも再評価することであった。いったん、自分自身を壊したのである。
そこで、これまで持っていた、世の中に対する恨み辛みや斜に構えた態度が、少しではあるが、氷解しはじめたのである。そんなことから、自分は写真を通して社会と関わることができるんだ、という次のステップへの足がかりを得ることができた。もちろん、私の場合は写真であったが、そのきっかけは人それぞれによって異なるだろう。
(続く)
〈追記〉ビルマ(ミャンマー)取材が一段落し、もし可能なら、久しぶりにパース訪問を計画しております。できれば2月か3月にでも。
 |