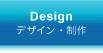|
Vol.192/2014/01
|
「抗いの彷徨(2)」

《4×5(フォー・バイ・ファイブ)カメラ》はこんな形をしている。昔を知っている人なら、学校などで記念撮影をするとき、写真屋さんが使っているのを見たことがあることだろう〈TOYOFIELD のHPから引用〉。
その一つには、自分をリセットできたことだ。自分の考え方や社会の見方を考え直す機会があったこと。自分の目には、社会をそのように見えていたのが、実は、そのように見るように慣らされていたことに気づいたこと。
それを説明してみたい。
写真学校に入って最初の半年は、4×5(インチ)という大型カメラを使わされた。今みたいに、スマートフォンで気軽にデジタル写真を撮れる時代ではなかった。4×5カメラでは、撮りたい被写体を見つけたら、三脚を立て、カメラを組み立て、手動で露出を測り、特殊なレンズを使ってピント合わせしなければならない。大変な作業である。
また、自分が写真を勉強するために通った学校は、米国東部ボストンであったので、冬は猛烈な寒さである。零下20度近くにもなる。そんなところで、屋外で写真を撮るには、集中力が必要となる。ポートレイトならまだしも、動いている人などを撮ろうとするなら、それこそ大変である。
撮りたい被写体を見つけたら、素早くカメラをセットし、シャッターのレリーズを切る。でないと、凍えてしまうのだ。写し終わったフィルムは、もちろん手で現像する必要がある。フィルムも大きく、文字通り4×5インチ=10センチ×12センチほどの、絵はがき大のフィルムである。現像も大変だ。
フィルムの現像が終わると、フィルムを選んで、実際にどのイメージを写真を焼き付けるかを判断しなければならない。ややこしいことに白黒フィルムは、写った画像が白黒が反転している。最初のうちは、選んだネガフィルムを使うと、一体どういう写真ができ上がってくるのか、皆目見当がつかなかった。やがて、それもトレーニングの中に入っていたのだが、まずはカラーの世界から白黒だけの世界に頭を切り替えることができるようになった。そのうち慣れてくると、白黒の反転した状況で世界を見るようになってきた。反転した白黒(モノクロ)のネガを見続けると、世界の見方がガラリと一変する。
フィルムの現像を終えると、次は暗室に籠もって、現像液に浸けた印画紙に焼き付け作業をしなければならない。薄暗い赤いランプの下、時間をかけて、現像液から自分の撮影したイメージが、徐々にゆっくりと浮かび上がってくるのを静かに待つ。そこで、できあがった写真をインストラクターに批評してもらうのである。だが、初めの頃、インストラクターからは、写真の善し悪しを指摘されるのではない。シビアな質問が返ってくるのだ。
「どうして、この時間に、この位置で、この画角で、このシャッタースピードで写真を撮影したのか」「どうして、被写体の背後の電柱を1/4ではなく1/5ほど画面に入れたのか」「そもそも、どうしてこの被写体を選んだのか」
そういう質問を真に受けて、撮影のためボストンの町を歩くと、「あ、良い感じ」って思っても写真を撮れなくなってしまう。「どうして自分は、この風景を良い、って感じてしまうのか」と考え込んでしまうからである。それでも写真を撮らないと話にならない、無理にでもシャッターを切ることになる。そこで、また、インストラクターからの質問攻めにあうことになる。
。
 |