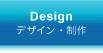|
Vol.188/2013/10
|
“On the Road”『オン・ザ・ロード』

『ビート読本』の【編・役者ノート】から(抜粋) ケルアック、バロウズが共に、自分はビートではないと発言している事実を真に受ける必要はないが、近年のスナイダーのエコロジスト的な活動を見ても、ビルマとかが一つの文学的コンセプトに収斂するものとは考えにくい。年表から表れる彼らの交流の密度から見れば、それはやはり戦後の一世代(ポストウオー・ジェネレーション)が、その出会いと相互影響の内に形成した、短期間の “熱い季節” ではなかったかと思われる。
実は、そう、この連載のタイトルである“On the Road”もこの小説から拝借したものである。自分もこの“On the Road”の登場人物のように生きてみたいと、そして生きてきたと確認するために、このタイトルにこだわっているのだ。
“On the Road”を知るきっかけとなったのは、確か今から30年ほど前、偶然手にした『This(あの佐野元春が企画出版)』という雑誌だった。その中に「ビートニクス特集』というのがあり、そこでジャック・ケルアックやアレン・ギンズバーグなどビートニクスの名前を知ることになった。あの頃の自分は、英語の勉強を兼ね、ビートに関する本を無理に買い、読みあさっていた。
10代から20代にかけて、おそらく誰もが、どう生きるのか、なぜ生きるのか、という疑問を持って毎日を送っているだろう。それは時代や地域を超えた、人として根源的な問いであろう。しかし、自分の考えと社会との間に(人によって強弱はあるが)ズレを感じるのも、また自然なことである。そして、その世間とのズレの殻を破るため、さて、どうすればいいのだろうか、とまた悩むことになる。
酒と異性とドラッグ。
この3点セットに浸ることによって、自分の周りを縛っている形から逃れる術がそこにあると錯覚し、自由を錯覚する米国的な流れもある。特に、米国ではその傾向が顕著であった。私自身、日本の狭さと米国の醸し出す自由という雰囲気にはまっていたため、迂闊にも米国礼賛的な考えであった。
人は、同時進行している今という時代に埋もれてしまって、この今を冷静見ることができない。そのため、自ずと過ぎ去った過去を見てしまう。その過去も、半世紀前ではなく体感できる直前の時代を見てしまう。私の場合、それが60年代から70年代の日本社会であった。日本では高度経済成長が終焉に近づき、それに伴って学生運動も終わりを迎えていた。やがて、日本社会には、抵抗するという姿であるが、閑かな異議申し立てをするヒッピーと呼ばれる人たちが姿を現し始めた。
あの熱い社会はどこにいったんだ、という気持ちが自分の中にくすぶり続けていた。社会に反抗する人や熱い運動が消滅していったように思えた。それだからこそ、ヒッピーの源流の一つにもなった、ビート・ジェネレーションという流れにますます興味を持っていったのだ。
ペンギンブックス版の“On the Road”の裏表紙をめくると、1958年に(22歳の時に初めて)“On the Road”を読み、その翌年再読したという書き込みがある。それ以後、折に触れ、気になる箇所を読み返している。
ケルアック自身は、小説(映画)の中でサルの役で、フィクションの中で自由に生きるディーンはニール・キャサディという実在の人物として登場する。破天荒な生き方をするのは、本当のところケルアックではなく、実はキャサディであった。確かに、ケルアックの生き方は一見すると、無茶苦茶だが、その実は、自分の生き方を冷静に問いかけ続ける性格だった — だから小説を書き続けることができたのだ。
どんなに奔放な生き方を望んだとしても、自分の領分を超えた生き方は実はできないこと。そのことを誰もが知るところとなる。そのことを知ったとき、人は歳を取り始めるのだ。
 |