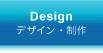|
Vol.188/2013/09
|
ビルマ(ミャンマー)の「ロヒンジャ問題」を手がかりにして(11)—最終回

バングラデシュのクトゥパロン公式難民キャンプで投網の手入れをするロヒンジャの女性(2009年12月)。
ロヒンジャの人びとはその後、時代の変わり目を見定め、自分たちが土着の民族であると主張をすることで、そこにビルマ国内での生活を続ける可能性を見い出していった。私には、ロヒンジャの人びとが自分たちの民族性を強く主張するのは、半世紀に及ぶ軍政下で最も差別され、迫害を受けてきた彼ら彼女たちが取った生存をかけた最期の主張、と思わざるを得ない。それが、彼らに残された生き抜くための唯一で、最後の方法(叫び声)であるように思える。
ビルマ軍政が「民政化」された今、自由にモノをいえる雰囲気が人びとの間に広がっている。ラカイン人やロヒンジャたちの間にはいくつかの組織があり、まさにそこには穏健な人から急進的な人まで様々な人がいるが、声の大きい急進派の主張がもっぱら紹介され、それが争いに拍車をかけてしまっている。血が流れることによって、人びとの憎悪が増幅され、この問題の元々の原因がまったく忘れ去られてしまっているのだ。
ラカイン州で発生し、広がった紛争は表面上、[仏教徒]VS[ムスリム]・[ラカイン人]VS[ロヒンジャ]という、「民族対立」や「宗教紛争」の構図であるが、実はその紛争の背景には、半世紀近く続いたビルマ軍政の政策の負の歴史、ビルマ社会におけるイスラームに対する差別意識、さらにこの紛争を利用して現地の人びとからその土地を奪おうとしている別の勢力が存在している。
昨年4月1日の補欠選挙で国会議員に当選したアウンサンスーチー氏は、「ラカイン州での暴力について、『問題の根源を見ずに片方の肩を持つわけにいかない』と発言、まずは法の支配の確立が必要(VOA)」と述べた。
差別意識は、宗教や民族に限ったものではない。異なる者に対する排外的な意識や感情を抑えるには、今のところ人権思想に基づいた法の支配を目指すしかない。しかし、その道を歩むには、これからもとてつもない犠牲が払われなくてはならないのだろうか。
(終)
この「ロヒンジャ問題」連載の第1回目の最後に、私は次のように書いた。
現地に入った私がまず考えざるを得なかったのは、ビルマにおいて「民族」を考えるとは、すなわち宗教問題や植民値問題などを含めた歴史問題、さらに「お前は何者か」と問うような疑問そのものへの問いかけであった(つまり、どうしてそのような疑問が生まれるのか、という問いかけでもある)。
ロヒンジャの問題を考えていく過程で、この自分自身への問いかけへの答えは、時には表れ時には隠れてしまい、その尻尾を捕まえることがきていないままである。自分に納得がいく答えは、果たして見つかるのだろうか、自問中である。
 |