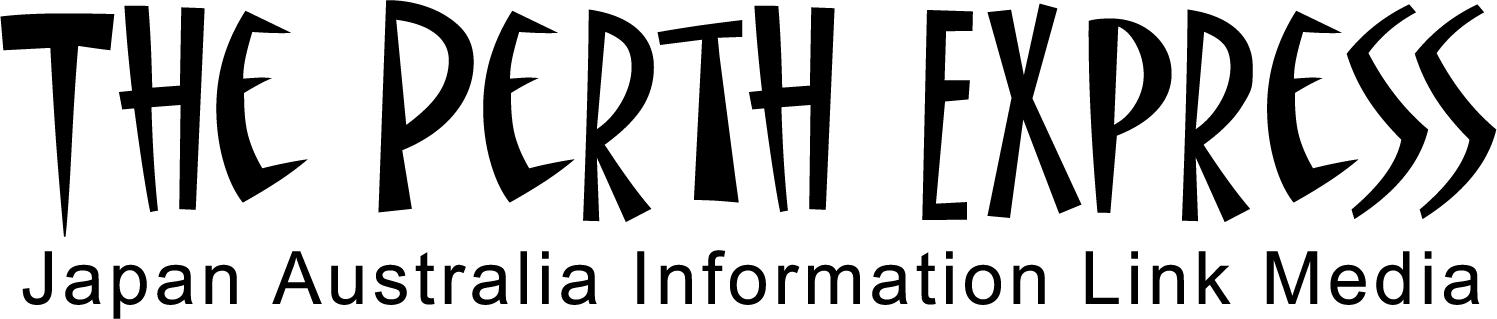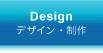|
Vol.179/2012/12
|
「ビルマ(ミャンマー)の「ロヒンジャ問題」を手がかりにして(4)」
呼称変更は地域名にも
だが、地名変更を見てみると、例えば、シャン州の「シポー(Hsipaw)」や「チャイントン(Kyaingtong)」は「ティボー(Thibaw)」や「ケントン(Kengtung)」など、本来はシャン語に近い英語表記からビルマ語読みに変わっている。
〈ビルマ〉から〈ミャンマー〉への英語による国名変更で、ビルマ国内に暮らす諸民族の位置を尊重しようと主張していた当時の軍政の説明は、実は地名の変更をみると無理がある。
また軍政は、国名の英語呼称の変化に伴って次のような変更を行っている。
1988年までビルマは「ビルマ社会主義計画党(BSPP:Burma Socialist Programme Party)」が国を支配していた。軍政はそれまで「ビルマ社会主義計画党」を英語で表す際、“BSPP”と表記していたのが、 これも“MSPP(Myanmar Socialist Programme Party)”と表記するようになった。
軍政は、「史実」としてあった「ビルマ(Burma)」という呼称をすべて「ミャンマー(Myanmar)」に変えることで英語の呼称 〈ビルマ(Burma)〉 という言葉を消し去ろうとしているようである。このような歴史的な表記までさかのぼって変更することは果たして可能なのだろうか。
史実の書き換えである。まるで小説『ビルマの竪琴』を『ミャンマーの竪琴』とするようなものである。
1989年における「ビルマ」から「ミャンマー」への英語の呼称の変更は、同時に史実の書き換えがあり、諸民族の存在を弱めるような変更あったとしたら、その主張─「ビルマはビルマ族だけを指し、ミャンマーは諸民族を含めた言葉である」は受け入れ難いものである。
確かに〈ビルマ〉や〈ミャンマー〉という単語自体に政治的な意味はなかった。ビルマの場合、例えば国名表記の際には、1930年代に、その後1947年、74年、89年と後づけで政治的な意味が歴史的に付与されてきた。
つまり、「〈ビルマ〉と〈ミャンマー〉から〈ビルマ〉か〈ミャンマー〉か」へと位相が変わったのである。
特に89年の英語の呼称変更の後、国名の変更に加えて「史実の書き換え」があった。それゆえ、当時の軍政の主張をそのまま受け入れるのは、ビルマの人であれビルマの人以外であれ、受け入れがたいのである。
    |