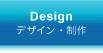Vol.213/2015/10
記憶と記録の交差点(6)—< Room 411 >に暮らして(3・下)
 |
モーモーと知り合って3年後の2004年頃、ホテルを辞めた彼女の行方は分からなくなっていた。が、ある日、彼女から結婚式への招待状が届いた。結婚式で会った彼女は、新しい門出を友人たちに祝ってもらい、幸せそうだった。 |
ワオ、である。
おいおい、冗談じゃない。私は驚きを通り越して、パニックに陥った。そりゃ、荷物の受け渡しで感謝してもらえて嬉しいが、それにしても、これは行き過ぎだ。両手で優しく彼女の肩を掴んで、身を離した。顔を上げたモーモーの目は、私の気のせいかキラキラと輝いている。
こりゃ、ダメだ。
この状況はやばいぞ…。頭の中で警報機がワンワンと鳴り響く。なんとかこの雰囲気を変えなければ。私にはそんな気は毛頭ない。だが、ホテルの部屋に男と女が一緒にいる。しかも、女性スタッフと…。もし、このことがホテルに知れたら大変なことになる。
「こんなことをしちゃあダメだよ」
私は優しい口調で、しかし、はっきりと拒否の意思を込めて対応した。
「さあ、行きなさい。これで全て忘れよう」
そう言って、私は彼女の頬に軽く口づけをした。部屋の扉を開けて顔だけ出し、廊下を見通す。そこに誰もいないことを確認して、彼女を送り出した。
なんとまあ、いやはやだ。これがあのおとなしいビルマ人女性のすることか。私はできる限り長期間ビルマに滞在して、この国の姿を写真で記録すのことが最大の目的である。なので、これは本当に困る。
噂社会のビルマで、「あの外国人は女を部屋に連れ込んでいる」という話が広がれば、とんでもないことになるのだ。ましてや私は、危険な政治的な取材にも関わる立場でもある。彼女がとばっちりを受けたら、それこそ大変だ。
それから数週間後、モーモー再びは、私がバンコクに行く予定があると聞きつけ、サンダーへの荷物運びを頼んできた。今度は直接、私の部屋にその荷物を持ってきた。おいおい、段々と大胆になってくるじゃないか。気のせいか、またまたあどけない様子ながら瞳をキラキラさせている。抱きつきそうになる彼女を押しとどめる。
「もし、君が部屋に出入りしていることがマネージャーに知れたら、私は大変なことになる。ホテルを移らなければならなくなるんだ。荷物は喜んで運ぶから、今後は、部屋に入ってくるのは絶対にダメだよ」
私は、彼女の両肩をつかみ、それ以上近づかないように諭す。
モーモーと2人っきりで話をするのにいちばん好都合なのは、朝食の時である。宿泊客がそれほど多くない日には、仕事が手薄になり、彼女は結構手持ちぶたさになる。荷物を預かった翌朝、パンを焼きながらインスタントコーヒーにお湯を注いでいる彼女に話しかけた。
「早くボーイフレンドを見つけたほうがいいぞ。この間、紹介してあげた日本人の男の子とはどうなったんだ?」
「やっぱり、今の私は学校を終えるのがいちばん大切よね。それから、もっと良い仕事も探さないといけないし。そう、その日本の人から手紙が来たわ。これから返事を書こうと思っている。でもね、あ、次にバンコクに行ったらサンダーに『元気を出して』って伝えてね」
それから半年後、ある日突然、ホテルに彼女の姿が見えなくなった。マネージャーに訊ねると、何でも家の都合で仕事を辞めた、という。モーモーとの出会いはある意味、軍政下での取材という意味で、かなりドキドキさせられた経験だった。