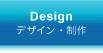Vol.201/2014/10
「抗いの彷徨(9)—下」
西暦でいえば2001年1月1日の夜明け前。遠い記憶を辿るかのように、私は夢うつつの中で迫撃砲の音を聞いた。反射的に時間を確認する。朝5時40分だ。日が昇るまで、まだ1時間半ほどある。果たして、この音は「新世紀」の幕開けの祝砲と呼んでいいのだろうか。
それは、10月半ばから始まる乾季のど真ん中、1年での冷え込みが一番きつい時期だった。35度近い日中の気温は、夜明け前後には5度を下回る日較差となる。何がつらいかといえば、この気温の差である。床についたのは囲炉裏の真横だ。厚手のジャケットを着込み、さらに毛布を2枚重ねた。寒さをしのごうと、火の落ちかけた囲炉裏に身体をすりよせる。竹簀の床「プダ」がギシッと音を立てた。
砲弾の爆発音は10分ほどで止んだ。夜明け前の静寂が戻る。前日となんら変わらない朝を迎え、鶏がけたたましく鳴き始めた。
「20世紀は戦争の世紀だった」
過去形で呼ぶのは、ここでは全く無意味だ。また、「世紀」という枠組みで彼ら、カレン人の存在を捉えるのもおかしい。「新世紀」を迎えたといっても、西暦2001年の夜明けは、カレン歴によると2740年である。とりわけ特筆すべき区切りの年ではない。
「カレン人の土地には、その土地の時間の流れがある」
寝不足と寒さの中、ぼんやりとした頭でそんなことを考える。
昨夜、2000年12月31日の深夜、短波ラジオのダイヤルを回していたら、偶然、NHKの短波放送が入った。ビルマの山奥のゲリラ基地で聴く放送。おのずと耳が敏感になっていた。とぎれとぎれの放送に耳をそばだてていると、どうやら、鴨長明の『方丈記』が流れているようだ。
「ゆく河の流れは絶えずして、しかも、もとの水にあらず。よどみに浮ぶうたかたは、かつ消え、かつ結びて、久しくとゞまりたるためしなし。世中にある、人と栖と、又かくのごとし」
司令部があるカレン人の村は、静かな朝を迎えた。そのあまりののどかさに、自分が戦闘の最前線近くにいることも忘れてしまう。目が覚めると、(司令官の)ボジョーは既に司令部を後にしていた。そうやって、2001年1月1日、21世紀という「新世紀」の日を迎えた。 だが、主(あるじ)のいないKNLA第5旅団での新年の一日は、ただぼんやりと過ごしただけだった。
 |