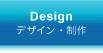Vol.216/2016/01
記者としてのフォトジャーナリスト
こんな文章を読むと、思わず自分の取材力や文章力のつたなさを嘆いてしまう。いったいどうすればいいのか。能力もない自分はいまさら、ジタバタしても仕方がない。そのあたりを高木仁三郎さんの『市民科学者として生きる』を読んで補うしかない。
「実際に問題に直面して解決を迫られた時には、持ち合わせの知識と経験とが総動員される。逆に言えば、その知識と経験が可能にする範囲でしか、問題に対処し得ないのかもしれない」
つまりは自分の能力以上のことは期待できない、という厳しい指摘である。
さらに、40年近く内戦状態が続くアフガニスタンで支援を続ける活動家の中村哲さんは、内村鑑三の『後世への最大遺物』を次のように引用している。
「私たちの生かされたこの世界に、何かお礼を置いて逝きたいというは清らかな欲望である。さて、何を遺すか。先ずカネがある。カネを卑しんではいけない。カネによって善い事業を起こせる。諸君、よろしくカネを作るべし。そこで、或人々にはカネは作れないが、事業を遺すことができる。農業を興し、日本を緑あふれる楽園とせよ。だが、カネも事業も才能に恵まれなければ、文筆を以て精神を遺せる。今できぬ戦を将来に託せる」
こう説き及んだ末に、内村は結論する。「ではカネも、事業も、文筆も、いずれの才にも恵まれぬ場合はどうしたらよいか。ここに誰にもできて、他の誰にも真似できぬ最大の遺物がある。それは、諸君の生き方そのものである。置かれた時と場所で、諸君の生きた軌跡が人々の励ましや慰めとなることである」
要は、自分の記者として生きた軌跡を、それがたとえ拙いものであったとしても、身の丈に応じてまとめるしかないのである。厳しいけれど、それが平々凡々とした自分が向きあうしかない現実なのである。
 |
|
| エルサルバドルの停戦直後に撮影した母と娘(赤ん坊)。この写真は今から16年前、本誌『パースエクスプレス』での連載「On the Road」第一回目(2000年March〜April号)、「いつか再び、喜びの涙を」に使ったものである。 |
自分の記者としての経歴を振り返って見ると、今でも忘れられない一通の手紙が手元にある。今から24年前、当時米国ボストンに住んでいた時、現地で発行する『Boston Note』という日本語情報誌にフォト・ルポルタージュを寄稿することになった。それは、中米の紛争地エルサルバドルから米国ボストンへ向けての取材ルポであった。その連載の一回目の直後、エルサルバドルで取材中の私の元に、編集部経由でボストンの読者から一通の手紙が届いた。その一通の手紙は、読者を勇気づけると同時に書き手の私を大いに勇気づけてくれるものであった。しかも偶然、私の敬愛する千葉敦子氏からの引用があったのも嬉しかった。
その時ぐらいからである、自分にはカッコのよい取材報告はできないなぁ、いつも悪戦苦闘しながら、それこそ地べたを這いずり回りながら得た情報を書き綴っていくしかないのだなぁ、と思い至ったのである。その報告もキチンとした形で完成できなくても、最低限、自分の生きた軌跡を記すことで、その不十分な報告を補ってくれることを信じていくしかない、と。
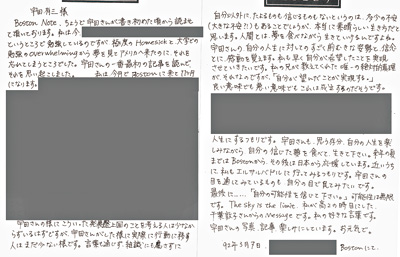 |
個人宛の私信であるが、私の責任において問題がないと思える部分を公開した。 |