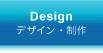|
Vol.167/2011/12
|
第3回 「逆境の中で」 柴田 大輔
 |
黙々と土に向き合う田口さん。決してあきらめない姿がそこにある。 |
茨城県南東部、海沿いに平野が広がる。以前は鹿島郡・行方郡と呼ばれた鹿行(ろっこう)地区だ。土地が広く、大規模な農家が多い。国内でも有数の農産地であり、首都圏の食卓を賄う食糧庫として機能している。
震災後、旧鹿島郡の鉾田市で農業法人を立ち上げた人たちがいる。飯島浩さん(46)と田口英行さん(45)だ。
2人の出会いは高校時代。陸上部の先輩と後輩だった。当時はそれほど親しくなかった。
その後、飯島さんは地元の旅行会社に就職する。就農したのは30歳。不況の中、業界の先行きに不安が募っていた。羽振りのいいメロン農家の知人が眩しく見えた。思い切って脱サラし、農地を借りてメロン栽培を始めた。
信用金庫に就職した田口さんは35才の時、夫人の実家を継いで就農した。農業の経験はなかったが、「自宅に道具は揃ってるし、会社に行く感覚で畑に行ってたよ」と話す。
2人に共通するのは、ある程度年齢を重ね、社会経験を経てから就農したことだ。経営感覚が農業でも重要だと考えていた。共通の価値観が2人を近づけた。
飯島さんはその後、時期の限られるメロンから、年間を通して収穫できるホウレンソウや水菜のハウス栽培へ主軸を移す。人を雇い、規模を拡大する。そこでは、アジアからの外国人研修生が貴重な労働力となる。背景にあるのが、就農者の高齢化・若者の農業離れだ。
田口さんが暮らす地区は、市内でも古い農家が多い。周りを見渡すと、60代70代の農家ばかり。後継者がいないことから廃業する人もいる。自身の体力も年々衰えていく。農業にも競争力が求められる中、農家としての将来に危機感を募らせていた。
新しい方法を模索していた田口さんが、飯島さんに声をかけた。漠然とだが、価値観の近い飯島さんとなら一緒にやれるのではと考えた。それが昨年のことだ。震災は、その矢先の出来事だった。
3月、県内ではホウレンソウに続き、水菜が出荷停止となる。飯島さんは作物の廃棄に追われた。そこに震災前に出荷された野菜が返品されてきた。「なんなんだよ」と吐き捨てるしかなかった。さらに、6人いた外国人研修生のうち5人が、放射能を恐れ帰国した。安全宣言が出た後も、人手不足から作物の生育に収穫が追いつかず、廃棄するしかなかった。
   |