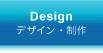Vol.215/2015/12
写真家としてのフォトジャーナリスト
先日、知り合いの雑誌編集者と中堅写真家と3人で会食をする機会があった。今のメディア状況を話し合っていくと、やはり写真をメインに仕事をするのが2人いたため、自ずと話題の中心が写真となっていった。
話が佳境に入ったところで、私はその2人に何気なく聞いてみた。
「それじゃあ、世界で名の知れた、誰か記憶に残る世界的な写真家(フォトグラファー)の名前って、すぐに挙げられますか。いや、厳密に言うとメディア業界には属さない人たちでも知っているような写真家の名前を。そう、3人ぐらい…?」
その質問で一瞬、間が空いた。2人そろって口をつぐみ、その場がシンとなった。思いがけない質問だったのか、両氏ともにすぐに答えを出せなかった。
「例えば、戦争写真家のロバート・キャパとか…」
場を和らげるために私はそう続けた。さらに、数秒の間が空いので、私はダメ押しするように 「(ジェームズ・)ナクトウェイとか、(セバスチャン・)サルガドもいるよね」と。
その場がホッとした空気が流れた。
まあ、ロバート・キャパ(Robert Capa)は別格として、メディアに関わらない人でナクトウェイ(James Nachtwey)やサルガド(Sebastiao Salgado)の名を知っている人とはまずいないであろう。実はこの2人、ドキュメンタリー映画の題材(主人公)にもなっているほど、業界では有名である(『戦場のフォトグラファー ジェームズ・ナクトウェイの世界 』『映画「セバスチャン・サルガド/地球へのラブレター」』。
一方、これが世界的な作家となれば、名前はすぐに挙がるだろう──魯迅、スタインベック、ドストエフスキー、村上春樹などなど。まあ、文字文化には数百年の歴史があり、ノーベル賞に文学賞があるということなど写真とは別格である。
その写真は、150年ほどの歴史しかないし、一般社会でそれほど大きな(強い)影響を与えてこなかったのも事実である。写真を生業としている身として、メディアの位置に占める影響力という点では少々肩身が狭いが、客観的に見てもそれは事実である。写真は、時に冷たい目で見つめ直さねばならない記録(記憶)メディアなのである。
その昔、私自身も米国で本格的に写真を学び始めたとき、ナクトウェイとサルガドの写真を見て、その写真のクオリティに衝撃を受けたのも忘れられない。確かにこの2人は、数え切れないほどの写真家に影響を与えたことだろう。写真を始めた頃、いつかは彼らみたいな写真を撮りたいと思っていた。しかし、この2人の写真の質を、我流であるが、冷静に分析できるようになっていったからだろうか。やがて写真という表現媒体の深みに入るにつれ、なぜかその思いは薄れていった。
 |
「亡命大統領を迎えて」─ハイチから亡命せざるを得なかったアリスティド大統領が米国ボストンを訪れた。ハイチ出身の人びとが彼の訪米を熱狂的に出迎えた(1992年)。 |
 |
|
| 「取引の後で」─中米エルサルバドルの田舎で撮影した市場の風景(1996年)。 |
ナクトウェイは天才である。誰も彼の写真を真似できないであろう。彼は、個人の能力を超えた写真を撮るのである。一方、サルガドはマスター(名人)であろう。スケールが大きく細かな写真を生み出す。才能さえあればサルガドにはなれるであろう。2人とも記憶にも記録にも残る写真を生み出している。もっとも私の目指している写真は、彼らの写真に魅力を感じつつも、この2人とは方向性が異なっているようにも感じていた。ナクトウェイやサルガドに憧れて、彼らと同じような写真を撮りたいと2人を目指す写真家は多い。この2大巨匠の背中を追っかけている写真家は多いが、2人が見ている視線の先を想像している写真家は少ないと思う。もちろん私自身は、逆立ちしてもナクトウェイやサルガドになることはできない。しかし、一体誰だろうか、自分の目指すような写真家とは…。
1990年代始め、写真を学びながら、不安な時を過ごしていた。フリーランスのフォトジャーナリストとして仕事を始めても、その答えは出てこなかった。その間、自分の住処も米国ボストンから日本の神戸に戻り、取材先も中米エルサルバドルやグアテマラから東南アジアのビルマ(ミャンマー)にシフトしていった。
日本の神戸に落ち着いた後も、市内で何度も引っ越しを繰り返していた。その引っ越しの度に不要な荷物を捨てていた時、どうしても捨てることのできなかった写真集を何度も見返すことになった。あるとき、何の気なしに見直した写真集──米国の写真家ロバート・フランク(Robert Frank)の写真集に釘付けになってしまった。ああ、これこそが自分が探し求めていた写真の方向性ではないのか。ホッとひと息ついた瞬間であった。その時、写真を撮る仕事を始めて10年近くたっていただろうか。
ロバート・フランク自身は写真業界では有名であるが、ナクトウェイやサルガドのように映画の題材にはならないであろう。なぜかというと、彼は、日常を淡々と撮り続ける写真家だからだ。派手さがないのである。だからこそ私は、そんな彼の日常を撮した写真が好きなのである。
ロバート・フランクの写真を見ていると、彼の見つめる視線の先が浮かんでくる。写真家が撮る写真の中に、社会・時代の本質が見えてきそうなのである。彼の代表作でもある写真集“THE AMERICANS”のページをめくると、ただ単に米国のありふれた日常が次々に現れる。圧倒されないが、何度も何度も見直してしまう、ささやかな写真群がそこにある。
ロバート・フランクの写真集は、その一枚一枚の素描の確かさに加えて、写真を並べる順番や編集など、フィルムカメラを使っていた時代の作品として完結している。今振り返って見ると、この写真集を眺めてから自分の撮る写真の傾向がはっきりと変わっていった。
デジタルカメラが全盛の今という時代になっても、フィルムカメラから写真を始めた自分は、今ここでしか撮ることのできないそんな時代を写すイメージを撮りたいと思う。しかし、写真家が写真論を語り始めるのは愚の骨頂である。それは評論家の域である。写真家は、カメラを持って現場に行き、現場に立っただけの写真ではなく、その場を画像として記録し、記憶に残す作業をするのが務めなのである。身体が動く限り現場に行こう。いつもそのことをかみしめておきたい。
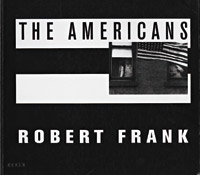 |
ロバート・フランクの写真集、“THE AMERICANS”の表紙。 |
 |