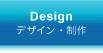|
Vol.194/2014/03
|
「抗いの彷徨(4)」

画面構成に気をつかった例。何を言いたいのか、撮し手よりも見る側の想像力に判断を委ねようとしたイメージ。
「写真を撮る」というのは、実は非常にエキサイティングな行為でもある。見知らぬ人にカメラを向けて、顔をしかめられ嫌がられる場合ももちろんある。それでも、撮るぞ撮るぞというオーラを発しながら被写体に近づき、息のかかるほどの距離でシャッターを押せた時の快感はたまらないものである。撮影する一瞬、被写体との間に特別な磁場を作り上げ、撮影後は被写体と笑顔で目と目を合わせる。そんなとき、たとえ言葉は通じなくとも、レンズを通して会話できた、一体感を味わったという感覚を得ることがあるからだ。痺れる行為である。その結果、そこそこ満足のいくイメージを捉えることができたら、それこそ人を撮るという行為がやめられなくなっていく。
そのうち広角の24mmレンズでは飽き足らず、20mmの超広角レンズへとエスカレートしてしまった。やがて、私のメインレンズは16mm〜35mmのズームレンズとなり、主に16mmという超々広角の画角で写真を撮るようになってしまった。
モノを見る例えとして、「鳥のように事象を俯瞰して見る。蟻のように現象を目の前で見る」といわれることがある。私はそれに「ゾウガメのように粘り強く《見続ける》」と付け加えることにしている。
学生時代に、ある教師が何気なく言った一言が忘れられない。
「成功しようと思ったら、人ができないことをすること(才能のある人ならば)。才能がないと思う人は、人ができることを人より先にすることだ」と。
これを聞いた私は、この2つとも自分には当てはまらないな、と思った。自分自身、取り立てて成功者になろうとは思っていない。それでも、自分の好きなことをするために、いったい何ができるのか。
「人が諦めることを簡単に諦めないで、自分のペースでやり続けること」くらいだろうか。そう、ゾウガメが生き続けるように、息長く。そう思って写真を撮り続けている。
(続く)
 |